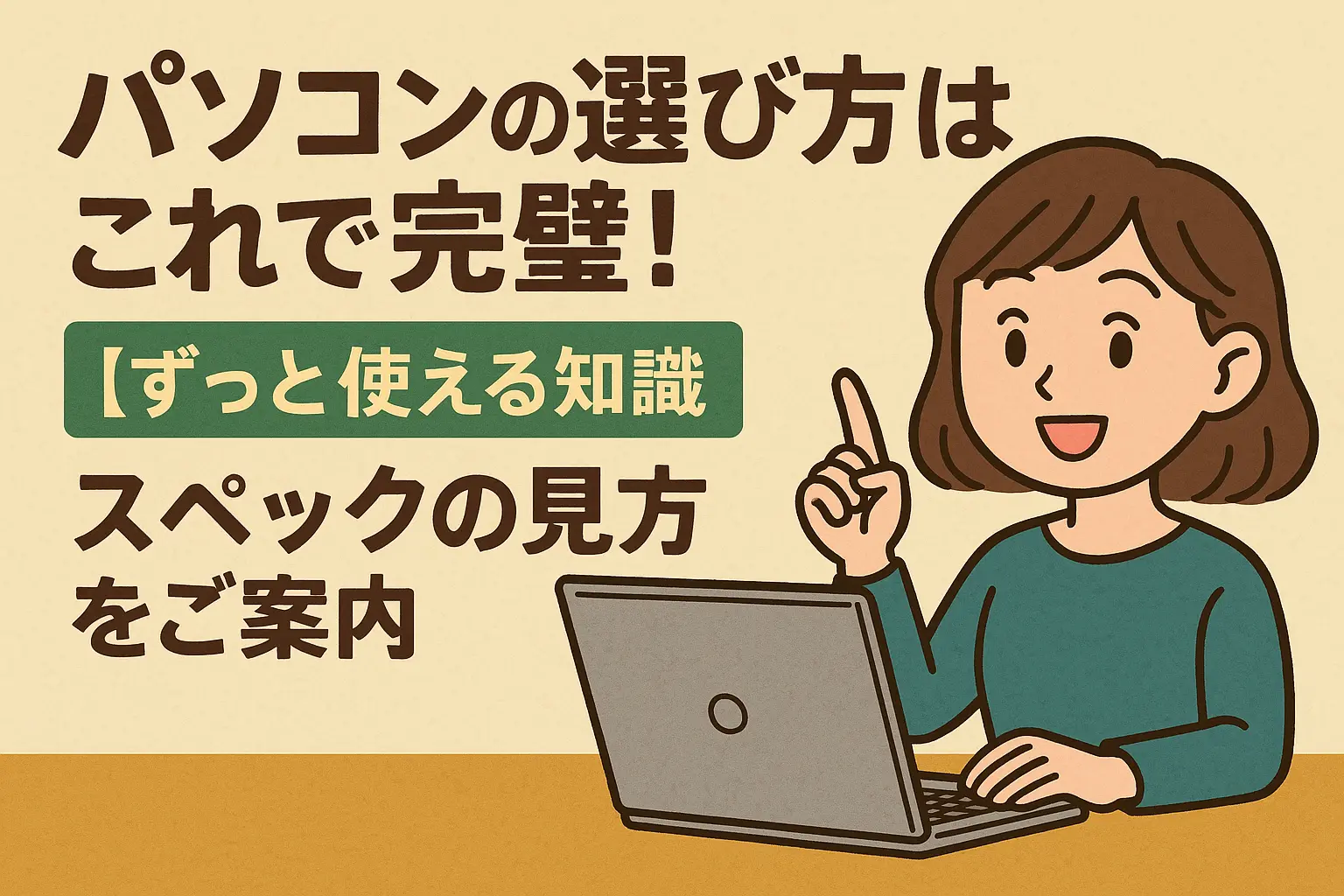はじめまして。パソコン選びに悩んでいる方、あるいはこれからPCスペックをしっかり理解して自分に最適なパソコンを購入したい方に向けて、この記事では「パソコンの選び方」を徹底的に解説します。
近年はオンライン学習やリモートワークなど、さまざまなシーンでパソコンを活用する機会が増え、初心者のみならず中級者以上の方でも「どんなスペックのパソコンを選べばいいのか」迷うことが多いです。
そこで本記事では、CPU・メモリ・ストレージ・GPU・ディスプレイ・Microsoft Officeの選び方など、パソコン購入の際にチェックすべき主要ポイントをまとめました。初心者の方でも理解しやすいように専門用語をかみ砕いて解説し、さらに上級者にもうなずいていただける内容を盛り込みます。
結論としては、以下のポイントを押さえるだけでほとんどの失敗が防げます。
- OSの選択(WindowsかMacか)
- ノートパソコンかデスクトップか
- CPUやメモリ、ストレージなどの基本スペック
- 使用用途に応じたGPU(グラフィックボード)の要不要
- ディスプレイのサイズ・解像度・発色方式(グレア / ノングレア)
- Microsoft Officeの付属・サブスク・アカデミックライセンス
- 拡張性や周辺機器との連携を見越した選択
まずはざっくりと全体像を把握して、次のセクションから詳しくご紹介していきます。ぜひ最後までご覧いただき、最適なパソコンをゲットしてください。
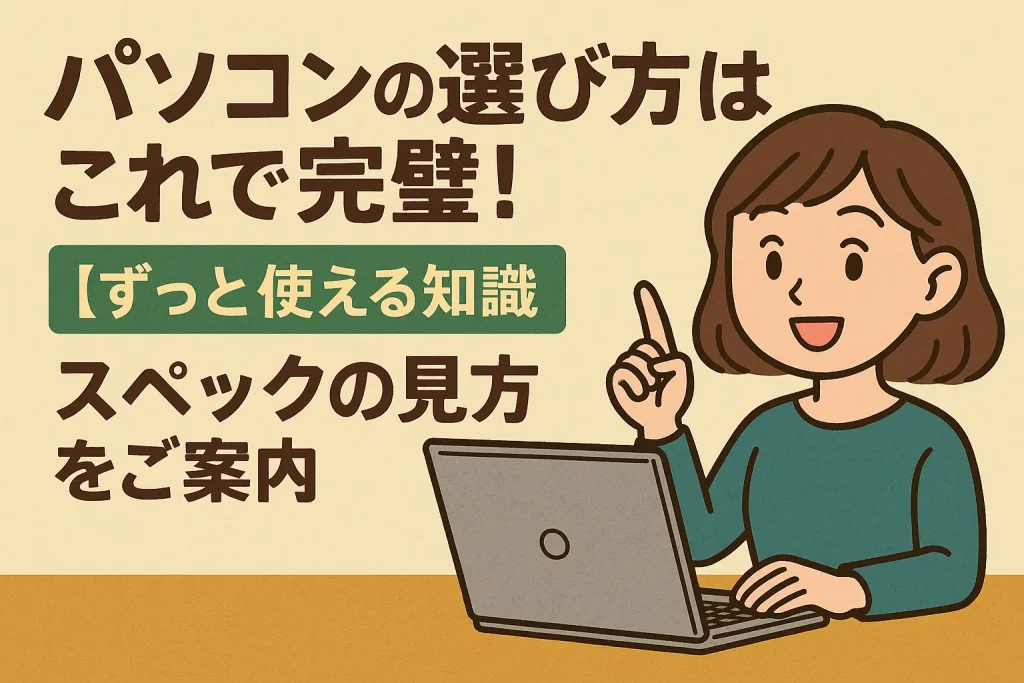
1. WindowsかMacか、それとも?
パソコン選びの第一歩となるのがOS(オペレーティングシステム)の選択です。日本国内ではWindows PCが圧倒的に普及しており、Microsoft Officeなどビジネスソフトの対応が充実していることが特徴です。一方で、クリエイティブ用途やデザイン性の高さを好むユーザーからはMacも根強い人気があります。
- Windows PC
- 普及率が高く、トラブル時の情報が豊富
- 仕事や学校で指定ソフトがWindows専用のことが多い
- ゲームもWindows用が多い
- Mac PC
- Apple製品(iPhone、iPad)との連携がスムーズ
- クリエイティブ系ソフトとの相性を重視する方に向いている
- デザイン面がスタイリッシュ
ここで「どちらが優れているか?」というより、「どちらがご自身の用途や環境に合うか」を軸に考えましょう。Windows特有のソフトを使う予定がある場合や、周囲にWindowsユーザーが多い場合はWindowsがおすすめです。逆に、Apple製品で統一したエコシステムを作りたい場合やデザイン作業がメインであればMacも視野に入れてください。
🌸新生活応援Ver(親しみやすいトーン)
📢春からの新生活、PC選びで迷ってない?
これを見れば、”買って後悔しない1台”がすぐわかる✨
▶︎ 【2025年春最新版】新生活者 パソコン ベスト5|おすすめモデルからAI性能まで徹底解説
2. ノートかデスクトップかの選択
次はパソコンの形態をどうするかという問題です。ノートパソコン(ラップトップ)にするか、デスクトップパソコンにするかを決めます。
- ノートパソコン
- 持ち運びできる
- 設置スペースが少なくて済む
- コンパクトだが拡張性はやや低い
- デスクトップパソコン
- CPUやGPUなどのパーツ交換、アップグレードがしやすい
- モニターやキーボードの単体交換が可能
- 据え置き前提なので設置スペースを確保する必要あり
最近のノートパソコンは性能がかなり上がっており、一般的な仕事や学習レベルであれば十分高速に動きます。自宅メインで、かつ拡張性や高い性能を重視するならデスクトップを選ぶのも良いでしょう。
もし、「持ち運びたい場面もあるけれど、家では大画面で作業したい」という方は、ノートパソコン+外付けモニター(デュアルモニター)を利用する方法がおすすめです。
3. PC性能を左右する3大要素:CPU・メモリ・ストレージ
パソコンの要となるのが以下の3つのパーツです。
- CPU(頭脳)
- メモリ(作業台)
- ストレージ(保存場所)
これらを押さえるだけでも、「何がどれくらい性能に関係するのか」がクリアになります。
3-1. CPU(頭脳)
パソコン全体の処理をコントロールする中心的存在で、「頭脳」に例えられるのがCPUです。近年の主流は以下の2社のCPUとなります。
- Intel製:Core i シリーズ
- Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 などのグレードがある
- 世代ごとに性能が大幅に異なる(例:第12世代、第13世代など)
- AMD製:Ryzen シリーズ
- Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 などのグレードがある
- 同じく世代ごとに性能が進化(例:第5世代など)
CPUを選ぶときは、「グレード」(i3, i5, i7 など)だけでなく、「世代」(第10世代、第12世代など)も確認しましょう。世代が大きく異なると、同じi5同士でも性能差が大きく出ます。
また、2023年末にはIntelの新ブランド「Core Ultra」シリーズも登場しています。こちらはグラフィックス機能とAI機能が強化され、省電力化が進んだ最新アーキテクチャです。予算に余裕があるなら、Core Ultraシリーズを選ぶのも一つの手です。
CPUスコア(PassMark)を活用する
CPU性能を比較する一つの指標として「PassMark」などのCPUベンチマークスコアをチェックする方法があります。これは数値が高いほどハイパフォーマンスであることを示します。
目安としては、1万〜2万点あたりあれば、一般的な作業(Word、Excel、Zoom会議、ウェブブラウジング、動画視聴)を同時に行ってもスムーズに動作します。少し高度な動画編集や軽いゲームも可能です。
3-2. メモリ(作業台)
メモリ(RAM)は、CPUの処理作業を一時的に置いておく「作業台」です。
- 8GB:最低限の一般作業なら可能
- 16GB以上:余裕を持って複数のタスクを並行できる
オンラインミーティングをしながら他の作業を行う場合や、大きめのファイルを扱う動画編集・画像編集をする可能性があるなら、16GB以上をおすすめします。
3-3. ストレージ(保存場所)
ストレージには、主にSSD (Solid State Drive) とHDD (Hard Disk Drive)の2種類があります。現在は断然SSDが主流です。
- SSD(特にM.2 NVMe)
- 高速起動・高速読み込み
- 振動や衝撃に強い
- 動作音も静か
- HDD
- 安価で大容量
- 読み込み速度はSSDに劣る
特に最近のノートパソコンはM.2 NVMe規格のSSDを搭載しており、起動やソフトの読み込みが非常に速いです。容量は512GBを基本に考えると安心。動画や高解像度画像を大量に保存したい場合は1TB以上にするか、外付けSSDを活用しましょう。
【徹底解説】初心者でもわかる!M.2 SSDの正しい選び方と爆速化のポイント
🌸新生活応援Ver(親しみやすいトーン)
📢春からの新生活、PC選びで迷ってない?
これを見れば、”買って後悔しない1台”がすぐわかる✨
▶︎ 【2025年春最新版】新生活者 パソコン ベスト5|おすすめモデルからAI性能まで徹底解説
4. GPU(グラフィックボード)の必要性
GPU(Graphics Processing Unit)は映像処理に関わる部分で、以下の2つに分けられます。
- CPU内蔵GPU
- CPUの中に組み込まれている
- WordやExcel、Webブラウジング、動画視聴などは十分対応できる
- グラフィックボード(専用GPU)
- 高度な3D処理、動画編集、ゲームプレイが必要な方に必須
- GPUチップ+VRAM(映像処理専用メモリ)を備えている
たとえば、3Dゲームや本格的な動画編集、細かなイラスト・3D CADなどをする方は、NVIDIA GeForceシリーズ(RTX / GTX)などを搭載したパソコンを選ぶと快適に作業ができます。
- GeForce RTX:レイトレーシング機能が充実しており、写実的な光や影を再現可能
- GeForce GTX:RTXの前世代。初心者の動画編集やイラスト制作にも十分対応できる
GPUの性能を大きく左右するのは世代とグレードです。たとえばRTX 30xxシリーズよりもRTX 40xxシリーズのほうが新しく性能が高い傾向にあります。また、後につく数字が大きいほど(RTX 4060、4070、4080、4090など)グレードが上がり、処理能力も上がっていきます。
5. ディスプレイ仕様の選び方
パソコンの画面選びも重要なポイントです。ノートパソコンの場合は最初からディスプレイが内蔵されているため、解像度や表示方式に注目する必要があります。
5-1. グレアかノングレアか
- グレア(光沢あり)
- 発色が鮮やか
- 写真や映像が鮮明で美しく見える
- 周囲の光を映し込みやすく、目が疲れやすい場合もある
- ノングレア(光沢なし)
- 映り込みが少ない
- 長時間見ても疲れにくい傾向
- 色味が落ち着いて見える
長時間の作業ならノングレア、映像重視ならグレア、といった基準が一般的ですが、最終的には好みで選んで問題ありません。
5-2. 解像度の違い
- フルHD(1920×1080)
- 一般的なノートPCではスタンダードな解像度
- コスパも良く、作業領域としても十分
- WUXGA(1920×1200)
- 縦方向がやや広いので、作業効率が少し上がる
- 4K(3840×2160)
- 映像編集や、高精細な表示を求める場合は◎
- ただしGPU性能が求められ、バッテリー消費も多い
4K対応ディスプレイを使うなら、グラフィックボードやCPUにもそれなりのハイスペックが要求される点に留意しましょう。
5-3. ディスプレイサイズ
- 15.6インチ:ノートパソコンでは一般的なサイズ。作業領域をしっかり確保できる
- 13〜14インチ:携帯性を重視する方に人気。軽量かつバッテリー持ちも良い傾向
- 17インチ以上:重量が増すため、持ち運びより据え置き用途向け
サイズは作業のしやすさと携帯性のトレードオフです。用途に合わせて選びましょう。
【2025年最新】モバイルモニターおすすめ選び方完全ガイド|失敗しない7つのポイントと注意点
6. DVDドライブや周辺機器の有無
近年のノートパソコンでは、DVDドライブ(光学ドライブ)を搭載しないモデルが増えています。音楽や映画はネット配信が主流となり、不要だと考えるユーザーが増えたためです。必要な方は以下をチェックしてください。
- Blu-rayドライブ:Blu-ray、DVD、CDの読み書き可
- DVDスーパーマルチドライブ:DVD、CDの読み書き可(Blu-rayは不可)
光学ドライブ非搭載モデルでも、外付けドライブを後から購入・接続できます。USBポートなどは事前に数を確認しておきましょう。
7. Microsoft Officeの選び方
ビジネスや学業で利用機会の多いMicrosoft Office(Word、Excel、PowerPointなど)は、購入時の大きなポイントになる場合が多いです。Officeの導入方法は大きく3つに分かれます。
7-1. プリインストール版
パソコン本体を買う際に、あらかじめOfficeが付属しているもの。
- メリット
- セットアップの手間が少なく、買ってすぐに使える
- 使い切りライセンスなので、そのPCが壊れるまで期限なく利用できる
- デメリット
- 他のPCへOfficeを移行できない
- バージョンアップはされず、いずれサポート終了のタイミングがくる
7-2. パッケージ版(永続ライセンス)
パソコンとは別に店舗やオンラインでOfficeライセンスを購入する方法。
- メリット
- PCの付属品ではないため、万が一パソコンが壊れても他のPCで再利用できる
- 買い切りで追加料金がかからない(サポート終了までは)
- デメリット
- 常に最新バージョンを使えるわけではなく、サポート終了がくる
- 購入の手間がやや面倒
7-3. サブスクリプション版(Microsoft 365)
月額または年額で使用料を支払うタイプです。
- メリット
- 常に最新バージョンが使える。サポート終了の心配がない
- 1TBのクラウドストレージ(OneDrive)が利用できる
- 1契約で複数デバイス(5台まで)にインストールできる
- デメリット
- 定額を払い続ける必要がある
学校によっては在学中、無償でMicrosoft Officeを利用できるプランを提供しているケースもあります。新入学でPCが必要な方は、あらかじめ学校に確認しておきましょう。卒業後は自分で購入する必要がありますが、在学中は不要かもしれません。
8. 購入時に参考になる情報ソース
パソコンを検討するときは、実機を取り扱う家電量販店やパソコン専門店へ足を運んで、実際の使い心地やキーボードの配置などを確かめると失敗が減らせます。
また、CPUやGPUの性能比較はオンラインでも確認可能です。たとえば、PassMark などのベンチマークサイトを利用すると、数値化された性能指標をチェックできます(検索や閲覧のみ英語サイトでも容易にできます)。
各メーカー公式サイト(たとえばMicrosoft公式サイト)では、最新のOffice情報やサポート内容などを常にアップデートしているので、一度は目を通してみるとよいでしょう。
9. まとめ
本記事ではパソコンの選び方として、以下のポイントを解説しました。
- OSの選択:Windowsなら汎用性が高く、学校や仕事での互換性も広い。MacならApple製品との連携やデザイン性が高い。
- ノートかデスクトップか:携帯性重視ならノート。カスタマイズ性や性能追求ならデスクトップ。
- CPU・メモリ・ストレージ
- CPUはCore i5やRyzen 5以上(できれば第12世代以降)を目安にすると快適
- メモリは16GB以上を推奨(8GBは最低限)
- ストレージはSSD(M.2 NVMe)で512GB以上が安心
- GPUの必要性:高度な3Dゲームや動画編集なら専用のグラフィックボードが必要
- ディスプレイ:解像度(FHD〜4K)と発色方式(グレア / ノングレア)は好みと用途で選ぶ
- DVDドライブの有無:最近は非搭載が多いが、必要なら外付けドライブでも対処可
- Microsoft Officeの導入方法:プリインストール版、パッケージ版(永続ライセンス)、サブスクリプション版(Microsoft 365)から選択
- 公式情報や実店舗の活用:ベンチマークサイトやメーカー公式サイトを参照し、必要スペックを見極める
これらのポイントを踏まえれば、初心者から上級者まで自分に合ったPCを見つける際の指針になります。「何をしたいのか」「どのくらい予算があるのか」を自問自答しながら、パーツのスペックを照らし合わせてください。
10. 免責事項
- 本記事の情報は公開日時点の参考情報をもとに作成しています。製品の仕様や価格は予告なく変更される場合があります。
- 本記事では一般的な情報提供を目的としており、特定の製品の購入や利用を強制・保証するものではありません。
- 実際の購入判断につきましては、ご自身の責任とご予算・目的に応じて検討いただきますようお願いいたします。
- 本記事の内容を利用したことによる損害やトラブルに関しては、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
パソコンのスペックをしっかり理解し、自分に合った一台を選ぶことができれば、作業効率も快適さも飛躍的に向上します。ぜひ本記事のポイントを参考に、後悔のないパソコン選びを実現してください。