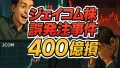「出先でもデュアルディスプレイで作業効率を上げたい」「ノートPCの画面だけでは狭すぎる」「スマホやゲーム機の画面を大きく映したい」
近年、テレワークやハイブリッドワークの普及、そして多様化するデバイスとの連携ニーズの高まりから、「モバイルモニター(モバイルディスプレイ)」の需要が急速に拡大しています。しかし、いざ選ぼうとすると、画面サイズ、解像度、接続方法、スタンドの形状、価格帯など、チェックすべき項目が多く、どれを選べば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
安価なものから高機能なものまで、まさに”沼”とも言えるほど多くの製品が存在するモバイルモニター。選択を誤ると「思ったより重くて持ち運べない」「ケーブル1本で繋がると思ったのに繋がらない」「角度調整ができなくて見づらい」といった失敗に繋がりかねません。
この記事を読めば解決できること
- モバイルモニター選びで失敗しないための7つの重要ポイント
- 画面サイズ、画質、接続方法など、あなたに最適なスペックの見極め方
- 意外と見落としがちなスタンド形状や付属品の重要性
- 価格帯ごとの特徴と選び方のコツ
- 安心して使えるメーカー選びのヒント
この記事では、数多くのモバイルモニターを実際に試してきた経験(まさに”沼”の主の視点!)に基づき、最新の情報と選び方のツボを7つのポイントに凝縮して徹底解説します。この記事を読めば、あなたにとって最適な一台を見つけ、快適なモバイル環境を手に入れることができるはずです。
【先に結論】モバイルモニター選び 7つの最重要ポイント
- 価格帯と予算: 1万円台後半~4万円前後が中心。機能と予算のバランスを見極める。
- 画面サイズ: 持ち運び重視なら13.3~14インチ、据え置き併用なら15.6インチ。用途に合わせて選ぶ。
- 画質(解像度・表面処理): 用途に合わせてフルHDか4Kか、光沢か非光沢(アンチグレア)かを選ぶ。
- タッチ対応の有無: 必要なら選択肢に。価格と重量増も考慮。
- スタンド形状: 最重要! 角度調整が自由な「自立式スタンド」が断然おすすめ。
- 接続端子と電源: USB Type-C(映像出力対応)が便利。PCとの相性や電源供給も要チェック。
- 付属品とメーカー: 必要なケーブルが揃っているか、信頼できるメーカーかを確認。
それでは、各ポイントを詳しく見ていきましょう。
ポイント1:価格帯と予算 – モバイルモニターはいくらで買える?
まず気になるのが価格です。モバイルモニターの価格帯は、機能やサイズによって幅がありますが、大まかな目安を知っておくことが大切です。
- エントリークラス(1万円台後半~2万円台前半):
- 最も一般的な価格帯。フルHD解像度、13.3インチ~15.6インチのモデルが多い。
- 基本的な機能は備わっており、コストパフォーマンスに優れる。
- ただし、スタンドがカバー兼用タイプだったり、輝度や色域が控えめな場合もある。
- 最近では、この価格帯でも自立式スタンドを採用するモデルが増えてきている。
- 目安予算: 17,000円~25,000円程度
- ミドルクラス(2万円台後半~3万円台):
- 画質(高輝度、広色域)や、筐体の質感、スピーカー品質などが向上する。
- タッチ対応モデルや、より軽量・薄型なモデルも選択肢に入ってくる。
- 自立式スタンド搭載モデルが主流。
- 目安予算: 25,000円~35,000円程度
- ハイクラス(4万円以上):
- 4K解像度、有機ELパネル、高リフレッシュレート(ゲーミング用途)、高精度なタッチパネルなどを搭載したモデル。
- クリエイティブな作業や、画質に徹底的にこだわりたい方向け。
- 大手PCメーカー製の信頼性が高いモデルもこの価格帯に多い。
- 目安予算: 40,000円以上
【表1】価格帯別 モバイルモニターの特徴比較
| 価格帯 | 目安予算 | 主な特徴 | おすすめユーザー |
|---|---|---|---|
| エントリークラス | 1万円台後半~2万円台前半 | フルHD、カバー兼用スタンド or 低価格自立スタンド、基本機能 | コスパ重視、一般的な用途 |
| ミドルクラス | 2万円台後半~3万円台 | フルHD(高画質)、自立スタンド、タッチ対応モデルも、質感向上 | バランス重視、画質や使い勝手にもこだわる人 |
| ハイクラス | 4万円以上 | 4K、有機EL、高リフレッシュレート、高精度タッチ、大手メーカー製、高品質筐体 | クリエイティブ作業、最高画質を求める人、予算に余裕あり |
選び方のポイント
- まずは予算の上限を決める: 3万円程度の予算があれば、かなり選択肢が広がり、満足度の高いモデルを選びやすくなります。
- Amazon等での注意点: 1万円台前半の安価なモデルもありますが、スタンドがカバー兼用タイプであったり、サポート体制が不明確な場合があります。後述する「スタンド形状」は非常に重要なので、安さだけで飛びつかず、スタンドがしっかりした自立式タイプを選ぶのがおすすめです。自立式を選ぶと、必然的に1万円台後半以上が中心となります。
- 4Kやタッチ対応が必要か?: これらの機能は価格を押し上げる要因です。本当に必要か、予算と照らし合わせて検討しましょう。
ポイント2:画面サイズ – 持ち運びやすさと作業領域のバランス
モバイルモニター選びで最も重要な要素の一つが画面サイズです。主に以下の3つのサイズが主流です。
- 13.3インチ:
- メリット: 最も小型・軽量で持ち運びに最適。多くのビジネスバッグに легко (легко – ロシア語で「簡単に」) 収まる。
- デメリット: 画面表示領域がやや狭い。
- おすすめな人: とにかく携帯性を最優先したい人。外出先での使用がメインの人。
- 14インチ:
- メリット: 13.3インチと携帯性(重量・サイズ感)は大きく変わらないが、表示領域は少し広がる。持ち運びと作業領域のバランスが良い。
- デメリット: 15.6インチに比べると作業領域は狭い。
- おすすめな人: 持ち運びもするが、作業領域もある程度確保したい人。迷ったらこのサイズがおすすめ。
- 15.6インチ:
- メリット: ノートPCで一般的なサイズ。広い作業領域を確保でき、据え置きのサブモニターとしても快適。
- デメリット: サイズが大きく、重くなるため、携帯性は劣る。ビジネスバッグによってはギリギリか入らない場合も。
- おすすめな人: 外に持ち出す頻度が低い人。家の中で移動させて使うことが多い人。作業領域の広さを重視する人。
【表2】画面サイズ別 モバイルモニターの特徴比較
| 画面サイズ | メリット | デメリット | おすすめユーザー | 携帯性(目安) | 重量(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.3インチ | 最も小型・軽量、携帯性抜群 | 画面がやや狭い | 携帯性最優先、外出メイン | ◎ | 約600g~700g |
| 14インチ | 携帯性と作業領域のバランスが良い | 15.6インチよりは狭い | 迷ったらコレ、持ち運びも作業もある程度重視 | 〇 | 約650g~750g |
| 15.6インチ | 広い作業領域、据え置きサブとしても快適 | サイズが大きく重い、携帯性は劣る | 持ち運び頻度が低い、作業領域重視、家メイン | △ | 約850g~1kg以上 |

重さの比較(例)
- 13.3インチ: 約600g~700g
- 14インチ: 約650g~750g (13.3インチと大差ないモデルも多い)
- 15.6インチ: 約850g~1kg以上 (14インチから明確に重くなる)
※上記はあくまで目安であり、製品によって異なります。
選び方のポイント
- 持ち運び頻度で決める: ほぼ毎日持ち運ぶなら13.3インチか14インチ。家の中での移動がメインなら15.6インチでもOK。
- カバンに入るか確認: 特に15.6インチは、ケースに入れるとさらに大きくなるため、手持ちのカバンに収納できるか事前に確認しましょう。
- 迷ったら14インチ: 13.3インチと14インチのサイズ・重量差は比較的小さいため、迷ったら少しでも画面が大きい14インチを選ぶのがおすすめです。14インチから15.6インチへのサイズ・重量増は顕著なので、ここは明確な選択が必要です。
ポイント3:画質 – 解像度と表面処理を用途で選ぶ
画面の見やすさ、美しさを左右するのが画質です。主に「解像度」と「表面処理」をチェックしましょう。
【表3】解像度・表面処理の比較
| 項目 | 種類 | メリット | デメリット | おすすめ用途/ユーザー |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | フルHD (1920×1080) | 主流で十分な解像度、価格が手頃 | 4Kほどの精細さはない | 一般的な用途、コスト重視 |
| 4K (3840×2160) | 非常に高精細、緻密な表示が可能 | 価格が高い、PC側の負荷も考慮 | 写真・動画編集、クリエイティブ作業、高画質映像鑑賞 | |
| 表面処理 | 光沢 (グレア) | 色鮮やか、黒が締まる、映像鑑賞向き | 映り込みやすい、指紋が目立つ | 写真・動画鑑賞、タッチ操作したい人 |
| 非光沢 (ノングレア/アンチグレア) | 映り込みが少ない、目が疲れにくい、作業向き | 光沢より色の鮮やかさ・コントラストが劣る場合あり | 長時間作業、文書作成、映り込みが気になる人 |
解像度
- フルHD (1920×1080):
- 現在の主流。ほとんどのモバイルモニターがこの解像度。
- 一般的な事務作業、Webブラウジング、動画視聴などには十分な解像度。
- 価格も手頃なモデルが多い。
- おすすめな人: コストを抑えたい人。一般的な用途がメインの人。
- 4K (3840×2160):
- フルHDの4倍の画素数を持つ高精細な解像度。
- 写真編集、動画編集、CADなど、緻密な表示が求められる作業に適している。
- 映像コンテンツを高画質で楽しみたい人にもおすすめ。
- 価格は高くなる傾向がある。
- おすすめな人: クリエイティブな作業をする人。高画質な映像を楽しみたい人。予算に余裕がある人。

表面処理
- 光沢 (グレア):
- メリット: 色が鮮やかに見え、黒が引き締まる。写真や動画の鑑賞に向いている。
- デメリット: 外光や照明が映り込みやすい。指紋が目立ちやすい。
- タッチ対応モデルは、ほとんどが光沢タイプ。
- おすすめな人: 写真や動画をきれいに見たい人。タッチ操作をしたい人。
- 非光沢 (ノングレア / アンチグレア):
- メリット: 外光の映り込みが少なく、目が疲れにくい。長時間の作業に向いている。
- デメリット: 光沢タイプに比べると、色の鮮やかさやコントラストがやや劣る場合がある。
- おすすめな人: 仕事や文書作成など、長時間の作業がメインの人。映り込みが気になる人。
選び方のポイント
- 基本はフルHDでOK: よほど高精細な作業をしない限り、フルHDで十分快適に使えます。
- 4Kは必要なら: 明確な目的(写真・動画編集など)がある場合や、予算が許す場合に検討しましょう。高画質なモデルは、輝度や色再現性も高い傾向があります。
- 作業メインなら非光沢: 長時間画面を見るなら、目の負担が少ない非光沢がおすすめです。
- 映像美重視なら光沢: 写真や動画の色鮮やかさを重視するなら光沢が良いでしょう。
- タッチ対応はほぼ光沢: タッチ対応モデルを選びたい場合は、基本的に光沢になります。どうしても非光沢が良い場合は、別途非光沢の保護フィルムを貼るという方法もありますが、ぴったり合うサイズを探す手間や、タッチ感度が若干変わる可能性も考慮しましょう。
ポイント4:タッチ対応 – あると便利?必要性を見極める
一部のモバイルモニターには、スマートフォンのように画面を直接タッチして操作できる「タッチ対応」モデルがあります。
タッチ対応のメリット・デメリット
- メリット:
- 直感的な操作が可能になる(スクロール、拡大縮小など)。
- 接続するPCがタッチ非対応でも、モニター側でタッチ操作が可能になる。
- プレゼンテーションなどで、画面を指し示しながら説明しやすい。
- デメリット:
- 価格が高くなる傾向がある。
- タッチパネル層があるため、若干重く、厚くなる場合がある。
- 表面処理が光沢(グレア)タイプがほとんど。

選び方のポイント
- PCが非タッチでもタッチ操作が可能に: 「ノートPCは軽さ重視で非タッチモデルを選んだけど、たまにタッチ操作したい」という場合に便利です。
- 必要性をよく考える: タッチ操作に明確なメリットを感じるか、予算と重量増を許容できるかを検討しましょう。「あれば便利かも」程度であれば、無理に選ぶ必要はないかもしれません。
- 4K+タッチモデルは高価格帯: 高画質とタッチ操作の両方を求める場合は、ハイクラスの価格帯になることを覚悟しましょう。
ポイント5:スタンド形状と筐体の質感 – 使い勝手と満足度を左右する最重要ポイント!
モバイルモニター選びにおいて、画面サイズや画質と同じくらい、いや、それ以上に重要かもしれないのが「スタンドの形状」です。 ここを妥協すると、後々使いづらさを感じることになります。
【表4】スタンド形状の比較
| スタンド形状 | メリット | デメリット | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| カバー兼用スタンド | 別途スタンド不要、比較的安価 | 角度調整がほぼ不可、安定性に欠ける場合あり | △ |
| 自立式スタンド | 角度調整が自由自在、安定性が高い | 価格が高くなる傾向 | ◎ |
スタンド形状の種類
- カバー兼用スタンド:
- 付属の保護カバーが折り畳み式のスタンドになるタイプ。
- 初期のモバイルモニターに多かった形状。
- メリット: 別途スタンドが不要。比較的安価なモデルに多い。
- デメリット: 角度調整がほとんどできない、できても段階が限られる。 安定性に欠ける場合がある。
- 結論: これから買うなら、このタイプは積極的にはおすすめしません。
- 自立式スタンド (キックスタンドタイプ):
- モニター本体の背面に、角度を自由に調整できるスタンドが内蔵されているタイプ。
- メリット: 角度調整の自由度が非常に高い。 安定性が高い。設置が簡単。
- デメリット: カバー兼用タイプより価格が高くなる傾向がある。
- 結論: これから買うなら、断然このタイプがおすすめです! 見る場所や姿勢に合わせて最適な角度に調整できるため、圧倒的に快適です。

選び方のポイント(スタンド)
- 迷わず「自立式スタンド」を選ぶ: 少々価格が高くなったとしても、角度調整の自由度は使い勝手に直結します。電車の中、カフェのテーブル、自宅のソファなど、様々な場所で快適に使うためには、自立式スタンドが必須と言っても過言ではありません。
筐体の質感
価格差は、筐体の質感にも表れます。
- 安価なモデル: プラスチック感が強い、ベゼル(額縁)が太い、本体の一部が少し浮いている(パカパカする)など、価格なりの部分が見られることがあります。実用上問題ないことが多いですが、所有満足度は低いかもしれません。
- 高価なモデル: 金属素材が使われていたり、ベゼルが狭くスタイリッシュだったり、全体的に剛性感があり、しっかりした作りになっています。
選び方のポイント(質感)
- 実用性重視なら割り切りも: 「見た目や質感より、価格と機能」という場合は、安価なモデルでも十分役立ちます。
- 所有満足度も重視するなら: 細部の作り込みや質感にもこだわりたい場合は、ある程度の価格帯のモデルや、信頼できるメーカーの製品を選ぶと良いでしょう。レビューなどを参考に、質感についてもチェックするのがおすすめです。
ポイント6:接続端子と電源 – ケーブル1本で繋がる?注意点は?
モバイルモニターをPCや他のデバイスと接続するための端子と、電源供給の方法も重要なチェックポイントです。
【表5】主な接続端子と特徴
| 端子種類 | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| USB Type-C (DP Alt Mode) | 映像+電源をケーブル1本で供給可能 (条件あり) | PC/スマホ側も対応必須、電力不足で映らない場合あり、指定ポートがある場合も |
| HDMI (Mini/Micro) | 多くの機器に対応する汎用映像端子 | 別途モニターへの電源供給が必須、変換ケーブルが必要な場合が多い |
主な接続端子
- USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応):
- 最もおすすめの接続方法。
- 対応するPCやスマホと接続すれば、映像信号と電源供給をケーブル1本で行える場合が多い。
- ただし、PC側のUSB Type-Cポートも映像出力(DisplayPort Alternate Mode)と電源供給(USB Power Delivery)に対応している必要があります。
- モニターによっては、複数のType-Cポートがあり、映像入力用と電源入力用が指定されている場合があるので注意。
- HDMI (Mini HDMI / Micro HDMIが多い):
- 多くのノートPCやゲーム機、レコーダーなどが搭載している汎用的な映像端子。
- HDMI接続の場合は、別途モニターへの電源供給が必要になります(通常は付属のACアダプターやPCのUSBポートからType-C経由で給電)。
- モバイルモニター側は省スペースのため、Mini HDMIやMicro HDMI端子になっていることが多い(変換ケーブルが付属しているか確認)。

電源供給に関する注意点 (USB Type-C接続)
USB Type-Cケーブル1本で接続できるのがモバイルモニターの大きな魅力ですが、必ずしもうまくいくとは限りません。
- PC側の出力不足: PC側のUSB Type-Cポートからの電力供給が、モニターが必要とする電力に満たない場合、画面が映らない、ちらつく、明るさが足りないといった現象が起こることがあります。特に画面サイズの大きいモニターほど、消費電力も大きくなる傾向があります。
- モニター側の要求電力: モニターが必要とする電力が大きい場合も同様です。
- ケーブルの問題: 映像出力に対応していない安価なUSB Type-Cケーブルを使用すると、映像が出力されません。必ずモニターに付属しているUSB Type-Cケーブルを使用しましょう。
もしUSB Type-Cケーブル1本で映らなかった場合の対処法:
- PCの別のUSB Type-Cポートを試す: ポートによって性能が異なる場合があります。
- モニターにACアダプターを接続する: モニターに付属のACアダプター(または別途用意したUSB PD充電器)を接続し、モニターに電源を供給した上で、PCとUSB Type-Cケーブルで接続します。これにより、PCからの電力供給に頼らずに映像を出力できます。
- HDMIで接続する: HDMIで接続し、別途モニターに電源を供給します。
選び方のポイント
- USB Type-C (DP Alt Mode) 対応は必須: ケーブル1本で接続できる可能性のあるUSB Type-Cポートは、最低1つは搭載されているモデルを選びましょう。
- HDMIもあると安心: ゲーム機など、Type-C映像出力に対応していない機器も接続したい場合は、HDMI端子も搭載されていると便利です。
- PCとの相性は使ってみないと不明な部分も: 残念ながら、カタログスペックだけでは、手持ちのPCとケーブル1本で確実に繋がるかは断言できません。「繋がらない可能性もある」ことを念頭に置き、その場合はACアダプターを使う、と割り切ることも必要かもしれません。
- パススルー充電: モニターによっては、モニターのUSB Type-C(電源入力用)にACアダプターを繋ぐと、PCにも給電できる「パススルー充電」に対応しているモデルもあります。必須ではありませんが、あると便利な機能です。
ポイント7:付属品とメーカー、その他 – ケースやサポート体制もチェック
最後に、付属品やメーカーの信頼性、その他の細かい点も確認しましょう。
付属品
- 必要なケーブルが揃っているか?:
- USB Type-C to Type-Cケーブル (映像・電源用): 必須。付属ケーブルを使うのが基本。
- HDMIケーブル (通常-Mini/Micro): HDMI接続する場合に必要。
- USB Type-A to Type-Cケーブル (電源用): HDMI接続時や、PCからの給電が足りない場合に、ACアダプターやPCのUSB-Aポートからモニターへ給電するために使う。
- ACアダプター: 付属していると安心。特にHDMI接続を考えている場合や、Type-C接続で電力不足が心配な場合に。
- 保護ケース/カバー:
- 持ち運びが多いなら必須。傷や衝撃から守ります。
- 最初から専用ケースが付属しているモデルもあります。付属していない場合は、別途購入を検討しましょう。Amazonなどで1500円~2000円程度で購入できます。ケーブル類を一緒に収納できるポケット付きが便利です。

メーカーとサポート
モバイルモニターは、大手PCメーカーから、比較的新しい専業メーカー(いわゆる中華系メーカー含む)まで、様々なメーカーが参入しています。
- 大手PCメーカー (例: Lenovo, Dell, HP, ASUSなど):
- メリット: ブランドの信頼性、比較的しっかりしたサポート体制。PC本体とのデザイン的な親和性。
- デメリット: 価格は高めになる傾向。
- 専業メーカー (例: EVC、Innocn、kksmart、ARZOPAなど多数):
- メリット: コストパフォーマンスの高いモデルが多い。ユニークな機能を持つ製品もある。
- デメリット: メーカーによってサポート体制にばらつきがある可能性。長期的な信頼性は未知数な場合も。
選び方のポイント(メーカー・サポート)
- 日本語サポートの有無: 万が一の不具合や、接続方法で困ったときに、日本語でスムーズに問い合わせできるかは重要です。購入前にメーカーサイトなどで確認しておくと安心です。レビューで使用感だけでなく、サポート対応についての言及も参考にしましょう。
- レビューを参考にする: Amazonなどのレビューは玉石混淆ですが、多くのユーザーの声は参考になります。特に、自分と同じようなPCやデバイスとの接続実績、トラブルシューティングの情報は役立ちます。
- 信頼できる情報源: 私(この記事の執筆者)のようなレビュアーや、信頼できるメディアのレビュー記事も参考に、製品ごとの特徴や注意点を把握しましょう。
モバイルモニターを最大限に活用するために – PC選びとの連携
モバイルモニターは単体でも便利ですが、接続するPCとの連携も重要です。特にUSB Type-Cケーブル1本での接続を最大限に活用するには、PC側のポート仕様が鍵となります。
これからPCの購入も検討している方は、以下の記事も参考に、モバイルモニターとの連携も視野に入れたPC選びをすることをおすすめします。
- PCの基本的な選び方を学ぶなら:
【パソコンの選び方】初心者から上級者まで失敗しないPCスペックの見方と選択ポイント
https://enjoykeiri.com/how-to-choose-pc/ - 新生活向けのおすすめPCモデルを知るなら:
【2025年春最新版】新生活者 パソコン ベスト5|おすすめモデルからAI性能まで徹底解説
https://enjoykeiri.com/choose-pc-for-students-workers/
これらの記事を参考に、映像出力や電源供給に対応したUSB Type-Cポートを持つPCを選べば、モバイルモニターをよりスマートに、快適に活用できるでしょう。
まとめ:あなたに最適なモバイルモニターを見つけよう
モバイルモニターは、選び方のポイントさえ押さえれば、あなたのデジタルライフを格段に豊かにしてくれる便利なアイテムです。最後に、7つの重要ポイントと、特に注意したい点を表でまとめます。
【表6】モバイルモニター選び 7つのポイント早見表
| ポイント | 主な選択肢/チェック項目 | 特に重視したい点 |
|---|---|---|
| 1. 価格帯 | エントリー(~2万円台前半), ミドル(~3万円台), ハイ(4万円~) | 予算と機能のバランス、自立スタンドなら1万円台後半~ |
| 2. 画面サイズ | 13.3インチ, 14インチ, 15.6インチ | 持ち運び頻度、作業領域、迷ったら14インチ |
| 3. 画質 | 解像度(フルHD/4K), 表面処理(光沢/非光沢) | 用途(作業/映像鑑賞)、目の疲れやすさ |
| 4. タッチ対応 | あり / なし | 必要性、予算、重量増、光沢パネル許容度 |
| 5. スタンド | カバー兼用 / 自立式 | 【最重要】角度調整の自由度 → 自立式が断然おすすめ |
| 6. 接続端子 | USB Type-C(DP Alt), HDMI | ケーブル1本接続の可否 (PC側も要確認)、汎用性 |
| 7. 付属品・メーカー | ケーブル類、ACアダプター、ケースの有無、サポート体制 | 必要なものが揃っているか、日本語サポートの有無 |
これらのポイントと表を参考に、あなたの使い方や予算に合ったモバイルモニターを選び、より快適で効率的な作業環境、あるいはより楽しいエンターテイメント環境を手に入れてください。モバイルモニターは、一度使うとその便利さから手放せなくなる、まさに”沼”な魅力を持ったデバイスです!
免責事項
- この記事は、モバイルモニターの一般的な選び方に関する情報提供を目的としており、特定製品の購入を推奨するものではありません。
- 製品の仕様、価格、販売状況は常に変動する可能性があります。最新の情報は各メーカーの公式サイトや販売店でご確認ください。
- 記事内で紹介している価格帯やスペックは、執筆時点での一般的な目安です。
- USB Type-Cケーブル1本での接続は、お使いのPC、モニター、ケーブルの組み合わせによって動作しない場合があります。接続の可否を保証するものではありません。
- 製品の選択、購入、利用に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、筆者およびサイト運営者は一切の責任を負いかねます。
- 記事内のリンクには、アフィリエイトリンクが含まれる場合があります。