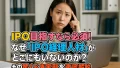「パート収入を増やしたいけど、扶養から外れるのは避けたい…」「学生アルバイトで稼ぎたいけど、親の税金が増えるのは困る…」
そんな風に悩んでいる方は多いのではないでしょうか?特に最近では、「所得税の103万円の壁が160万円に引き上げられた」というニュースを目にして、さらに混乱しているかもしれませんね。特に2025年(令和7年)年末調整では扶養・控除の新ルールで大激変が予想されます。
結局、私たち扶養内パートや学生アルバイトは、どの「年収の壁」に一番気を付ければいいのでしょうか?そして、もし壁を超えてしまったら、具体的にどれくらいの負担が増えることになるのでしょうか?
ご安心ください。この記事では、令和7年度の税制改正で新設・変更された「税金の壁」と、以前から存在する「社会保険の壁」について、税理士の視点から最新情報を分かりやすく徹底解説します。単に制度を説明するだけでなく、各壁を超えた場合の具体的な負担額をシミュレーションし、「手取りが減ってしまう損するゾーン」についても詳しくお伝えしていきます。
読み終える頃には、あなたが本当に意識すべき「年収の壁」が明確になり、これからの働き方や収入計画を自信を持って立てられるようになるでしょう。さあ、一緒に複雑な「年収の壁」の全貌を解き明かしていきましょう!
令和7年税制改正でどう変わった?新たな「年収の壁」を徹底整理

まず、今回の税制改正で私たちの周りにどんな「年収の壁」が新しくできたのか、または変わったのかを整理しておきましょう。これまで「103万円の壁」として広く知られていた所得税の非課税ラインが、実は大きく変わっています。
今回の改正の具体的な内容は、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」が引き上げられたこと。
基礎控除は48万円から最大95万円に、給与所得控除は最低55万円から最低65万円にそれぞれアップしました。この2つを合わせると、48万円+55万円=103万円だった非課税ラインが、最大95万円+最低65万円=160万円まで引き上げられたことになります。つまり、年収160万円以下であれば、本人の所得税はかからなくなったのです。
さらに、夫(世帯主)が受けられる配偶者控除や配偶者特別控除も、妻の年収が160万円以下であれば満額(38万円)受けられるよう変更されました。しかし、160万円を超えると控除額が徐々に減っていくため、これが新たな「160万円の壁」となります。
配偶者以外の扶養親族(子供や親など)がいる場合の扶養控除も変わりました。年収160万円以下なら本人に所得税はかかりませんが、年収が123万円を超えると、夫が受けられる扶養控除(38万円~63万円)が受けられなくなってしまいます。これが「123万円の壁」です。
特に19歳以上23歳未満の大学生などのお子さんを持つご家庭には朗報です。「特定親族特別控除」が創設され、子供の年収が150万円以下なら親が満額63万円の控除を受けられるようになりました。年収150万円を超えると控除額が減少していくため、これが「150万円の壁」と呼ばれます。
そして、所得税とは別に住民税にも変更がありました。住民税が非課税となる「100万円の壁」は、給与所得控除が10万円増えたことで、「110万円の壁」に変わっています。
これら4つの「税金の壁」に加え、以前からある「社会保険の106万円の壁」と「130万円の壁」の2つを合わせた、合計6つの「年収の壁」について、次章から一つずつ詳しく見ていきましょう。
まずは税金の壁!超えても負担は“ゆるやか”な4つの壁
税金の壁は、社会保険の壁と異なり、「壁を超えた瞬間に負担が爆発的に増える」という性質のものではありません。多くの場合、負担は比較的ゆるやかに増えていきますので、過度に恐れる必要はありません。
住民税の「110万円の壁」:月数千円〜の負担増
住民税には、所得に関わらず誰でも支払う「均等割」と、所得に応じて支払う「所得割」の2種類があります。このうち、均等割すら支払わなくてよくなる非課税限度額が、自治体によって年収103万円から110万円の間で定められています。これを住民税の「110万円の壁」と呼びます。
この壁を超えると、扶養内パートの妻や学生アルバイトの子供本人が住民税を支払う必要が出てきます。
壁を超えた時に増える負担の金額
110万円の壁を超えた場合に必要となる均等割は、最低4,000円。これに森林環境税1,000円が加わり、最低でも年間5,000円の負担となります(自治体によっては若干上乗せされることもあります)。
所得割については、給与所得控除や住民税の基礎控除(43万円)など、合計108万円を超える部分に約10%かかります。例えば、年収120万円で他に控除がなければ、所得割は約1万2,000円程度。均等割と合わせても、合計約1万7,000円程度の負担増にとどまります。
つまり、110万円の壁を10万円超えて年収120万円になったとしても、増える住民税の負担は年間で合計1万5,000円〜2万円前後。この程度の負担増であれば、「壁を気にして仕事量を抑える」といった極端な働き方を考える必要はあまりないでしょう。
【注意点】
ただし、単身世帯や夫の収入がない世帯で、住民税非課税世帯だけが受けられる国民健康保険料の軽減や高額療養費の優遇措置などを受けている方は要注意です。非課税限度額を超えると、これらの優遇措置が受けられなくなるため、思わぬ負担増になる可能性があります。
扶養控除の「123万円の壁」:特定の扶養親族に影響
扶養控除の「123万円の壁」とは、扶養親族(子供や親など)の年収が123万円を超えると、世帯主(夫など)が受けられる扶養控除が適用されなくなることを指します。
ただし、この壁を気にする必要があるのは、配偶者と19歳以上23歳未満の子供以外の扶養親族がいる場合です。配偶者の場合は「配偶者特別控除」、19歳以上23歳未満の子供の場合は後述の「特定親族特別控除」があるため、年収123万円を少し超えたぐらいでは世帯主の税額は大きく増えません。
壁を超えた時に増える負担の金額
扶養控除の金額は、通常38万円ですが、70歳以上の親(同居の場合は58万円、別居の場合は48万円)など、親族の年齢や同居の有無で金額が変わります。
例えば、世帯主が所得税率10%で納税している場合、扶養控除38万円が受けられなくなると、世帯主の所得税は38万円 × 10% = 3万8,000円増えます。さらに住民税でも、扶養控除33万円が受けられなくなるため、33万円 × 10% = 3万3,000円の負担増となります。
合計すると、世帯主の税負担は年間7万1,000円の増加になります。世帯主の所得税率によってはさらに増える可能性もあるため、対象となる扶養親族がいる場合は、少し注意が必要です。
特定親族特別控除の「150万円の壁」(学生アルバイト向け):親の税負担が“段階的”に増加
19歳以上23歳未満の大学生の年齢にあたるお子さんを扶養している親御さんにとって、学費の負担は大きいものです。そのため、通常38万円の扶養控除が「特定扶養控除」として63万円に引き上げられています。今回の税制改正で新設された「特定親族特別控除」は、この特定扶養控除が適用される子供向けに設けられた制度です。
お子さんがアルバイトをして年収123万円を超えると、親が受けられる特定扶養控除63万円自体はなくなります。しかし、その代わりに「特定親族特別控除」が適用され、親の税金はすぐには高くならない仕組みになっています。この制度ができたことで、学生アルバイトが扶養から外れると親の税金が急激に高くなる、という事態が避けられるようになりました。
ただし、お子さんの年収が150万円(合計所得85万円)を超えると、特定親族特別控除の額が徐々に減少していきます。これが「150万円の壁」です。
壁を超えた時に増える負担の金額
もしお子さんの年収が150万円の壁を10万円超えて160万円になった場合、特定親族特別控除は63万円から51万円に12万円下がります。親の所得税率が10%だとすると、12万円 × 10% = 1万2,000円の所得税負担が増えることになります。住民税の特定親族特別控除は年収160万円以下なら変わらないため、住民税の負担増はありません。
このように、150万円の壁を超えても「急激に負担が増える」というよりは、「階段のように少しずつ負担が増えていく」イメージです。この壁を極端に警戒して、お子さんのアルバイトを制限するような必要は少ないでしょう。ただし、増えるのはお子さん本人ではなく親御さんの税負担ですので、学業との兼ね合いも含め、ご家族で事前に相談することをおすすめします。
所得税と配偶者特別控除の「160万円の壁」:夫婦それぞれの税負担増
「160万円の壁」について、より詳細なメリット・デメリットや最新税制改正案のポイントは、税理士が徹底解説したこちらの記事もご参照ください。
扶養内パートの奥様がいるご家庭の場合、年収123万円を超えると夫(世帯主)の配偶者控除38万円は受けられなくなります。しかし、その代わりに「配偶者特別控除」が適用されるため、年収123万円を少し超えたぐらいでは夫の税額は増えません。
今回の税制改正により、妻の年収が160万円(合計所得95万円)を超えると、配偶者特別控除の額が徐々に減少していくことになります。これが「160万円の壁」です。
また、年収160万円を超えると、妻本人にも所得税がかかり始めるため、この壁を超えた場合には、夫婦それぞれにかかる税負担を計算する必要があります。
壁を超えた時に増える負担の金額
1. 妻本人にかかる所得税
妻本人の所得税は、年収160万円(給与所得控除と基礎控除を合わせた金額)を超えた部分に対して、最低5%の税率がかかります。例えば、年収が10万円増えて170万円になった場合、妻にかかる所得税は(170万円 − 160万円) × 5% = 5,000円程度です。所得税率は所得に応じて変わりますが、およそ年収380万円以下であれば5%の範囲内です。
2. 夫にかかる税金(所得税と住民税)
夫の税金も、妻の年収が増えることで変動します。もし妻の年収が170万円になった場合、夫の所得税の配偶者特別控除は38万円から31万円に7万円下がります。夫の所得税率が10%だとすると、7万円 × 10% = 7,000円の所得税負担が増えます。
さらに、住民税の配偶者特別控除も33万円から21万円に12万円下がるため、12万円 × 10% = 1万2,000円の住民税負担が増えます。夫の税金は合計で1万9,000円の増加となります。
このように、160万円の壁を10万円超えたとしても、急激に夫婦の税負担が増えるわけではありません。負担は緩やかに増えていくイメージですが、負担が増えることは確かなので、ワークライフバランスも考慮しながら仕事量を調整することをおすすめします。
最も注意すべき!負担が“一気に重くなる”社会保険の壁
最も注意すべき!負担が“一気に重くなる”社会保険の壁
パート・アルバイトも対象となる社会保険加入条件について、まずは全体像を把握しましょう。
ここまで見てきた「税金の壁」は、超えても負担がゆるやかに増えるものでした。しかし、ここから解説する「社会保険の壁」は、超えた瞬間に負担が跳ね上がり、手取りが大きく減ってしまう可能性が高い、最も注意すべき壁です。
勤務先が従業員51人以上の企業の場合:「106万円の壁」
勤務先が従業員数51人以上の企業(2027年10月からは36人以上、2035年10月からは全企業に拡大予定)の場合、扶養内パートや学生アルバイトの皆さんが特に気を付けたいのが「106万円の壁」です。
2024年10月以降、以下の4つの要件を全て満たした場合、短時間労働者として社会保険への加入が義務付けられます。
1. 所定内賃金が月額8.8万円以上
* 雇用契約書などに定められた毎月の基本的な給与や手当のことです。残業代や賞与、通勤手当、家族手当、皆勤手当などは含みません。
2. 所定労働時間が週20時間以上
* 雇用契約書などに定められた通常の週の勤務時間です。残業時間は含みません。ただし、実績が2ヶ月連続で週20時間以上となり、その状態が続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象となることもあります。
3. 2ヶ月を超える雇用の見込みあり
4. 学生でない
* 学生アルバイトはこの106万円の壁を気にする必要はありません。
月額賃金8.8万円を年収に換算すると8.8万円 × 12ヶ月 = 105.6万円になるため、これが「106万円の壁」と呼ばれています。この壁を超えると、社会保険上の世帯主(夫など)の扶養から外れ、パートや子供本人が社会保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。
壁を超えた時に増える負担の金額
社会保険料は、会社が半分負担してくれるとはいえ、自己負担分だけでも給与の約14%〜15%かかります。年収106万円の場合、単純計算で106万円 × 15% = 15万9,000円もの社会保険料が給与から天引きされることになります。
この負担は、106万円を超えた部分にだけかかるのではなく、年収全体に対してかかるため、非常に重く感じられます。壁を超える直前の年収105.5万円と、社会保険に加入して年収106万円になった場合を比較すると、手取りが急激に減ってしまうのです。
【要注意!】手取りが減る「損するゾーン」
年収105.6万円からおよそ年収125万円あたりまでは、社会保険料の負担が重く、壁を超えない働き方をしている年収105.5万円よりも手取りが少なくなってしまう「損するゾーン」に入ります。このため、「どうせ壁を超えるなら、思い切ってたくさん稼いで手取りを増やしたい」と考える方が増えるのも無理はありません。
社会保険加入のメリット・デメリット
もちろん、社会保険に加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気やケガで働けなくなった場合に傷病手当金が、出産時には出産手当金がもらえたりするなどのメリットはあります。しかし、年収120万円で1年間加入したとしても、増える年金は月額500円程度と、長期的に見ないと実感しにくい金額です。特に、健康保険料は支払いの方がリターンより大きくなる傾向があります。医療費のメリットは大きいですが、負担とのバランスをよく考える必要があるでしょう。
最近では、このような手取りの減少を防ぐため、事業主に対して助成金を支払う「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」という制度も新設されました。しかし、どこまで活用されるかは、今後の状況次第と言えるでしょう。
勤務先が従業員50人以下の企業の場合:「130万円の壁」
勤務先が従業員数50人以下の企業の場合、現時点では「106万円の壁」の適用はありませんが、扶養内パートや学生アルバイトの年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れなければなりません。これが「130万円の壁」です(ちなみに、60歳以上の場合は180万円以上になります。また、夫の年収の2分の1以上の収入になった場合も扶養から外れます)。
この場合、妻や子供は以下のいずれかの対応が必要になります。
- 自分で国民健康保険と国民年金に加入する
- 勤務先が社会保険の適用事業所で、週30時間以上(正社員の4分の3以上)勤務するなど、社会保険の加入要件を満たし、勤務先で社会保険に加入する
【要注意!】年間の見込み収入額で判定
社会保険の年収130万円以上の判定は、税金のように1月から12月の収入で判定するのではなく、「年間の見込み収入額」で判定されます。そのため、年の途中でも昇給や仕事量の増加で給与月額が10万8,334円以上になった場合など、その時点から1年間の見込み収入額が130万円以上になると、扶養から外れてしまうことがあるので注意が必要です。
ただし、職場の人手不足などによる「一時的な収入増」であると勤務先の事業主が証明書を発行してくれれば、2年連続までなら130万円を超えても扶養にとどまることが可能です。
壁を超えた時に増える負担の金額
1. 勤務先で社会保険に加入した場合
年収130万円で勤務先の社会保険に加入した場合、単純計算で130万円 × 15% = 19万5,000円もの社会保険料が給与から天引きされます。税金の額は約2万円下がりますが、それでも手取りは約17万5,000円も少なくなってしまいます。
【要注意!】手取りが減る「損するゾーン」
壁を超える直前の年収129.9万円より手取りを多くするためには、およそ年収153万円以上稼ぐ必要があります。その間の年収130万円から153万円あたりは、せっかく稼いでも手取りが減ってしまう「損するゾーン」です。
2. 自分で国民健康保険と国民年金に加入した場合
これは「130万円の壁」で最も負担が大きくなるケースです。
* 国民健康保険料:平等割、均等割、所得割の3種類で構成され、40歳〜64歳の人がいれば介護保険料分も上乗せされます。京都市を例に年収130万円(40歳未満、世帯人数1人)で試算すると、年間約8万8,000円となります。
* 国民年金保険料:全員一律で月額1万7,510円(令和6年度)。年間約21万円です。
これらを合わせると、年間で約29万8,000円もの社会保険料を自分で支払うことになります。税金が約2万円下がったとしても、手取りは約27万8,000円も少なくなってしまう計算です。
【要注意!】手取りが減る「損するゾーン」
この場合、壁を超える直前の年収129.9万円より手取りを多くするためには、およそ年収162万円以上稼ぐ必要があるため、年収130万円から162万円あたりが「損するゾーン」となります。国民年金は将来年金として受け取れますが、国民健康保険は支払うだけで将来の年金には繋がりません。どうせ130万円の壁を超えるなら、できれば勤務先で社会保険に加入できるぐらい働くことを検討したいところです。
個人事業主や副業をしている場合:「130万円の壁」が基本
個人事業主の方や副業をされている方も、社会保険の壁は「130万円」が基本です。社会保険の130万円の壁は、基本的には全ての人に共通して適用される壁だからです。個人事業主も、130万円の壁を超えると世帯主の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
副業をしている方も注意が必要です。メインの勤務先の給与収入だけでは106万円や130万円の壁を超えなくても、別の会社からの給与収入や、個人事業としての事業収入などを合算した合計額が130万円の壁を超えると、やはり扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入することになります。
また、社会保険上の収入には、税金がかからない通勤手当や失業給付、傷病手当金、出産手当金なども含まれてしまいます。これらの収入も合わせて130万円以上になるかどうかを判定してください。
会社員と異なる点は、一時的な収入増であっても、事業主の証明書をもらって扶養に残り続けるような制度は利用できないことです。残念ながら、個人事業主の場合は130万円の壁を超えるとすぐに扶養から外れてしまいます。
【深掘り解説】社会保険上の「事業収入」の判定基準は?
個人事業主の場合、難しいのが「社会保険上の収入が130万円以上かどうかの判定」です。売上高で判定するのか、経費を差し引いた後の利益で判定するのか、青色申告特別控除も差し引いた事業所得で判定するのか、といった問題が生じます。
結論から言えば、これらのいずれでもなく、概ね「売上高から売上原価を差し引いた利益の部分(粗利益)」で判定されることが多いです。
なぜこのような曖昧な結論になるのでしょうか?それは、社会保険上の収入判定方法が法律で細かく定められていないからです。昭和61年4月1日に旧社会保険庁から出された通知には「事業所得などの収入金額から差し引くことができる経費は、社会通念上明らかに所得を得るために必要と認められる経費に限る」と書かれています。
しかし、この「社会通念上明らかに所得を得るために必要と認められる経費」が具体的にどこまでを指すのか、通知には明記されていません。日本年金機構のQ&Aにも「売上原価は認める。減価償却費は認めない。一律の整理には馴染まない」といった記載があるだけです。
私自身、過去に何度も年金事務所などに問い合わせましたが、「仕入れなどの売上原価は認めますが、それ以外の経費は認められません」といった回答をされることがほとんどでした。法律で明確に定められていない以上、柔軟に売上原価以外の経費も直接必要経費として認めてもらえる可能性もゼロではありませんが、実務上は事務的に「粗利益」の部分で判定されることが多いのが現状です。
不動産収入がある場合も、事業収入と同じく売上高から直接必要経費を差し引いて判定することになりますので、注意してください。
まとめ:結局、気を付けるべきは「社会保険の壁」!
今回は、令和7年の税制改正で新しく登場・変更された4つの「税金の壁」と、以前からある2つの「社会保険の壁」について、具体的な負担額を交えながら徹底解説してきました。
最終的に、あなたが最も注意すべき「超えてはいけない年収の壁」は、やはり「社会保険の壁」です。
- 勤務先が従業員51人以上の企業(または将来的に適用拡大される企業)の場合:「106万円の壁」
- 勤務先が従業員50人以下の企業、または個人事業主・副業者の場合:「130万円の壁」
これらの社会保険の壁を超えてしまうと、年間15万円〜30万円近い社会保険料の自己負担が発生し、一時的に「手取りが減る損するゾーン」が生じてしまう可能性が非常に高いからです。
一方で、住民税の「110万円の壁」、扶養控除の「123万円の壁」、特定親族特別控除の「150万円の壁」、そして所得税と配偶者特別控除の「160万円の壁」といった「税金の壁」は、超えても負担が少しずつしか増えないため、そこまで極端に警戒する必要はないでしょう。
従来の「103万円の壁」が160万円まで引き上げられたことで、一見働きやすくなったように見えますが、社会保険の壁がなくならない限り、制度は複雑になる一方です。
この複雑な「年収の壁」は、知っているか知らないかであなたの手取り額が大きく変わってしまいます。この記事が、あなたの収入計画を立てる上で役立つ「道しるべ」となれば幸いです。もし迷った時は、ぜひこの記事を読み返して、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
—
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個人の状況に応じた税務・社会保険に関するアドバイスを提供するものではありません。税法や社会保険制度は常に改正される可能性があります。具体的な判断や手続きについては、必ず税理士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。