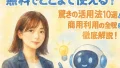2025年(令和7年)の年末調整は、これまでの常識を覆すほどの「大激変」を迎えます。毎年恒例の手続きだと油断していると、思わぬ落とし穴にハマったり、受けられるはずの控除を見逃してしまったりするかもしれません。特に、パートやアルバイトで働く方、学生のお子さんを持つご家庭、そして扶養内で働く配偶者を持つ方にとっては、家計に直結する重要な変更点が目白押しです。
なぜ、これほど大規模な変更が行われるのでしょうか?その背景には、国の「年収の壁」対策や、深刻化する人手不足問題への対応があります。つまり、「もっと働きたいのに、税金や社会保険料で損をするのが怖い」と感じる方々が、安心して仕事に取り組めるような環境を整えようという狙いがあるのです。
本記事では、公認会計士・税理士の専門的視点から、2025年(令和7年)年末調整の「過去最大級の変更点」を、あなたの生活にどう影響するのかという視点で、一つ一つ丁寧かつ徹底的に解説していきます。具体的には、年末調整の必要書類の様式変更から、個人の「基礎控除」の大幅な見直し、扶養親族の範囲の拡大、そして新設される「特定親族特別控除」の全貌、さらには配偶者控除の注意点、住宅ローン控除の簡素化、源泉徴収額の思わぬ落とし穴まで、あなたが知るべき情報を網羅しています。
この記事を最後まで読めば、2025年(令和7年)の年末調整で「何を」「どうすれば良いのか」が明確になり、自信を持って手続きを進められるようになるでしょう。自分の家族構成や働き方に合わせて、今一度シミュレーションし、確実にメリットを享受するための準備を始めましょう。

2025年(令和7年)年末調整、なぜこれほどの大改革なのか?
2025年(令和7年)の年末調整が大掛かりな変更を迎える背景には、現代社会が抱える複数の課題を解決しようとする国の明確な意図があります。単なる税制改正ではなく、私たちの働き方や家族のあり方、経済活動全体に影響を与える「社会変革」と捉えることができるでしょう。
「年収の壁」対策と労働力不足の解消へ
最大の要因の一つは、長年議論されてきた「年収の壁」問題への対策です。これまで、パートやアルバイトで働く方が「年収103万円」「年収130万円」といった特定の収入ラインを超えると、所得税や住民税が発生したり、社会保険の扶養から外れて自身で保険料を負担することになったりするため、「これ以上働くと手取りが減る」と労働時間を調整するケースが多発していました。これが、労働力不足が深刻化する中で、働く意欲のある人々の労働参加を阻害する要因となっていました。
国は、この「年収の壁」がもたらす労働意欲の減退を解消し、より多くの人が能力に応じて働けるようにすることを目指しています。特に、学生アルバイトや主婦(夫)のパートなど、短時間労働者が「壁」を気にせずに働けるよう、税制上の優遇措置を拡大することで、労働市場への供給を増やし、人手不足の解消につなげたいと考えているのです。
学生・若年層の労働を後押しする狙い
今回の改正では、特に19歳から22歳の学生や若年層に対する「特定親族特別控除」が新設されるなど、この層への手厚い配慮が見られます。これは、学費を稼ぐためにアルバイトをする学生や、社会に出る前の若者が、学業と両立しながらも積極的に労働市場に参加しやすい環境を整備する狙いがあります。彼らが「年収の壁」を気にせずに働けるようになれば、企業はより多様な人材を確保できるようになり、経済全体の活性化にも繋がると期待されています。
複雑化する税制への対応と透明性の確保
一方で、今回の改正により、年末調整の手続きや所得計算の仕組みは一時的に複雑化します。しかし、これは各個人の多様な働き方やライフスタイルに合わせた、よりきめ細やかな税制を目指す過程でもあります。国民一人ひとりが自分の収入や家族構成に応じた適切な税負担を理解し、不要な控除漏れがないよう、情報提供の強化と手続きの簡素化も同時に進められています(例えば、住宅ローン控除の長所方式)。
今回の年末調整の変更は、単なる「手続きの変更」ではありません。私たちの働き方、家族の支え方、そしてお金との向き合い方に、大きな影響を与えるものです。だからこそ、変更点を正しく理解し、自分の状況に合わせて適切に対応することが、これからの時代を賢く生き抜く上で不可欠となるでしょう。
まずはここから!「収入」と「合計所得」の基本を再確認
2025年(令和7年)の年末調整の変更点を理解する上で、最も基本的ながら誤解されやすいのが、「収入」と「合計所得」の違いです。この二つの言葉が混同されがちですが、税金や扶養の判定においては、明確に区別して理解することが不可欠です。
「収入」とは、いわゆる「額面」のこと
まず「収入」とは、一般的に皆さんが「額面」と呼んでいる、会社から支払われる給与や賞与の総額を指します。例えば、月給30万円、ボーナス年2回で各30万円であれば、年間の給与収入は「30万円 × 12ヶ月 + 30万円 × 2回 = 420万円」となります。これは、社会保険料や税金などが引かれる前の、文字通り「稼いだお金の総額」のことです。
「給与所得控除」とは「会社員の経費」
会社員やパート・アルバイトの方が受け取る給与収入には、「給与所得控除」というものが適用されます。これは、個人事業主でいうところの「経費」に相当するもので、給与を受け取るためにかかった費用(スーツ代、書籍代、交通費など)を、個別に計算する手間を省くために一律で認められているものです。
この給与所得控除の額は、給与収入の金額に応じて決められています。2025年(令和7年)からは、最低額が従来の55万円から65万円に増額されます。これは、給与収入が少ない人ほど控除額が増える形になり、税負担が軽減されることを意味します。
【例】給与収入150万円の場合(2025年より)
- 給与収入:150万円
- 給与所得控除:65万円(最低額)
- 計算式:150万円(収入) – 65万円(給与所得控除) = 85万円
「合計所得」こそが扶養や控除の判定基準
そして、「合計所得」とは、この給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。上記の例で言えば「85万円」が合計所得となります。
さらに重要なのは、この「合計所得」は給与収入だけではなく、副業による事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得(例:FXや仮想通貨の利益、年金収入の一部)など、すべての所得の合計額を指すということです。扶養の対象になるかどうか、あるいは各種控除を受けられるかどうかは、この「合計所得」の金額によって判断されます。
【ポイント】
- 収入(額面):会社から受け取る給与の総額。
- 合計所得:収入から給与所得控除(会社員の場合)などを引いた後の金額。複数の所得がある場合はその合計額。
- 扶養や各種控除の判定基準は「合計所得」!
これから解説する年末調整の変更点では、様々な「○○円の壁」が出てきますが、その多くは「合計所得」を基準としています。この基本をしっかりと押さえておくことで、複雑に見える税制改正も、スッキリと理解できるようになるはずです。
大混乱必至!2025年(令和7年)年末調整「必要書類」の大変化
2025年(令和7年)の年末調整で、多くの人が最初に直面する変化が「必要書類の様式変更」でしょう。毎年、お馴染みの書類に記入していた方も、今年は新たな書類や、名称が変わった書類に戸惑うかもしれません。特に、「特定親族特別控除申告書」の新設は、今までにはなかった大きな変更点です。
年末調整書類の歴史的変遷と2025年の新様式
年末調整の書類は、これまでも時代の変化に合わせて形を変えてきました。かつては2枚だったものが、平成30年に3枚となり、令和2年にはさらに複雑化しました。そして、2025年(令和7年)には、以下のように書類の構成が大きく変わります。
| 時期 | 主な年末調整書類 |
|---|---|
| 〜平成29年 | 「扶養控除等申告書」(マル扶)など2枚 |
| 平成30年〜 |
「扶養控除等申告書」(マル扶) 「配偶者控除等申告書」(マル配) 「保険料控除申告書」(マル保)など3枚 |
| 令和2年〜 | 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」(マル基配所)が登場し、3枚に統合される形に |
| 令和7年(2025年) |
「扶養控除等申告書」(マル扶) 「特定親族特別控除申告書(新設)」 「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」(マル基配) 「保険料控除申告書」(マル保) |
新設される「特定親族特別控除申告書」とは?
今回の目玉となるのが、新たに加わる「特定親族特別控除申告書」です。これは、主に19歳から22歳(年末時点で)の特定親族を持つ方が提出する書類で、その子供が一定の年収を超えていても控除を受けられる「特定親族特別控除」を申請するために必要になります。
- 提出対象者: 12月31日時点の年齢が19歳から22歳の扶養親族を持ち、その親族が後述する「特定親族特別控除」の対象となる方。
- 記載事項: 特定親族となるお子さんの氏名、マイナンバー、そして重要なのが「合計所得金額の見積もり額」です。年末調整の提出時期が11月頃だとすると、12月までの見込み所得を正確に記載する必要があります。見込みと実際の所得にずれが生じた場合は、会社に申し出て再提出するか、間に合わなければ確定申告で修正する必要があります。これは、特に学生アルバイトなどで年間を通して収入が変動しやすいケースでは注意が必要です。
「扶養控除等申告書」(マル扶)の変更点
「扶養控除等申告書」(通称マル扶)は、ほぼ全員が提出するお馴染みの書類ですが、こちらにも変更点があります。
- 名称変更: 従来の「控除対象扶養親族」という名称が、今後は「源泉控除対象親族」へと変わります。これは単なる名称変更だけでなく、後述するように扶養の範囲も一部変更されるため、注意が必要です。
- 記載欄の追加: 特定親族特別控除の対象となる親族がいる場合は、「特定親族」としてその旨を記載する欄が新設されます。
- 再提出の必要性: もし今回の扶養の範囲改正によって、新たに扶養対象となる家族が増えた場合は、令和7年分のマル扶を再提出する必要があります。その際は、「異動事由」の欄に「令和7年12月31日改正」といった内容を記載して提出しましょう。
「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」(マル基配)の変更点
従来の「マルキ配所」が「マル基配」となり、その名の通り「所得金額調整控除申告書」が分離されます。特に基礎控除については、後述するように個人の所得に応じて控除額が変動するようになるため、この申告書に記載するあなたの「合計所得金額の見積もり額」が、より重要になります。
その他の書類
- 「保険料控除申告書」(マル保): こちらは大きな変更はありません。生命保険料、地震保険料、社会保険料などを申告するための書類です。
このように、2025年(令和7年)の年末調整では、提出書類の名称変更や新設、記載内容の重要性が増しています。特に複数の書類の提出が求められる場合、抜け漏れがないように、早めに内容を確認し、準備を進めることが賢明です。
個人の「基礎控除」が大きく変わる!所得に応じた新ルールを徹底解説
これまでの年末調整では、ほとんどの人が一律48万円の「基礎控除」を受けていました。しかし、2025年(令和7年)からは、そのシンプルさが過去のものとなります。あなたの所得に応じて基礎控除額が変動する、全く新しいルールが適用されるのです。これは、個人の税負担に大きな影響を与えるため、最も注目すべき変更点の一つと言えるでしょう。
「一律48万円」の時代は終わり!所得に応じた基礎控除額
2025年(令和7年)からは、納税者本人の合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に変動します。特に、所得が低い層ほど手厚い控除が受けられるようになり、高所得者ほど控除額が減少する仕組みです。
具体的な控除額は以下の通りです。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 | (参考)給与収入のみの場合の年収目安 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 200万4千円未満 |
| 132万円超257万円以下 | 88万円 | 200万4千円〜475万2千円未満 |
| 257万円超472万円以下 | 68万円 | 475万2千円〜665万5千円以下 |
| 472万円超612万円以下 | 63万円 | 665万5千円〜850万円以下 |
| 612万円超642万円以下 | 58万円 | 850万円〜890万円以下 |
| 642万円超672万円以下 | 48万円 | 890万円〜930万円以下 |
| 672万円超702万円以下 | 38万円 | 930万円〜970万円以下 |
| 702万円超732万円以下 | 28万円 | 970万円〜1010万円以下 |
| 732万円超762万円以下 | 18万円 | 1010万円〜1050万円以下 |
| 762万円超792万円以下 | 8万円 | 1050万円〜1090万円以下 |
| 792万円超802万円以下 | 1万円 | 1090万円〜1100万円以下 |
| 802万円超 | 0円 | 1100万円超 |
給与所得控除の増加と所得税の「160万円の壁」
基礎控除の変更と同時に、会社員やパート・アルバイトの方が受けられる給与所得控除の最低額も、従来の55万円から65万円に増額されます。
この二つの変更が組み合わさることで、特に低所得者層にとって、所得税の負担が大きく軽減される可能性があります。
例えば、給与収入が200万4千円未満(合計所得132万円以下)の方を見てみましょう。
- 新しい基礎控除額:95万円
- 新しい給与所得控除額:65万円
- 合計:95万円 + 65万円 = 160万円
つまり、給与収入が160万円までであれば、所得税がかからないという「所得税の160万円の壁」が新たに登場することになります。これは、これまで103万円の壁や130万円の壁を意識していた方にとって、大きなメリットとなり得ます。この「160万円の壁」が本当にあなたの手取りを増やすのか、税理士の視点からさらに深く掘り下げた解説はこちらでご確認ください。
ただし注意!住民税と社会保険料の壁は依然として健在
「所得税の160万円の壁」ができたからといって、無条件に160万円まで働いても手取りが減らないわけではありません。なぜなら、住民税と社会保険料の「壁」は、依然として残っているからです。
- 住民税の壁: 住民税は、所得税よりも低い所得から課税されます。一般的に、給与収入が約100万円〜110万円を超えると住民税が課税される可能性があります。今回の改正でも、住民税に関する基礎控除額の見直しはありますが、所得税ほどの大きな緩和は見込まれません。
- 社会保険料の壁: 最も注意が必要なのが、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の「壁」です。
* 「106万円の壁」: 従業員数101人以上の企業などで働く場合、月額約8.8万円(年収約106万円)を超えると、社会保険への加入義務が生じ、自身で保険料を負担することになります。
* 「130万円の壁」: 上記の条件に該当しない場合でも、年収が130万円を超えると、扶養を外れて自身で社会保険に加入しなければなりません。
これらの社会保険料の負担は非常に大きく、税制上のメリットを大きく上回る可能性があります。パート・アルバイトの社会保険加入条件について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。したがって、「所得税の160万円の壁」は、あくまで「所得税がかからないラインが広がった」という認識にとどめ、住民税や社会保険料の壁には引き続き注意が必要です。特に、パート主婦の方などは、社会保険の壁を優先して働き方を検討することをお勧めします。
基礎控除の「限定加算額」が源泉徴収に与える影響
今回の基礎控除の改正には、一つ実務上で注意すべき点があります。前述の表で「88万円」「68万円」「63万円」「58万円」となっている控除額には、実は「限定加算額」と呼ばれる2年間限定の加算額が含まれています。例えば、合計所得が132万円超257万円以下の方の88万円は、本来の58万円に30万円が加算された額です。
この限定加算額は、税務当局側では「あくまで一時的なもの」と捉えられているため、来年1月からの給与計算で用いられる「令和8年分源泉徴収税額表」には、この加算額が反映されていません。つまり、税額表の計算では、あなたの基礎控除額が実際よりも低く見積もられて源泉徴収が行われます。
これが何を意味するかというと、毎月の給与から天引きされる所得税が、実際よりも高めに設定される可能性があるということです。
「なんだか手取りが減ったような気がする」「いつもより所得税が多く引かれているな」と感じたら、この限定加算額が原因かもしれません。しかし、これは年末調整で精算されるため、最終的には本来の控除額が適用され、多く徴収されていた分は還付金として戻ってきます。もしかしたら、来年の年末調整では、例年よりも多くの還付金が期待できるかもしれませんね。
扶養の範囲が大激変!「年収の壁」対策と新設「特定親族特別控除」
2025年(令和7年)の年末調整で、多くの家庭に影響を与えるのが「扶養の範囲」の大幅な変更です。特に、お子さんがいるご家庭や、学生アルバイトをされている方、そして「年収の壁」を意識していた方にとっては、働き方や税金の計算に大きな変化が生じます。
扶養親族の合計所得上限が123万円に拡大!
これまでは、扶養親族になるための条件として「合計所得が48万円以下」(給与収入のみの場合、年収103万円以下)という「103万円の壁」が広く知られていました。しかし、2025年(令和7年)からは、この基準が大幅に緩和されます。
- 新基準: 扶養親族となるための合計所得上限が、58万円以下へと変更されます。
- 給与収入のみの場合: 給与所得控除の最低額が65万円に増えたため、「58万円(合計所得) + 65万円(給与所得控除) = 123万円」となり、給与収入123万円以下であれば扶養親族に該当するようになります。
これにより、これまで「103万円の壁」を意識して労働時間を調整していた方は、年収が123万円まで引き上げられても、引き続き親や配偶者の扶養親族として控除を受けられるようになります。これは、扶養者側の税負担軽減だけでなく、被扶養者側も安心して、より多くの収入を得られるようになる大きなメリットと言えるでしょう。
以下に、年齢別の扶養控除額の概要を示します。
| 年齢(12月31日時点) | 区分 | 合計所得上限 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳以下 | 年少扶養親族 | 58万円以下 | 0円 | 児童手当が支給されるため控除はなし |
| 16歳〜18歳 | 一般扶養親族 | 58万円以下 | 38万円 | — |
| 19歳〜22歳 | 特定扶養親族 | 58万円以下 | 63万円 | 扶養控除。別途「特定親族特別控除」あり |
| 23歳〜69歳 | 一般扶養親族 | 58万円以下 | 38万円 | 非居住者は制限あり |
| 70歳以上(同居以外) | 老人扶養親族 | 58万円以下 | 48万円 | — |
| 70歳以上(同居) | 老人扶養親族 | 58万円以下 | 58万円 | — |
| 障害者控除 | — | — | 27万円/40万円/75万円 | 扶養控除に加算。金額は障害の程度による |
注目の新設!「特定親族特別控除」で学生・若年層の働き方が変わる
今回の年末調整の改正で、特に重要な新設控除が「特定親族特別控除」です。これは、19歳から22歳(年末時点で)の若年層の労働を後押しするために導入されるもので、「年収の壁」を気にせずに、より多く働けるようになる画期的な制度です。
- 対象者: 12月31日時点の年齢が19歳から22歳の親族。学生である必要はなく、この年齢であれば、例えばアルバイトをしている方も対象になります。
- 合計所得上限: 従来の扶養控除の基準(合計所得58万円)を超え、合計所得が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下)の範囲で適用されます。
- 控除額: 合計所得に応じて3万円から63万円の範囲で控除が適用されます。
* 給与年収150万円までであれば、最大63万円の特別控除を満額受けることができます。
* この控除は、親(納税者)の所得税・住民税を軽減する効果があります。
この「特定親族特別控除」の創設により、19歳から22歳の学生や若年層は、年収150万円まで稼いでも、親が所得税上の扶養から外れることなく(税制上のメリットを維持しつつ)控除を受けられることになります。
社会保険の壁にも変化!2025年10月1日からは150万円の壁へ
さらに朗報なのは、この特定親族特別控除の対象となる19歳から22歳の層に限り、社会保険の扶養に関するルールも変更されることです。
- 2025年10月1日以降: 19歳から22歳の被扶養者に限り、年収150万円までであれば、親の社会保険の扶養を外れることなく、自身の社会保険料の負担なしに働くことが可能になります。
これは、従来の「130万円の壁」を大きく超えるもので、この年齢層にとっては、税制面だけでなく社会保険面でも大きなメリットとなります。これにより、例えば月12.5万円(年収150万円)までアルバイトをしても、親の扶養から外れる心配なく、手取りを最大化できるようになります。まさに、国が「もっと働いて欲しい」というメッセージを、具体的な制度として示したと言えるでしょう。
「源泉控除対象親族」の新名称と影響
今回の改正では、これまでの「控除対象扶養親族」という名称が、「源泉控除対象親族」という新しい名称に変わります。これは、単なる呼び名の変更だけでなく、源泉徴収の計算を行う際に、この区分が関係してくるためです。
- 実務上の影響: 扶養控除等申告書(マル扶)の記載欄もこれに合わせて変更されます。新しい名称と範囲に慣れる必要があります。
- 扶養人数の再確認: 扶養の範囲が拡大したことで、これまで扶養に入れていなかった家族が新たに「源泉控除対象親族」となる可能性があります。その場合、会社に提出する扶養控除等申告書(マル扶)の扶養人数の記載が変わるため、年末調整のやり直しや再提出が必要になる場合があります。特に、年の途中で状況が変わった場合は、速やかに会社に報告しましょう。
この扶養の範囲の改正と特定親族特別控除の新設は、あなたの家族構成や働き方に大きな影響を与えます。特に19歳から22歳のお子さんがいるご家庭は、この機会に働き方を見直し、控除のメリットを最大限に活用することをおすすめします。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の変更点と注意点
配偶者がいる納税者にとって、年末調整の重要な要素となるのが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。今回の改正では、配偶者に関する控除の基本的な枠組みは維持されるものの、扶養親族の範囲拡大に伴い、配偶者の合計所得の基準額も変更されます。しかし、ここでも「社会保険の壁」が重要なカギを握ります。
配偶者控除の対象となる「同一生計配偶者」の基準
配偶者控除を受けられるのは、以下の条件を満たす「同一生計配偶者」です。
- 合計所得上限: 配偶者の合計所得が、従来の48万円以下から、58万円以下へと拡大されます。
- 給与収入のみの場合: 給与所得控除の最低額65万円と合わせて、年収123万円以下であれば、配偶者控除の対象となる「同一生計配偶者」に該当します。
配偶者控除の控除額は、納税者本人(稼いでいる側)の合計所得に応じて、以下のように段階的に減少します。
| 納税者本人の合計所得金額 | 配偶者控除額(一般) | 配偶者控除額(老人:70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1000万円超 | 0円 | 0円 |
💡 ポイント
- 配偶者の所得要件:配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)
- 老人配偶者:70歳以上の配偶者は控除額が10万円上乗せ
- 所得制限:納税者本人の所得が1000万円を超えると控除なし
【例】夫が稼ぎ、妻がパートの場合
- 妻の年収が123万円以下で、夫の年収が900万円以下であれば、夫は38万円の配偶者控除を受けられます。
- 妻が70歳以上で年収123万円以下の場合、夫の年収が900万円以下であれば、夫は48万円の老人控除対象配偶者控除を受けられます。
配偶者特別控除の範囲と注意点
配偶者の年収が123万円を超え、配偶者控除の対象から外れても、一定の条件を満たせば「配偶者特別控除」を受けることができます。
- 対象範囲: 配偶者の合計所得が58万円超148万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超201万1千円以下)の場合に、納税者本人の合計所得に応じて段階的に控除額が設定されます。
- 控除額: 配偶者の年収が上がるにつれて控除額は減少します。例えば、配偶者の年収が160万円の場合、納税者本人の年収が900万円以下であれば、38万円の配偶者特別控除を受けられます。
社会保険の「130万円の壁」「106万円の壁」は依然として重要!
配偶者控除や配偶者特別控除の所得基準が拡大されたことで、「もっと働いても税金面では大丈夫!」と考えるかもしれません。しかし、パート主婦(夫)の方にとって、税金以上に家計に大きな影響を与えるのが「社会保険の壁」です。
- 年収106万円の壁: 従業員数101人以上の企業(2024年10月からは51人以上)で働く場合、月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)になると、社会保険への加入が義務付けられ、自分で健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになります。
- 年収130万円の壁: 上記の条件に該当しない場合でも、年収が130万円を超えると、扶養を外れて自身で社会保険に加入しなければなりません。
社会保険料は、給与の約14〜15%(会社負担分を含めると約30%)を占めるため、この壁を超えると手取りが大きく減少する可能性があります。税制上のメリットと社会保険料負担を比較すると、多くの場合、社会保険料の負担の方が大きいため、安易に年収130万円(または106万円)を超えないよう、慎重な働き方の調整が必要です。
今回の改正で、税制上の扶養範囲は広がりましたが、社会保険の壁は依然として多くの働く人にとって重要な分水嶺となります。年末調整の書類作成だけでなく、ご自身の家計全体を見据えた働き方を検討する際には、社会保険料の負担についても十分に考慮に入れるようにしましょう。
なお、配偶者が70歳以上の場合、または特定の事情(障害など)がある場合は、控除額や要件が異なる場合があります。また、「源泉控除対象配偶者」という名称は以前から存在しており、今回の改正で新しくできたものではありません。
これだけは知っておきたい!その他の年末調整重要変更点
2025年(令和7年)の年末調整は、基礎控除や扶養の範囲に関する大きな変更だけでなく、実務的な手続きの簡素化や、納税者の皆さんが普段の給与で感じる手取り額に影響を与えるような、見過ごせない変更点も含まれています。
住宅ローン控除に「長所方式」が登場!添付書類が大幅削減
住宅ローン控除を受けている方にとって、毎年恒例の年末調整の大きな手間の一つが、金融機関から送られてくる「住宅借入金等年末残高証明書」を添付することでした。しかし、2025年(令和7年)からは、この手間が大幅に軽減される「長所方式」が新たに導入されます。
- 「長所方式」とは: 税務署から送付される「控除証明書」を提出するだけで、住宅ローン控除の年末調整ができるようになる方式です。これまでの「住宅借入金等年末残高証明書」の添付は不要になります。
- メリット:
* 金融機関からの書類到着を待つ必要がなくなるため、年末調整の準備を早めに進められる。
* 添付書類が減ることで、書類管理の手間や紛失のリスクが軽減される。
* マイナポータルと連携することで、さらに電子的な手続きも可能になります。
もちろん、これまでの金融機関からの借入金年末残高証明書を添付する方式も引き続き選択可能ですが、手間を考えると「長所方式」への切り替えが推奨されるでしょう。特に、複数年にわたって住宅ローン控除を受けている方は、この変更によって年末調整の手続きがかなり楽になるはずです。
源泉徴収額の注意点 – 基礎控除の限定加算額の落とし穴
「基礎控除」のセクションでも触れましたが、今回の改正で基礎控除額に設けられた「限定加算額」(2年間限定の加算額)は、皆さんの毎月の給与から天引きされる所得税額に影響を及ぼします。
- 令和8年分源泉徴収税額表に未反映: 来年1月以降の給与計算に使用される「令和8年分源泉徴収税額表」には、この限定加算額が織り込まれていません。
- 結果: 毎月の給与から源泉徴収される所得税は、本来適用されるはずの基礎控除額(限定加算額込み)よりも低い基礎控除額で計算されるため、通常よりも高めに天引きされることになります。
つまり、
- 「最近、給料の手取りが減った気がする…」
- 「なぜか所得税の金額が上がった?」
と感じるかもしれません。しかし、これは一時的なものです。年末調整の際には、限定加算額が考慮された正しい基礎控除額が適用されて税額が再計算されます。その結果、多く徴収されていた分は年末調整でしっかりと還付金として戻ってきます。
これは、国が一時的な財源確保や、年度途中の税額変更による混乱を避けるために取った措置と考えられます。納税者にとっては、毎月の手取りが減るように感じるかもしれませんが、年末にまとまった還付金が期待できるという側面もあります。この点を頭の片隅に置いておくことで、来年1月からの給与明細を見たときに慌てずに済むでしょう。
このように、2025年(令和7年)の年末調整は、単に書類の様式が変わるだけでなく、手続きの簡素化や税金の徴収方法にも細かな変更が加えられています。これらの変更点を把握しておくことで、年末調整をスムーズに、そして賢く乗り切ることができるはずです。
まとめ:2025年(令和7年)年末調整、あなたの家計を守る最終チェックリスト
2025年(令和7年)の年末調整は、まさに「過去最大級の変化」を迎えます。この記事では、あなたの家計に直結する重要な変更点を網羅的に解説してきました。ここで改めて、年末調整を乗り切るための最終チェックリストとして、主要なポイントを整理しましょう。
1. 必要書類の大変化を理解する:
* 「扶養控除等申告書」(マル扶)の「源泉控除対象親族」への名称変更と記載欄の確認。
* 「特定親族特別控除申告書」の新設。19歳〜22歳のお子さんがいる家庭は、この書類の提出が必須。特に「合計所得金額の見積もり額」の正確な記入が必要です。
* 住宅ローン控除を受けている方は、「長所方式」への切り替えを検討し、添付書類の簡素化のメリットを享受しましょう。
2. 基礎控除の新ルールを把握する:
* これまでの「一律48万円」は過去のものとなり、あなたの「合計所得金額」に応じて基礎控除額が変動します。特に、低所得者層は最大95万円に拡大されるため、所得税の負担が大きく軽減される可能性があります。
* 所得税の「160万円の壁」の登場を理解しつつも、住民税の壁(約110万円)や社会保険の壁(106万円・130万円)が依然として重要であることを忘れないでください。
3. 扶養の範囲と新設「特定親族特別控除」を徹底活用する:
* 扶養親族の合計所得上限が58万円(給与収入123万円)に拡大されたことで、より多くの家族が扶養に入れるようになりました。
* 最大の注目点は、19歳から22歳(12月31日時点)の学生や若年層を対象とした「特定親族特別控除」の新設です。給与収入150万円までであれば、親の所得税上の扶養から外れずに満額控除(63万円)を受けられます。
* さらに、2025年10月1日からは、この年齢層に限り社会保険の扶養も150万円まで拡大されるため、年収150万円までなら、親の扶養から外れずに社会保険料の負担なく働けるようになります。これは、学生アルバイトをされている方にとって、働き方の自由度を大きく高める朗報です。
4. 配偶者控除・配偶者特別控除と社会保険の壁を意識する:
* 配偶者の合計所得基準も58万円(給与収入123万円)に拡大されました。
* しかし、配偶者の方がパートで働く場合、税制上の控除額以上に社会保険の「106万円の壁」や「130万円の壁」が家計に大きな影響を与えることを再認識してください。税金だけでなく、社会保険料の負担も考慮に入れた働き方を検討することが賢明です。
5. 毎月の源泉徴収額の変動に心の準備を:
* 基礎控除の「限定加算額」が源泉徴収税額表に反映されていないため、来年1月からの給与では、所得税が高めに天引きされる可能性があります。しかし、年末調整で過払い分は還付されるため、心配はいりません。
今回の年末調整の変更は、複雑に見えるかもしれませんが、その多くは「年収の壁」に悩む人々が、より安心して働けるようにするための国の努力の現れです。特に、システムやスマホで年末調整の手続きを行う方も、これらの新しい概念や用語は必ず確認し、自分の家族構成や働き方に合わせた最適な選択を行うことが重要です。
国税庁のウェブサイトや、この記事を何度か読み返すことで、理解を深めていただければ幸いです。もしご自身のケースで不安や疑問があれば、スマホで簡単にできる確定申告ガイドなども参考にしつつ、お近くの税理士や税務署に相談し、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
【免責事項】
本記事の内容は、2025年9月時点の法令に基づき一般的な情報として提供されており、特定の個人や状況に対する税務上のアドバイスを意図するものではありません。税法は改正される可能性があります。実際の年末調整手続きや税務に関する具体的な判断については、必ず税務署または税理士等の専門家にご確認・ご相談ください。本記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねます。