皆さま、大変お待たせいたしました。2025年7月28日に公表された「株式会社オルツ 第三者委員会調査報告書」。100ページを超える膨大なこの報告書を読み解くのは、なかなか骨が折れる作業だったことでしょう。
本日は、上場企業の開示責任者でもあったエンジョイ経理編集長の視点から、この衝撃的な報告書の内容を詳細に解説します。株式会社オルツで一体何が起こり、どのような手口で不正が行われ、そしてどのような結末を迎えたのか。上場前の不正から上場廃止に至るまでの道のりを、時系列で徹底的に紐解いていきます。
このオルツの事件は、今後の上場制度、監査法人、そしてスタートアップ企業のあり方に大きな一石を投じるものです。監査法人にお勤めの公認会計士の方、企業の経理パーソンの方、あるいはこの事件に興味をお持ちの全ての方にとって、不正防止の教訓として深く理解していただきたいと願っています。何が起こったのか、そしてそこから何を学ぶべきか、一緒に見ていきましょう。
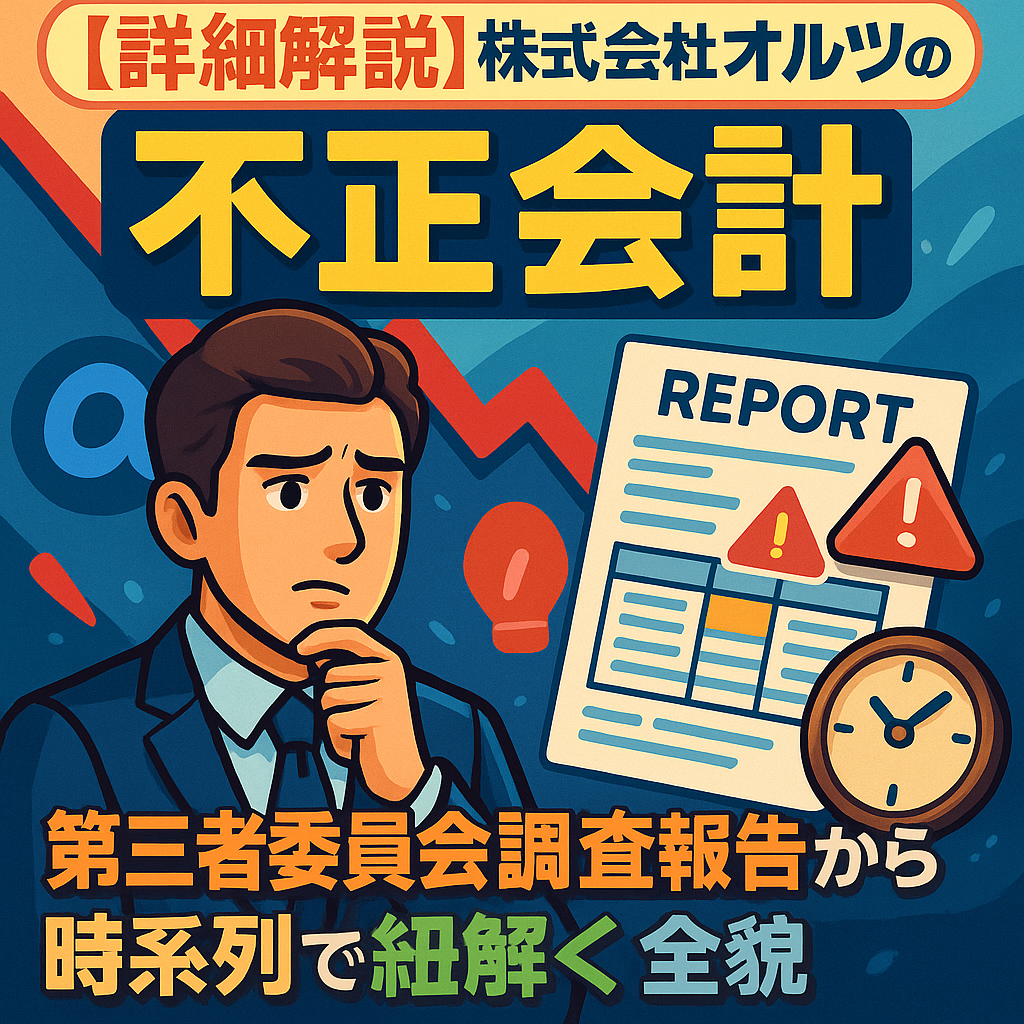
株式会社オルツとは? – スタートアップの光と影
まずは、今回の一連の不正会計事件の舞台となった「株式会社オルツ」について、その概要と事件発覚の背景から見ていきましょう。
株式会社オルツは、2014年11月に設立され、東京都港区六本木に本社を構える、資本金22億円のAI関連企業です。主力製品は「AI GIJIROKU」というAI議事録サービスで、近年流行のAI技術を扱う、まさに「キラキラした」スタートアップ企業として注目を集めていました。従業員規模は単体で23名、連結で75名程度と比較的小規模ながらも、2024年10月には東証グロース市場への上場を果たし、その成長性は多くの投資家から期待されていました。
しかし、上場からわずか半年後の2025年4月、証券取引等監視委員会による強制調査が入り、不正会計の疑いが浮上します。これを受けて設置された第三者委員会が約3ヶ月にわたる調査を行い、その結果として今回の調査報告書が公表されたのです。
報告書によると、なんと2021年6月から2025年3月までの約4年間にわたり、長期的に不正会計が行われていたことが判明しました。驚くべきは、この不正が上場前から行われていたという事実です。不正によって上場を果たしたというこの事態は、まさに「とんでもないこと」であり、市場に大きな衝撃を与えました。
オルツの売上は、2020年10月期には約5,500万円でしたが、そこから急成長を遂げ、2024年12月期には60億円に達しています。この急激な成長の裏には、後述する不正な売上の水増しがあったことが報告書で示されています。特に2024年12月期では、売上60億円のうち約49億円、実に82%が不正な売上であったというのです。2022年、2023年には90%以上が虚偽の売上という、まさに驚くべき実態が浮き彫りになりました。
オルツ売上推移(2020年10月期〜2024年12月期)
⚠️ 主な問題点
- 2024年12月期: 売上60億円のうち約49億円(82%)が不正
- 2023年12月期: 売上41億円のうち約37億円(91%)が不正
- 2022年12月期: 売上26億円のうち約24億円(91%)が不正
- 急成長の実態: 2020年の0.55億円から2024年の60億円への成長の大部分が不正によるもの
- 正常な売上は各年度とも数億円程度に留まり、見かけ上の急成長は不正会計によって演出されていた
また、監査法人に関しては、当初AW監査法人(一部ではビッグ4の一つと噂されています)が担当していましたが、2022年9月に監査法人が交代しています。この監査法人の交代が、不正の手口の進化と深く関わってくることになります。
事件の始まり:資金繰りの悪化と不正の誘惑
不正は、常に切羽詰まった状況や安易な考えから生まれるものです。オルツの場合も、事業の不振と資金繰りの悪化が不正の引き金となりました。
2020年1月に主力製品「AI GIJIROKU」をリリースしたオルツは、年間100社程度のパートナー企業と5万人のユーザーを獲得するという目標を掲げていました。しかし、同年4月から9月にかけて、その売上は計画を大きく下回り、月の普通預金残高が1,000万円を下回るなど、資金繰りは非常に厳しい状況に陥ります。
スタートアップ企業にとって、実績、特に売上実績はベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達に不可欠です。「うちのAI技術は将来性抜群です!上場すれば大きなリターンが期待できます!」とセールストークを展開しても、具体的な売上実績がなければ、なかなか出資は得られません。この窮地に立たされた社長は、「とりあえず売上実績を作ればいいんだ」という安易な発想に至ってしまいます。ここから、オルツの不正への道が始まったのです。
最初の不正は、いわゆる「同額取引」という手口でした。マーケティングリサーチ会社のJ社と組んで、以下のような取引が行われました。
1. オルツからJ社へ:「アンケート調査費用」の支払い(82.5万円)
* J社に「AI GIJIROKU」に関するアンケート調査を依頼するという名目で費用を支払う。これはオルツにとっては販促費として費用計上されます。
2. J社からオルツへ:「AI GIJIROKUアカウント発行費用」の支払い(1,500万円)
* J社がアンケート調査を実施するために「AI GIJIROKUアカウント」が必要だとし、その発行費用としてオルツに1,500万円を支払う。これはオルツにとっては売上として計上されます。
3. 裏取引:「1,500万円の返還」
* 実際には、J社がオルツに支払った1,500万円は、別の販促費用などの名目でオルツからJ社へ返還されるという裏約束があった。
つまり、オルツからすれば1,500万円の売上が立つ一方で、J社からすれば82.5万円を受け取って1,500万円を支払う大赤字になってしまいます。この大赤字を補填するために裏で資金が還流する仕組みです。これによって、オルツは実体のない売上を水増しすることに成功したのです。J社だけでなく、K社とも同様の取引が行われました。
不正の巧妙化:循環取引の進化とその手口
しかし、この最初の不正はすぐに露見します。
同額取引(バージョン1)の露見と学習
当然のことながら、オルツの監査を担当していたAW監査法人は、このJ社との「同額取引」をすぐに見抜きます。実体のない取引であり、オルツが計上した1,500万円の売上は認められないと指摘。実際に発生したアンケート調査費用82.5万円のみを費用として計上するよう修正を指示します。
この指摘を受けたオルツの社長は、ある意味で「学習」してしまいます。「売上先と外注先が同じだと監査法人にバレるのか」という知恵を付けてしまったのです。そして、「だったら売上と外注先を同一の相手にせず、支払い項目を分けて分割払いにすればバレないのではないか」という、さらに巧妙な手口を考え始めます。不正は進化していきます。
スラックなどのツールで部下に対し、バレにくいスキームを指示し始め、今度は全く別のL社との間で「同額取引バージョン2」を開始します。L社を「セールスパートナー」と位置付け、AI GIJIROKUのアカウント販売を代行してもらうという名目で200万円の売上を計上。しかし、この200万円はそのまま返還せず、100万円は「チャットサポート費用」、もう100万円は「カスタマーリレーション対応費用」といった具合に、複数の名目で分割してL社に還流させるようになりました。
広告宣伝費を使った循環取引(バージョン2)
2020年12月以降、社長はさらに売上目標を「10億円」に設定し、不正の規模は拡大していきます。よりバレにくくするために、「セールスパートナーとオルツが直接取引するからバレる。間に第三者を入れて循環取引にすればバレないのではないか」と画策します。
そして、不正は「広告宣伝費を使った循環取引(バージョン2)」へと進化します。
このスキームでは、セールスパートナーとオルツの間に「広告代理店(グル)」が加わります。
1. オルツからセールスパートナーへ「アカウント発行」(→オルツの売上3億円)
* オルツはセールスパートナーにAI GIJIROKUのアカウントを発行し、その対価として3億円を受け取る(オルツの売上)。
2. オルツから広告代理店へ「広告宣伝費」の支払い(3.3億円)
* オルツは広告代理店に広告宣伝を依頼し、その費用として3.3億円を支払う。実際には広告宣伝活動は行われない。
3. 広告代理店からセールスパートナーへ「還流」(3億円)
* 広告代理店は、オルツから受け取った3.3億円のうち3億円を、セールスパートナーに還流させる。広告代理店は手数料として3,000万円を受け取る。
この仕組みにより、オルツは売上3億円を計上すると同時に、広告宣伝費3.3億円を計上することになります。資金はぐるぐる回るだけで、オルツは広告代理店に支払う手数料分だけ損をする形です。しかし、社長は「1億円の売上成果が出るのであれば、少しでもプラスになるのであれば1億円近くの広告宣伝費はかけても良い」と、「行ってこい」の取引を指示していたと報告書には記されています。
この新たなスキームの開始により、オルツの内部管理体制、いわゆる内部統制は全く追いついていませんでした。AW監査法人は2021年6月頃から、「内部統制ができていない。新しいスキームの取引を開始したのに、整備が全く進んでいないではないか」と強く改善を求めています。
さらに、AW監査法人はこの新たな循環取引も看破します。M社とM社、R社とQ社といった、一見異なる企業間の取引に見えても、実態は「同じ社長」「同じ事務所」であったり、「グループ会社」であったりすることを発見し、「これらは実質的に同一企業であり、循環取引ではないか」と指摘したのです。
監査法人はオルツに対し、売上や広告サービスの「実在性」が確認できない限り監査は完了できないと突きつけます。しかし、オルツはグループ外のA社を間に挟むなどして、さらにスキームを複雑化させ、監査法人を欺こうとします。この時点で、オルツは製品開発や事業成長に時間を費やすべきスタートアップ企業としての本質を見失い、小ざかしい不正工作にばかり力を注ぐようになっていたのです。
最終的にAW監査法人は、循環取引の可能性が極めて高く、それを否定する証拠も提出されないことから、「これ以上は監査を継続できない」と判断。2021年12月期の監査計画を打ち切り、オルツの監査から降りることを決断しました。この結果、2021年12月期の監査は完了しませんでした。
研究開発費を隠れ蓑にした循環取引(バージョン3)
AW監査法人の離反後も、オルツの不正は止まりませんでした。今度は、株主から広告宣伝費が過剰であることの指摘が入ります。循環取引で広告宣伝費を巨額に計上していたため、それが赤字の原因となっていると見られたのです。
そこでオルツは、「広告宣伝費を増やさなければいい」という発想で、不正をさらに進化させます。それが「研究開発費を使った循環取引(バージョン3)」です。
このスキームでは、新たに「研究開発業者」を組み込みます。
1. オルツから研究開発業者へ「研究開発委託費」の支払い
* オルツは研究開発業者に研究開発を委託するという名目で資金を支払う。これは研究開発費として計上される。
2. 研究開発業者から広告代理店へ、そしてセールスパートナーへ
* 研究開発業者は受け取った資金を広告代理店へ、広告代理店はそれをセールスパートナーへと還流させる。
3. セールスパートナーからオルツへ「アカウント発行」(→オルツの売上)
* セールスパートナーはオルツにアカウント発行費用を支払い、オルツは売上を計上する。
このように、直接的な資金のやり取りはオルツと研究開発業者の間だけに見えるため、「これは研究開発費だ」と主張することで、広告宣伝費を増やさずに循環取引を継続しました。
調査報告書によると、2021年から2024年10月までの累計で、研究開発業者には約16.6億円、広告代理店には実に138億円もの資金が流れていました。そして、セールスパートナーからは137億円がオルツに還流し、売上として計上されていたのです。
これらの巨大な資金は、VCなどから調達した資金が自転車操業的に回されていたことを示唆しています。グラフを見ると、不正な売上と、広告宣伝費および研究開発費の金額がほぼ同額になっており、一見しただけで循環取引が行われていたことが明らかです。第三者委員会報告書も、「本件SPスキーム(セールスパートナーを介したスキーム)による資金循環はいわゆる循環取引に他ならない」と断定しています。
監査法人との攻防、そして交代
AW監査法人が監査を打ち切った後、オルツは別の監査法人(公認の監査法人)に交代します。しかし、この監査法人の交代劇の裏にも、オルツの巧妙な嘘と隠蔽工作が影を落としていました。
AW監査法人は、公認の監査法人に対して引き継ぎの際、明確に「循環取引の疑義がある」という懸念を伝えていたことが報告書で示されています。文書にもその記録が残っていたというのですから、公認の監査法人はこの事実を認識していたはずです。
しかし、公認の監査法人は、オルツ経営陣の巧みな説明と改ざんされた資料によって丸め込まれてしまいます。例えば、高額な広告宣伝費について質問すると、「これは将来を見据えた戦略的な投資であり、一時的に赤字を出すことは想定内だ」といった、もっともらしい説明をする。さらに、改ざんされた契約書や請求書など、外観上は整合性の取れた書類を提示され、「売上も順調に伸びている」という状況も相まって、公認の監査法人は「不正による重要な虚偽表示を示唆する状況があると識別をしていなかった」と判断してしまったのです。
結果として、公認の監査法人は「追加で監査手続きを行う必要はない」と判断し、AI GIJIROKUアカウントの実在性や広告宣伝活動の実態などを深く検証することなく、不正を見過ごしてしまいました。AW監査法人が残した警告を深く受け止めず、目の前の情報だけで判断してしまったことは、監査制度の信頼性にも大きな疑問符を投げかけることになりました。
不正の末期:証拠隠滅と嘘の説明
不正が長期化し、複雑化するにつれて、オルツの経営陣はさらに悪質な行為に手を染めていきます。それは、証拠の改ざんと虚偽の説明です。もはや、企業としての倫理観は地に落ちていたと言えるでしょう。
具体的には、以下のような行為が行われていました。
- 契約書の改ざん: 不利な情報を削除したり、日付を修正したりする。
- 電子メールの改ざん: 不正に関するやり取り(例えば「総裁を行わないという趣旨」といった指示)を削除し、無害なやり取りであるかのように偽装する。
- 請求書の改ざん: 品目や金額を意図的に修正し、関係者を欺こうとする。
これらの行為は、もはや不正の「末期症状」と言えるでしょう。本来、事業成長のために使うべき時間と労力を、不正の隠蔽と証拠改ざんに費やしていたのです。
さらに深刻なのは、オルツの経営陣がVC、主幹事証券会社、そして上場審査を行う東京証券取引所(JPX)の審査部に対しても、平然と虚偽の説明を繰り返していたことです。
特に、JPXに対する監査法人交代の理由説明は衝撃的です。オルツは、「AW監査法人はAI業界のベンチャー企業に対する理解が不足しており、上場準備体制における教科書的な指導しかしない。当社にはそぐわない指導内容だった」と、あたかもAW監査法人が無能であるかのように批判しました。そして、「当該取引の不適性の事実が一切確認できなかったとの見解であった」と、事実と異なる虚偽の説明を堂々と行ったのです。
このように、オルツの経営陣は、関係者すべてを騙し、虚偽の情報を積み重ねることで、上場という目標を達成しようとしました。この時点での企業の体質は、もはや正常とは言えませんでした。
第三者委員会報告書が示す厳然たる事実
第三者委員会調査報告書は、オルツの行った一連の不正に対して、極めて厳しい言葉でその行為を断罪しています。報告書の一部を引用すると、その怒りにも似た強い批判の言葉が読み取れます。
「ゲートキーパーとしての役割を有する(中略)オルツは、これらの意義を理解せずに適切な外形を取り繕うかのような対応に及んだものであり、このような対応は監査制度や上場審査制度の根幹を揺るがしかねない強い批判に値する行為である。また当社がベンチャーキャピタル等の多数の株主に対して事実と異なる説明や回答をしていたことについても企業と投資家との信頼関係を根本から損なうものであり、将来的な企業の資本調達の円滑性には悪く影響を及ぼす可能性があると言わざるを得ない。このような経緯があるにも関わらずオルツが上場を果たし不特定多数の投資家の投資対処となるに至ったことは誠に遺憾である。」
まさに、これは市場の健全性そのものを揺るがす行為であり、極めて罪深いと断じているのです。スタートアップ企業が本来備えるべき誠実さや革新性とはかけ離れた、安易な不正に手を染め、それを隠蔽し続けたオルツの行為は、スタートアップ市場全体に対する不信感を醸成しかねないものでした。
80億円もの資金を投資家から調達したと言われるオルツ。その資金が、事業成長ではなく、不正な売上の水増しと隠蔽工作のために無駄に費やされたことは、多くの人々に影響を与え、社会的な損失を生み出しました。
不正の結末:上場廃止への急展開
株式会社オルツの不正会計事件は、急展開を迎えました。第三者委員会調査報告書の公表後間もなく、2025年7月30日には上場廃止が決定され、同時に民事再生法の適用を申請するという事態に至りました。これは事実上の倒産と言えるでしょう。
不正によって手に入れた上場は、わずか半年で幕を閉じ、オルツの物語は悲劇的な結末を迎えました。この事件は、単一企業の不祥事として片付けられるものではありません。日本の資本市場、上場審査制度、そして監査法人というゲートキーパーのあり方にまで、根本的な問いを投げかける一大事件です。
今後、上場審査の厳格化、監査法人のチェック体制の強化、そしてスタートアップ企業のガバナンスに対する意識改革など、様々な制度変更や意識改革が求められることになるでしょう。
オルツ事件から学ぶべき教訓と今後の展望
株式会社オルツの不正会計事件は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。
1. 安易な不正は、より大きな不正を呼び、最終的に企業を破滅させる:
資金繰りの悪化という初期の課題に対し、短期的な売上水増しという安易な解決策に飛びついたことが、循環取引の巧妙化、証拠隠滅、虚偽説明へとエスカレートし、最終的に企業の命運を絶ちました。不正は一度手を出せば、なかなか引き返せないことを痛感させられます。
2. 内部統制の重要性とその形骸化の危険性:
新しいスキームの取引が始まるたびに、内部統制の整備が追いついていないことをAW監査法人は指摘していました。しかし、オルツはこれに真摯に向き合わず、結果として不正が野放しになってしまいました。スタートアップ企業であっても、成長に合わせて適切な内部統制を構築することの重要性は、言うまでもありません。
3. 監査法人のゲートキーパーとしての役割と限界:
AW監査法人は不正を見抜き、監査を打ち切るという厳しい判断を下しました。しかし、後任の監査法人は、結果的に不正を見過ごしてしまいました。監査法人がいかに企業に騙されず、独立性を保ち、実態を深く掘り下げて検証できるかという、その専門性と使命の重さを再認識させられます。特に、引き継ぎ情報があったにもかかわらず、なぜ見抜けなかったのかという点は、今後の監査制度の議論において重要な論点となるでしょう。
4. 投資家保護の重要性とデューデリジェンスの徹底:
VCを含む投資家たちは、オルツの将来性に期待して多額の資金を投じました。しかし、その裏では大規模な不正が行われていました。投資家は、企業の成長性だけでなく、その経営の健全性、特に不正リスクに対するデューデリジェンス(詳細調査)をさらに徹底する必要があることを示唆しています。
このオルツの事件は、日本の資本市場の信頼性を守る上で、決して風化させてはならない事例です。これから、上場審査基準の見直し、監査法人の審査プロセスや引き継ぎルールの改善、そしてスタートアップ企業に対するガバナンス指導の強化など、様々な方面で議論と改革が進むことが予想されます。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではいけません。私たちはこの事件から学び、より健全で信頼できる市場を築いていく責任があります。
—
免責事項
本記事は、株式会社オルツの第三者委員会調査報告書および関連報道に基づき、元上場企業の開示責任者として解説したものです。情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、信頼性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。また、本記事の内容は、いかなる投資判断を推奨するものではなく、読者の皆様の最終的な判断はご自身の責任において行われるものとします。本記事の内容によって生じた直接的、間接的ないかなる損害についても、筆者および運営者は一切の責任を負いません。本記事で言及した企業や個人に関する記述は、公開情報に基づくものであり、特定の個人や組織を誹謗中傷する意図はありません。


