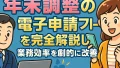業務改善・自動化の鍵!業務内容を正確に聞き出す最適な手法「スクリーン録画+AI分析」とは?
業務改善や自動化のプロジェクトに携わる皆さんなら、一度は経験があるのではないでしょうか?「この業務、自動化すればもっと効率的になるはずなのに、肝心の業務内容がうまく聞き出せない…」。まさに、多くのプロジェクトマネージャーや担当者が直面する、最も困難な壁の一つが「業務内容の正確な把握」です。どれだけ経験を積んでも、いざ担当者から業務内容を聞き出そうとすると、その難しさに直面します。
私も長年、業務改善自動化の仕事に携わる中で、この「聞き出す」というプロセスに最も頭を悩ませてきました。担当者が自身の業務を客観的に、そして漏れなく説明することは極めて困難です。人によって作業の進め方や判断基準が異なったり、無意識に行っている「暗黙知」が非常に多かったりするため、言葉だけで業務の全体像や細部を正確に把握することはほぼ不可能に近いのです。
しかし、ご安心ください。本記事では、この業務内容を聞き出すことの難しさを深掘りし、従来のヒアリングやアンケートといった手法が抱える根本的な課題を明らかにします。そして、その課題を根本から解決し、最も効率的かつ正確に業務を可視化する画期的なアプローチ、それが「スクリーン録画とAI分析」の組み合わせです。この手法がいかに担当者の負担を最小限に抑えながら、最大の改善効果を生み出すのかを詳しく解説し、具体的な手順から得られる成果まで、皆さんの業務改善プロジェクトを成功に導くためのヒントを惜しみなくご紹介していきます。

業務内容のヒアリングがなぜこんなにも難しいのか?見えない壁の正体
業務改善や自動化を進める上で、業務内容のヒアリングは不可欠なステップです。しかし、この最初の段階でつまずき、プロジェクトが停滞してしまうケースが後を絶ちません。なぜ、業務内容を正確に聞き出すことは、これほどまでに難しいのでしょうか。その背後には、いくつかの見えない壁が存在します。
まず、担当者自身の「説明不足」や「主観」が大きな要因となります。多くの人は、自分が日常的に行っている業務を客観視することが困難です。まるで呼吸をするように、あるいは箸を使うように、無意識のうちに特定の作業や判断を行っているため、「当たり前すぎて説明するまでもない」と感じてしまうのです。結果として、重要なステップが省略されたり、具体的な判断基準ではなく「なんとなく」「感覚で」といった抽象的な表現が使われたりすることが頻繁に起こります。また、長年その業務に携わってきた担当者ほど、専門用語を多用しがちで、ヒアリング側がその言葉の意味を正確に理解できないというミスマッチも生じます。
次に、「属人化」と「暗黙知」の弊害も深刻です。特定の個人しかできない業務や、言語化されていないノウハウ(暗黙知)が多ければ多いほど、業務内容を正確に聞き出すことは困難になります。例えば、「Aさんの判断基準」と「Bさんの判断基準」が微妙に異なる場合、どちらが「正しい」業務フローなのかを特定するのは至難の業です。このような属人化された業務は、文書化されていないがゆえに、口頭で説明しようとしても、どうしても抜け漏れや矛盾が生じてしまいます。
さらに、多忙な現場の現実もヒアリングの難しさを助長します。日々、膨大な業務に追われている担当者にとって、改めて自分の業務を棚卸しし、詳細に説明する時間は大きな負担です。改善の必要性は理解しつつも、目の前の緊急性の高い業務に優先順位をつけざるを得ず、ヒアリングや文書化の時間が後回しになってしまうことは少なくありません。「時間がなくて、まともにヒアリングする暇がない」「ようやく話を聞けたと思ったら、時間切れで中途半端に終わってしまった」といった経験は、多くの業務改善担当者が抱える共通の悩みでしょう。
加えて、言葉の「定義の曖昧さ」も聞き取りを難しくする要因です。例えば、「データをチェックする」という一言でも、担当者によって「目視で確認する」「ツールで自動チェックする」「過去データと照合する」など、具体的な作業内容は大きく異なります。このような曖昧な言葉遣いが、業務フロー全体を不透明にし、正確な理解を妨げてしまうのです。
最後に、担当者側の「心理的ハードル」も無視できません。自分の業務を詳細に説明することは、時に「自分の仕事が評価される」「非効率な部分やミスが指摘される」といった不安を伴います。特に、これまで属人的に進めてきた業務ほど、そのプロセスの公開に抵抗を感じる人もいるでしょう。このような心理的な壁は、率直でオープンな情報提供を阻害し、結果として業務内容の正確な把握を困難にするのです。
これらの見えない壁が複合的に作用することで、業務内容を聞き出すという最初のステップが、プロジェクト全体を停滞させる大きなボトルネックとなってしまうのです。
従来の業務把握手法が抱える根本的な課題
業務内容を把握するための手法はいくつか存在しますが、それぞれに一長一短があり、先に述べた「見えない壁」を完全に乗り越えることは難しいのが現状です。ここでは、これまで広く用いられてきた代表的な手法が抱える根本的な課題について、深掘りして考えてみましょう。
ヒアリング形式:表面的な理解に留まるリスクと時間的制約
対面やオンラインで担当者に話を聞く「ヒアリング形式」は、最もオーソドックスな方法です。担当者と直接対話することで、疑問点をその場で確認し、ある程度の情報を引き出すことができます。しかし、この手法にはいくつかの限界があります。
まず、担当者の記憶や認識に依存するため、情報の抜け漏れや主観が入り込みやすいというリスクがあります。人は、日常的に行っている作業の一部を無意識的に省略して説明したり、「やっているつもり」や「感覚値」で語ってしまったりすることが少なくありません。特に、イレギュラーな対応や、特定の条件でのみ発生する例外処理などは、ヒアリング時に担当者が思い出すことができず、見過ごされてしまうケースが多々あります。結果として、ヒアリングで得られた情報と実際の業務プロセスに乖離が生じ、正確な業務フローの構築が困難になるのです。
また、深いレベルまで掘り下げようとすると、ヒアリングに膨大な時間がかかります。複数の担当者から話を聞く場合や、業務が複雑であればあるほど、拘束時間は増大します。多忙な現場では、担当者が長時間のヒアリングに対応できないことも多く、情報が十分に得られないまま終わってしまうこともしばしばです。さらに、複数人からヒアリングした場合、担当者間の認識のずれや言葉の解釈の違いが明らかになり、それを解消するための調整にもさらなる時間と労力が必要となります。
アンケート/業務フロー記入シート方式:文書化の壁と無意識の作業の欠落
定型フォーマットに沿って業務を記入してもらう「アンケート/業務フロー記入シート方式」は、一度に多くの人から情報を集めるのに有効な手段に見えます。しかし、この方法にも大きな課題が潜んでいます。
最大の壁は「文書化の手間」です。詳細な業務フローを言葉で書き起こす作業は、担当者にとって非常に大きな負担となります。日々の業務に追われている中で、わざわざ時間を割いて煩雑なシートを埋めることは、かなりのモチ切ベーションと集中力を要します。結果として、アンケートの回収率が低迷したり、回答内容が不十分だったりすることが頻発します。多くの企業で「アンケートを出したものの、回答が返ってこない」「記入された内容は非常に抽象的で、結局何をやっているのかよくわからない」といった事態に陥っています。
加えて、担当者本人も無意識に行っている作業や、判断の裏にある思考プロセスは、シート上ではなかなか表現されません。例えば、PC操作で「この条件ならA、そうでなければB」といった明確な分岐点は記述されても、「AとBのどちらを選ぶか、画面の情報から判断する」といった、人間特有の判断基準や経験に基づく微妙なニュアンスは省略されがちです。これにより、業務フローシートは一見完成しているように見えても、実態と乖離した情報になってしまうリスクが高いのです。また、回収された情報を整理し、分析する側にも膨大な工数がかかり、せっかく集まった情報も宝の持ち腐れになってしまうこともあります。
同席・観察方式(シャドーイング):時間と場所の制約、そして心理的側面
実際に担当者の横で作業を見ながらメモを取る「同席・観察方式(シャドーイング)」は、最もリアルな情報が得られる手法と言えるでしょう。担当者のPC操作や判断の瞬間を間近で見ることができるため、言葉だけでは伝わりにくい「暗黙知」や、細かな操作手順を直接把握できます。
しかし、この手法には看過できない大きな制約があります。まず、時間コストが膨大であるという点です。一人の担当者の業務を一日中、あるいは数日間にわたって観察し続けることは、観察側と観察される側の双方に多大な時間的負担を強います。改善対象となる業務が多岐にわたる場合、全ての業務をシャドーイングするのは現実的ではありません。また、昨今のリモートワークが普及した環境では、物理的に隣に座って観察するという行為自体が非現実的であり、実施が非常に困難です。
さらに、観察される側の心理的側面も考慮する必要があります。人が観察されていることを意識すると、普段通りの業務が行われなくなる、いわゆる「ホーソン効果」が発生する可能性があります。無意識のうちに効率的なフリをしてしまったり、普段ならしないようなミスを隠そうとしたりするなど、本質的な業務フローが見えにくくなるリスクがあるのです。また、観察者はあくまで「見る」立場であり、担当者の思考プロセスや、なぜその判断に至ったのかという背景までを完全に把握することは難しいでしょう。これにより、得られる情報は豊富であっても、深掘りされた理解には至らない場合があります。
これらの従来の業務把握手法は、それぞれに利点があるものの、いずれも「担当者の負担が大きい」「情報の抜け漏れや主観が入り込みやすい」「時間や場所の制約が大きい」といった根本的な課題を抱えています。これらの課題を解決し、より効率的かつ正確に業務内容を把握できるアプローチが求められているのです。
業務把握のゲームチェンジャー:スクリーン録画とAI分析の強力な組み合わせ
従来の業務把握手法が抱える課題を乗り越え、最も効率的かつ正確に業務内容を可視化する方法、それが「スクリーン録画からのAI分析」です。このアプローチは、担当者のリソースをほとんど奪うことなく、実際の業務を「ありのまま」に記録し、さらにAIの力を借りてその内容を構造化・解析することで、これまでにないレベルで業務理解を深めることを可能にします。
なぜスクリーン録画が「最も効率的かつ正確」なのか
スクリーン録画が画期的なのは、その「客観性」と「網羅性」にあります。担当者は普段通りに業務を行うだけで、その全てのPC操作、画面遷移、入力内容、そして判断の瞬間までが、詳細な動画データとして記録されます。
この手法は、担当者への負担を最小限に抑えます。特別な準備や時間調整は不要で、いつもの業務をただ録画してもらうだけだからです。ヒアリングのように言葉を選んだり、アンケートのように時間をかけて文章を書いたりする必要がありません。この「ながら作業」で情報が取得できる点が、多忙な現場にとって非常に大きなメリットとなります。
また、リモートワーク環境においても、場所を選ばずに実施できる点も強力な強みです。観察者が現場に足を運ぶ必要がなく、各担当者が自宅やサテライトオフィスで業務を行う様子を効率的に記録できます。
さらに、スクリーン録画は「無意識の作業」や「イレギュラー対応」をも可視化します。普段、担当者が「当たり前」と感じて説明しないような細かなマウス操作やキーボードショートカット、あるいはごく稀に発生するエラー対応なども、動画には全て記録されます。これにより、ヒアリングやアンケートでは見落とされがちだった「暗黙知」を漏れなく捉えることができるのです。
録画された動画データは、何度も繰り返し見返すことが可能です。これにより、一度では見落としていた細かな操作や判断の背景を、じっくりと時間をかけて分析できます。これは、業務プロセスの再現性を高め、より深く、正確な理解へと繋がります。
具体的な手順と担当者の協力体制の構築
スクリーン録画を用いた業務把握の手順は非常にシンプルです。
まず、担当者には作業中のPC画面を録画してもらいます。録画ツールは、WindowsやMacに標準搭載されている機能(WindowsのゲームバーやXbox Game Bar、Macのスクリーンショットツールなど)でも十分対応可能です。より高機能なツールとしては、Zoomの録画機能や、クラウドベースのLoomなども有効でしょう。
録画された動画データは、Googleドライブなどのクラウドストレージにアップロードしてもらいます。大容量のデータアップロードが容易であり、業務の種類や担当者ごとにフォルダを整理してもらうことで、後々の分析もスムーズに進められます。
このプロセスを進める上で重要なのは、担当者との協力体制をいかに構築するかです。プライバシーとセキュリティへの配慮は最優先事項です。機密情報が含まれる可能性のある画面については、マスキング処理を依頼するか、特定の箇所は録画しないよう事前に指示を出すなど、慎重な対応が求められます。また、録画の目的を明確に伝え、担当者に納得してもらうことが不可欠です。「監視が目的ではなく、皆さんの業務をより楽にするための共同作業である」というメッセージを丁寧に伝え、心理的なハードルを軽減する努力が求められます。
AI分析による業務記述書の自動生成と深掘り
録画動画から得られた情報は、生データだけではまだ分析しにくい部分もあります。ここでAIの力が最大限に発揮されます。
まず、こちら側(業務改善担当者)では、録画動画を見ながら業務の流れや判断ポイントを箇条書きで整理します。例えば、「〇〇システムにログイン」「△△のボタンをクリック」「□□の情報を入力」「エラー発生時は××を再度確認」といった具体的な操作と判断のステップを洗い出します。
次に、この整理したリストをAIに渡します。そして、「この情報を元に、誰が読んでも分かる具体的な業務説明書を自動生成してください」と指示します。AIは、入力された箇条書きの情報を基に、文章の構成を整え、専門用語を平易な言葉に変換し、曖昧な表現を具体化してくれます。例えば、「判断する」という抽象的な記述に対し、動画から得られた文脈を読み取り、「具体的に画面上のどの情報を見て、どのような条件で判断しているのか」を明文化するサポートをしてくれるでしょう。AIによる業務記述書の自動生成やマニュアル作成の効率化については、こちらの記事もご参照ください。
さらに、AIは動画の内容を分析し、業務におけるボトルネックや非効率な箇所を特定するのにも役立ちます。例えば、特定の作業で頻繁に停止している箇所や、繰り返し同じ操作を行っている箇所などをAIが示唆することで、改善すべきポイントがより明確になります。
また、自動生成された業務説明書は、そのまま教育用マニュアルとしても活用できます。動画編集ソフトで要所に説明テキストや、AIが抽出した重要な操作ポイントをテキストとして加えれば、視覚的にも理解しやすいマニュアルが効率的に作成可能です。
このスクリーン録画とAI分析の組み合わせは、業務内容を聞き出すことの難しさを根本から解決し、迅速かつ正確な業務可視化を実現します。
参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」では、日本の多くの企業がDX推進に課題を抱えつつも、データ活用やAIの導入による業務効率化への期待が高まっていることが示されています。本手法は、まさにその期待に応える現代的なアプローチと言えるでしょう。
「見える化」から始まる劇的な業務改善:成果と持続可能なアプローチ
スクリーン録画とAI分析によって業務内容が詳細に「見える化」されると、その後の業務改善・自動化プロジェクトは劇的に加速します。この効率的な業務把握手法は、単なる情報収集に留まらず、具体的な成果と持続可能な改善文化を組織にもたらします。
リソースのボトルネック特定と優先順位付け
録画データとAIによる分析を通じて、どの作業が最も時間と労力を奪っているのか、つまり「リソースのボトルネック」が明確に浮き彫りになります。例えば、特定のアプリケーションへのデータ入力に何時間も費やされていること、あるいは複数のシステムを跨ぐ複雑な確認作業に膨大な時間がかかっていることなどが、客観的なデータとして示されます。これにより、「感覚値」や「思い込み」ではなく、明確なデータに基づいて自動化の優先順位を決定できるようになります。
最も費用対効果が高い箇所から優先的にRPA(Robotic Process Automation)などのスクリプトを導入していくことで、生成AIを活用したスクリプト量産による業務効率化は、大企業の経理現場でも実践が進んでいます。投資対効果を最大化できます。例えば、「毎月2件」といった具体的な自動化目標を設定し、着実に業務改善を進めていくことが可能になります。このように、小さな成功を積み重ねることで、プロジェクト全体の推進力が高まります。
担当者の負担軽減とモチベーション向上
煩雑で時間のかかる定型業務が自動化されると、担当者の業務負荷は劇的に軽減されます。これまで長時間労働の原因となっていたルーティンワークから解放され、本来集中すべきクリエイティブな業務や、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。これは、単なる時間削減に留まらず、担当者のストレス軽減、ひいてはワークライフバランスの改善に直結します。
自身の業務が改善され、効率化されていくプロセスを目の当たりにすることで、担当者のモチベーションは大きく向上します。「毎晩徹夜していたような業務が、午前中で終わるようになった」といった具体的な成功体験は、改善へのさらなる意欲を引き出し、自らも業務プロセスを見直し、改善を提案する文化を育む土台となります。この「最小限の負担で最大の効果を生む」というアプローチが、担当者にとっての大きなメリットであり、プロジェクト成功の鍵を握る要因となります。
組織全体の生産性向上とDX推進への貢献
業務プロセスが詳細に可視化され、自動化が進むことは、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。特定の個人に依存していた業務が標準化・形式知化されることで、属人化が解消され、業務の品質が安定します。これは、急な担当者の異動や退職が発生した場合でも、業務が滞るリスクを低減し、事業継続性を高めることに繋がります。
また、業務マニュアルの自動生成や効率的な作成が可能になるため、新人教育にかかるコストや時間を大幅に削減できます。引き継ぎもスムーズになり、組織全体の知識共有が進みます。
さらに、データに基づいた業務可視化と改善サイクルは、組織のデジタル変革(DX)を加速させる強力な原動力となります。経営層は、具体的なデータに基づいて業務改善の進捗や効果を把握できるようになり、より戦略的な意思決定が可能になります。継続的な改善の取り組みが、組織全体の競争力強化と新たな価値創造へと繋がっていくのです。AIをビジネスに活用し、仕事の生産性を劇的に変える具体的なテクニックについては、別記事で100選を紹介しています。
持続可能な業務改善文化の醸成
スクリーン録画とAI分析を組み合わせた業務改善アプローチは、一度きりのプロジェクトで終わるものではありません。これは、組織内に「継続的な改善文化」を醸成するための強力なツールとなり得ます。
担当者自身が自分の業務を見直し、改善提案を行う機会が増えることで、主体性が育まれます。AIツールを活用した効率的な分析手法が組織全体に定着すれば、日常的に業務のボトルネックを特定し、改善策を検討する習慣が生まれるでしょう。
このように、担当者に無理をさせず、最小限の負担で最大の効果を生み出すアプローチは、組織全体のエンゲージメントを高め、より良い働き方へと変革する持続可能なサイクルを確立します。業務内容の正確な把握こそが、成功への最短ルートであり、未来を拓く第一歩となるのです。
まとめ:業務内容の正確な把握こそ、成功への最短ルート
業務改善や自動化のプロジェクトは、しばしば「業務内容が正確に把握できない」という壁にぶつかり、停滞しがちです。従来のヒアリングやアンケート、観察といった手法には、それぞれ抜け漏れや時間的制約、担当者の負担といった根本的な課題が存在していました。しかし、現代のテクノロジーを活用した「スクリーン録画とAI分析」の組み合わせは、これらの課題を鮮やかに解決する画期的なアプローチです。
この手法は、担当者の負担を最小限に抑えながら、実際の業務プロセスを客観的かつ網羅的に可視化します。録画された生データは、AIの力を借りることで、誰が読んでも理解できる具体的な業務説明書へと変換され、さらにボトルネックの特定やマニュアル作成までを効率的にサポートします。
その結果として得られるのは、単なる業務の可視化だけではありません。明確なデータに基づく優先順位付けによる効率的な自動化推進、担当者の業務負担軽減とモチベーション向上、そして組織全体の生産性向上とDX推進への貢献という、計り知れないメリットをもたらします。
業務改善や自動化を成功に導くためには、何よりもまず、業務内容を正確に、そして深く理解することが不可欠です。本記事でご紹介した「スクリーン録画とAI分析」のアプローチは、そのための最も有効な手段であり、皆さんの組織がより生産的で、持続可能な成長を遂げるための強力な味方となるでしょう。
免責事項
本記事で紹介する業務改善手法は、一般的な情報提供を目的としています。個別の業務内容や組織体制、利用するツール、および関連する法的規制(特にデータプライバシーや個人情報保護、営業秘密の保護など)によっては適用が困難な場合や、専門家による詳細な検討、適切な同意形成が必要な場合があります。本手法を導入・実施するにあたっては、必ず関係部署(情報システム部門、法務部門など)や専門家と十分に連携し、自社の環境に合わせた適切な判断と対策を講じてください。本情報の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。