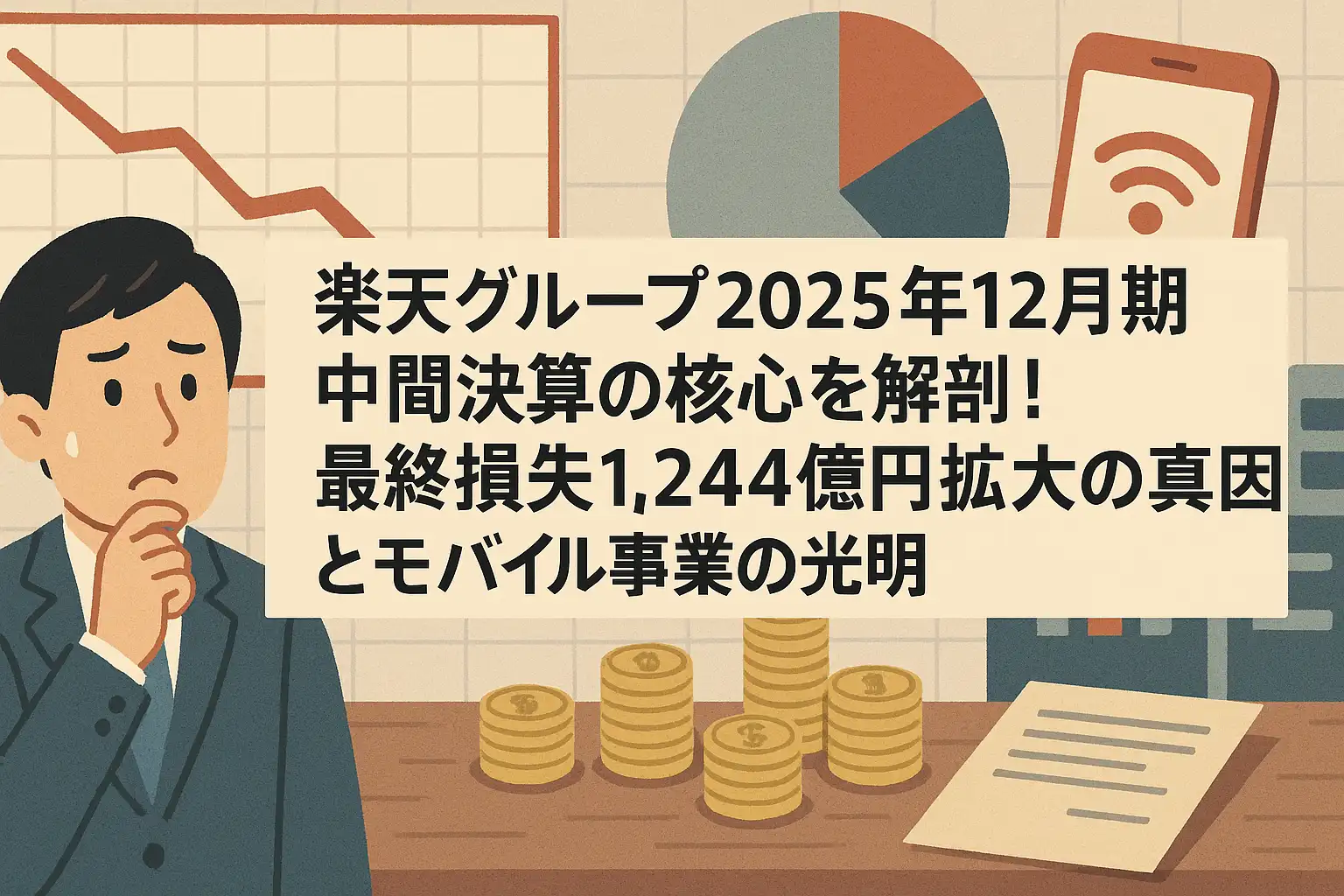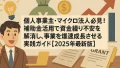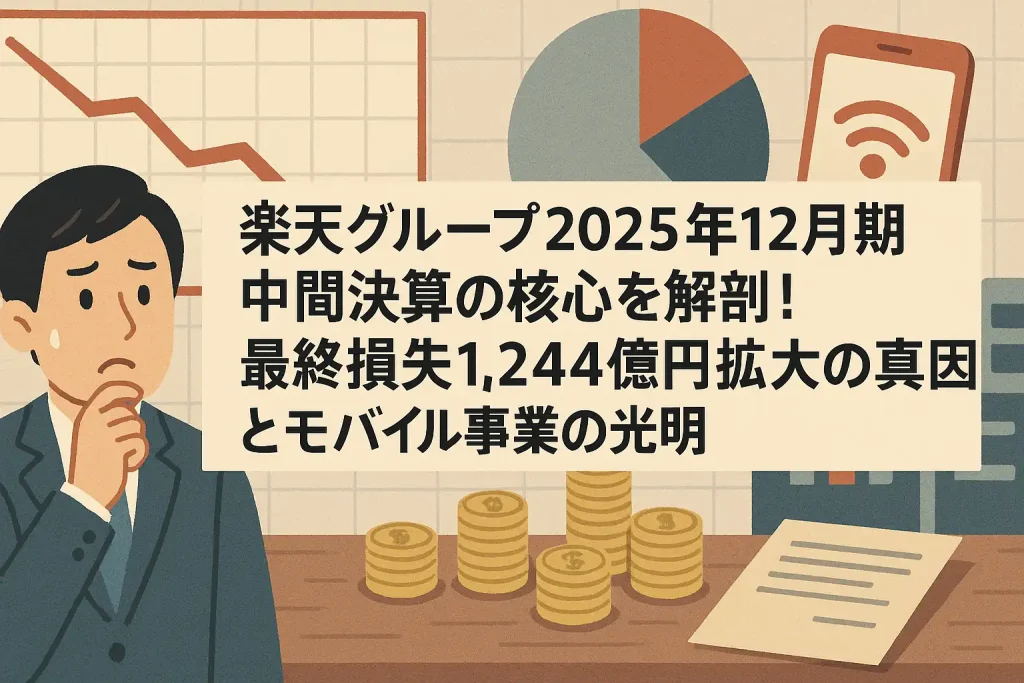
皆さんは普段、楽天のサービスをどれくらい利用していますか?楽天市場で買い物をする、楽天カードで決済する、あるいは楽天モバイルを使っている方も多いかもしれませんね。私たちの生活に深く根ざしている楽天グループが、先日、2025年12月期第2四半期(中間期)の連結決算を発表しました。
「売上は伸びてるらしい」「営業損失も改善してるって聞いたけど、でも最終的には赤字が拡大したって?」――そんな風に、今回の楽天グループの決算発表に疑問や関心を持った方も少なくないのではないでしょうか。前回の2025年12月期第1四半期決算について詳しくはこちらの分析記事をご参照ください。実はその通り、今回の発表はまさに「光と影」が交錯するような内容でした。売上収益は力強く二桁成長を達成し、長年の懸案だったモバイル事業も着実に改善の兆しを見せ、Non-GAAPベースでは営業利益の黒字転換まで果たしています。これだけ聞くと、まるで楽天がV字回復を遂げたかのように思えますよね。
しかし、その一方で、親会社の所有者に帰属する中間損失は前年同期から大きく拡大し、なんと1,244億円を超える規模となったのです。なぜ、売上が伸び、営業利益が改善しているのに、最終的な損失はこんなにも膨らんでしまったのでしょうか?一体、楽天の経営に何が起きているのでしょうか?
本記事では、この楽天グループ2025年12月期中間決算の発表内容を、皆さんが理解しやすいように徹底的に深掘りしていきます。特に、なぜ最終損失が拡大したのかという、最も気になる点に焦点を当て、その複雑な要因を一つずつ紐解いていきます。さらに、苦戦が続いていた楽天モバイルがEBITDA黒字化を達成したという明るいニュースの背景や、楽天グループ全体の今後の展望についても詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
楽天グループ、最新中間決算の全体像を読み解く:売上好調と営業改善の裏側
まずは、今回発表された楽天グループの2025年12月期中間決算の全体像から見ていきましょう。一見すると、非常にポジティブな数字が並んでいます。売上収益の力強い成長、そして営業損失の顕著な改善は、グループ全体の事業運営が着実に前進していることを示しています。
売上収益と営業利益の力強い成長
楽天グループの売上収益は、2025年12月期中間期(2025年1月1日~6月30日)において、1兆1,590億7,300万円を記録しました。これは前年同期の1兆509億800万円と比較して10.3%増という、まさに二桁成長です。この力強い売上成長は、インターネットサービス、フィンテック、モバイルという主要な3つのセグメント全てが堅調に推移した結果と言えるでしょう。特にフィンテック事業は、クレジットカードや銀行、証券といった各サービスが軒並み好調で、グループ全体の成長を力強く牽引しています。
さらに注目すべきは、IFRS(国際財務報告基準)ベースの営業損失が大幅に改善した点です。前年同期の△516億300万円の損失から、当期は△66億1,000万円の損失へと、その幅を大きく縮小しました。この改善は、モバイル事業における損失縮小が大きく寄与しており、長年にわたる楽天グループの課題であったモバイル事業が、ようやく収益改善のフェーズに入りつつあることを示唆しています。
非GAAP営業利益の黒字転換が示す経営努力
今回の決算発表で特に目を引くのは、Non-GAAP(非GAAP)ベースでの営業利益が黒字転換を達成したことです。Non-GAAP営業利益とは、IFRS基準では計上されるものの、企業の本業における収益力を測る上で調整される特定の費用や収益を除外して算出される指標です。楽天グループの場合、モバイル事業の基地局関連費用などが調整項目に含まれることが多いです。
このNon-GAAP営業利益が、前年同期の△372億7,300万円の損失から、当期は197億5,100万円の黒字へと転換しました。これは、楽天グループが事業構造の改善やコストコントロールに真剣に取り組んできた結果が表れたものと評価できます。本業の稼ぐ力が強化されている証であり、経営陣の努力が実を結びつつあることを示しています。株主や市場が最も注目する指標の一つである営業利益が黒字化したことは、楽天グループの経営健全化への強い意志と、その実現可能性を示唆する重要なポイントと言えるでしょう。
EBITDAから見るキャッシュ創出力の向上
決算分析において、営業利益と並んで重要視されるのが「EBITDA(イービットディーエー)」です。EBITDAとは、Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortizationの略で、税金や利息、減価償却費などを差し引く前の利益を指します。これは企業のキャッシュ・フロー創出力を評価する上で非常に有用な指標とされています。EBITDAの基本的な概念についてさらに詳しく知りたい方はこちら。
楽天グループのEBITDAは、1,830億9,000万円となり、前年同期比で53.1%もの大幅な増加を達成しました。Non-GAAP営業利益が黒字に転換し、それに加えて減価償却費などの非現金支出が調整されることで、キャッシュベースでの収益力が大きく向上していることがわかります。特にモバイル事業のように大規模な設備投資を伴う事業においては、減価償却費が大きくなりがちですが、EBITDAが大きく伸びるということは、事業が将来的に生み出すであろうキャッシュの期待値が高いことを示唆しています。このEBITDAの力強い伸びは、楽天グループが持続的な成長に向けた基盤を着実に固めつつある証拠と捉えることができるでしょう。
なぜ最終損失は拡大したのか?決算データが語る「不穏な影」
冒頭でお話しした通り、売上は伸び、営業損失も改善しているにもかかわらず、楽天グループの「親会社の所有者に帰属する中間損失」は前年同期の△759億6,200万円から、△1,244億3,500万円へと大幅に拡大しました。なんと、484億7,300万円もの損失拡大です。これは一体どういうことなのでしょうか?ここからが、今回の決算発表の「影」の部分、そして多くの人が疑問に思う核心に迫る部分です。決算資料を詳しく読み解くと、いくつかの非経常的かつ大きな損失要因が浮かび上がってきます。
金融収益の劇的な減少とLyft関連の影響
最終損失拡大の最も大きな要因の一つは、金融収益の劇的な減少です。前年同期には796億9,700万円もの金融収益があったものが、当期はわずか101億1,100万円にまで落ち込んでいます。この減少幅は実に約700億円にも上り、最終損失を押し上げる主要な要因となりました。
特に影響が大きかったのが、米国ライドシェア大手Lyft, Inc.の株式に関連する金融取引です。楽天グループは以前からLyft株を保有しており、その株式を対象とした「先渡売買契約」を結んでいました。この契約は、将来の特定の時点でLyft株を特定の価格で売買するというものです。前年同期には、この先渡売買契約に関連するデリバティブ評価益が158億4,200万円も計上されていました。しかし、当期は市場環境の変化やLyft株価の動向を受け、なんと67億5,900万円のデリバティブ評価損に転じてしまったのです。これは、利益が損失に変わっただけでなく、その額も大きかったため、金融収益全体を大きく押し下げる結果となりました。
さらに、金融費用については、前年同期の677億8,700万円から647億7,500万円に微減したものの、金融収益の減少幅があまりにも大きかったため、金融損益全体では大幅なマイナス寄与となりました。また、グループ全体の支払利息も増加傾向にあり、これらも間接的に最終損失に影響を与えています。特にLyft株式の先渡売買契約に係る金融負債の金利費用も発生しており、様々な金融取引が複雑に絡み合って最終的な数字に影響を与えていることが伺えます。
📉 赤字で揺れる楽天…しかし、その裏で進む「逆転の一手」がある。
それは生成AIが加速させる バイブコーディング革命。
今だから読める“禁断の黒字化戦略”をチェック!
👉 詳細はこちら
赤字の楽天をV字回復させる禁断の黒字化戦略 生成AIが加速させる「バイブコーディング」革命!
突発的な「非経常的損失」が重荷に
もう一つの大きな要因は、事業活動とは直接関係のない、突発的かつ非経常的な項目による損失が多額に計上されたことです。当中間連結会計期間に計上された非経常的な損失は合計で153億1,500万円に上り、前年同期の28億7,300万円から大幅に増加しました。これらの費用は、文字通り「経常的ではない」つまり、今後も継続的に発生するものではないと期待されますが、一時的に多額の損失として計上されたことで、最終利益を大きく圧迫しました。
具体的な内訳を見てみましょう。
- 国内スポーツ事業におけるコンサルティング契約の中途解約金(24億5,900万円): おそらくプロ野球の楽天イーグルスやサッカーのヴィッセル神戸といったスポーツ事業に関連する契約を、何らかの理由で途中で解約した際に発生した違約金と考えられます。
- カード債権流動化に係る消費税の追徴税額および延滞税額(49億4,300万円): クレジットカード事業で発生する債権を金融機関などに売却する「流動化」という手法において、過去の税務処理について当局から指摘を受け、消費税の追徴課税と延滞税が発生したものです。これは楽天カードなどの金融事業における会計処理のミス、あるいは解釈の相違が原因である可能性があります。
- 証券事業における不正アクセスに伴う顧客取引の補償に係る損失引当額(10億5,800万円): 楽天証券などの証券事業において、システムへの不正アクセスが発生し、その結果顧客の取引に損失が生じたことに対し、楽天側が補償を行うために積み立てた引当金です。セキュリティ対策の重要性を改めて認識させられる出来事と言えるでしょう。楽天証券の不正アクセス対策について詳しくはこちら。
- 過去に売却した子会社の債務の支払請求訴訟に係る引当金繰入額: すでに売却済みの旧子会社に関連する訴訟が提起され、その債務支払いが見込まれるため、事前に損失として引当金を計上したものです。
これらの非経常的な損失は、楽天グループが過去に抱えていた、あるいは突発的に発生した問題を処理するために要したコストであり、まさに「想定外の出費」として最終利益を大きく押し下げる要因となりました。
📉 赤字で揺れる楽天…しかし、その裏で進む「逆転の一手」がある。
それは生成AIが加速させる バイブコーディング革命。
今だから読める“禁断の黒字化戦略”をチェック!
👉 詳細はこちら
赤字の楽天をV字回復させる禁断の黒字化戦略 生成AIが加速させる「バイブコーディング」革命!
持分法投資損失と法人所得税費用の増加
さらに、最終損失を拡大させた要因として、持分法による投資損失の増加も挙げられます。楽天グループは、一部の関連会社への投資を「持分法」という会計処理で計上しています。この持分法を適用している企業の一つである「Rakuten Medical, Inc.」に対する投資について、46億2,600万円の減損損失を計上しました。減損損失とは、保有する資産の価値が著しく低下した場合に、その価値の下落分を損失として計上する会計処理です。Rakuten Medicalはがん治療に関する先進的な技術を持つ企業ですが、事業環境の変化や将来的な収益見通しの見直しなどにより、投資価値の再評価が行われた結果、減損が必要と判断されたのでしょう。
また、法人所得税費用が前年同期の177億9,700万円から357億1,000万円へと増加したことも、税引後の中間損失を押し上げる要因となりました。通常、利益が増えれば法人税も増えますが、今回は税引前損失が拡大している中で、税金費用が増えている点が複雑です。これは、特定の事業セグメントで利益が出ていることや、繰延税金資産の取り崩し、あるいは海外事業における課税のタイミングなど、複数の要因が絡み合っている可能性があります。
これらの複数の要因が複雑に絡み合い、売上成長や営業改善という「光」の部分がありながらも、最終的には親会社帰属最終損失が大幅に拡大するという「影」の部分を生み出したのです。
事業セグメント別詳細分析:楽天の未来を牽引する柱と課題
楽天グループの事業は、大きく「インターネットサービス」「フィンテック」「モバイル」の3つのセグメントに分かれています。今回の決算では、それぞれのセグメントが異なる顔を見せ、楽天グループ全体の成長と課題を浮き彫りにしています。
安定成長を続ける「インターネットサービス」
楽天グループの原点ともいえる「インターネットサービス」セグメントは、売上収益6,300億1,600万円(前年同期比6.9%増)、セグメント利益272億8,300万円(前年同期比4.0%増)と、堅実な成長を続けています。このセグメントには、中核である『楽天市場』をはじめ、旅行予約サイトの楽天トラベル、動画配信の楽天TV、楽天Koboなどのデジタルコンテンツ事業、広告事業などが含まれます。
『楽天市場』の流通総額と売上収益は順調に伸びており、これはEC市場全体の成長に加え、楽天独自のポイントプログラムやキャンペーン、そして物流サービスの強化が奏功していると言えるでしょう。特に、物流サービス「楽天エクスプレス」の拡充などにより、物流コストが効率化され、それによる損失縮小もセグメント利益に貢献しています。また、海外事業も堅実な成長を見せており、ECプラットフォームの強化や新規サービスの展開が、インターネットサービス全体の安定性を支えています。楽天のエコシステムの核となるこのセグメントが安定していることは、グループ全体の基盤を揺るぎないものにしています。
圧倒的な収益源「フィンテック」の進化
楽天グループの中でも、今や最も収益を稼ぎ出す柱となっているのが「フィンテック」セグメントです。売上収益は4,562億6,300万円(前年同期比15.2%増)と二桁成長を続け、セグメント利益も872億5,600万円(前年同期比16.8%増)と、その貢献度は圧倒的です。
フィンテックセグメントには、楽天カード、楽天銀行、楽天証券、楽天生命・損害保険、そして楽天ペイといった決済サービスが含まれます。今回の決算では、これらのサービスが全て増収を達成したと報告されています。クレジットカードの取扱高の伸長、銀行口座数の拡大、証券口座における顧客基盤の拡大、そして保険商品の販売増加などが、この力強い成長の原動力となっています。
特に、金融機関を取り巻く金利環境の変化も楽天フィンテックにとっては追い風となっており、運用利回りの向上も利益増に寄与していると見られます。楽天カードの「ポイント還元率の高さ」や、楽天銀行・楽天証券の「利便性の高さ」といったユーザーメリットが、顧客基盤の拡大に繋がり、それが収益へと直結している構図です。フィンテック事業は、楽天エコシステムにおける顧客の囲い込みと収益性の両面で、今後もグループ全体の成長を牽引していくでしょう。
期待と課題が交錯する「モバイル事業」:楽天モバイル単独EBITDA黒字化の意義
楽天グループにとって、常に最大の注目と同時に最大の課題でもあったのが「モバイル」セグメントです。今回の決算発表では、このモバイル事業から待望の明るいニュースが飛び込んできました。
モバイルセグメントの売上収益は2,228億2,800万円(前年同期比14.4%増)と堅調に増加。そして、セグメント損失は△883億1,200万円となり、前年同期の△1,195億500万円の損失から大幅に縮小しました。これは、通信品質の改善と積極的なマーケティング活動により、契約回線数が着実に増加していることが売上拡大に寄与していること、そして基地局建設費などのコストコントロールが奏功していることを示しています。
そして、最も大きなニュースが、楽天モバイル株式会社単独では、当第2四半期連結会計期間(4月~6月)に初めてEBITDA黒字化を達成したことです。EBITDA黒字化は、モバイル事業が事業そのものからキャッシュを生み出す体質に転換したことを意味します。これまで巨額の投資が必要とされ、赤字の主因であったモバイル事業が、ついに採算改善の重要な一歩を踏み出したのです。これは楽天グループ全体の財務健全化に向けた大きな前進であり、市場からも高く評価されるべきポイントです。
しかし、モバイルセグメント全体のIFRSベースでの損失はまだ残っています。EBITDAが黒字になったとはいえ、初期投資にかかった減価償却費などを考慮すると、IFRSベースでの営業利益や最終利益の黒字化にはまだ時間がかかる見通しです。それでも、モバイル事業が「稼ぐ力」を身につけ始めたことは、楽天グループの未来にとって大きな光明であることに間違いありません。
財政状態とキャッシュ・フローの動向:健全性への影響は?
ここまで、楽天グループの売上や利益、そして各事業セグメントの状況を見てきましたが、企業の全体像を把握するためには、財政状態(バランスシート)とキャッシュ・フロー(現金の流れ)も非常に重要です。今回の決算では、財務面でいくつか懸念される点も浮上しています。
自己資本と親会社持分の減少
まず、財政状態を示すバランスシートを見てみましょう。2025年6月30日時点での資本合計は1兆1,381億6,300万円となり、前連結会計年度末(2024年12月31日)から1,003億5,100万円減少しています。さらに重要なのは、親会社の所有者に帰属する持分合計が8,055億4,300万円となり、前連結会計年度末の9,278億6,800万円から減少した点です。
この減少の主な要因は、先に詳しく説明した親会社の所有者に帰属する中間損失1,244億3,500万円が計上されたことにより、利益剰余金(過去に稼いだ利益の蓄積)が1,364億1,700万円減少したためとされています。利益剰余金が減るということは、それまで積み上げてきた内部留保が目減りすることを意味し、企業の自己資金力が低下することに繋がります。
これに伴い、連結自己資本比率も、前連結会計年度末の4.7%から4.3%に低下しました。自己資本比率は、企業の財務の健全性を示す重要な指標の一つであり、総資産に占める自己資本の割合を示します。この比率が低いと、負債への依存度が高く、財務リスクが高いと判断されることがあります。楽天グループはモバイル事業への巨額投資で有利子負債が増大しており、自己資本比率の低下は、今後の資金調達や格付けにも影響を与える可能性があるため、継続的な改善が求められます。
営業活動によるキャッシュ・フローの逆転
キャッシュ・フロー計算書も見ていきましょう。特に、企業の本業でどれだけ現金を稼ぎ出しているかを示す「営業活動によるキャッシュ・フロー」の動向は非常に重要です。
楽天グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期には6,656億7,700万円もの資金流入(プラス)があったものが、当期は一転して1,339億6,000万円の資金流出(マイナス)となりました。これは大きな変化です。
この資金流出の主な要因は、やはり「税引前中間損失の計上」とされています。営業利益は改善しているものの、先に述べた金融収益の減少や非経常的損失、持分法による損失など、営業活動の枠外で発生した損失が、最終的にキャッシュの流れにもマイナス影響を与えた形です。
営業キャッシュ・フローがマイナスになるということは、本業で現金を稼ぐ力が一時的に失われていることを意味します。企業が成長するためには、営業活動で生み出されたキャッシュを再投資に回すことが理想的ですが、資金流出となると、外部からの資金調達に頼る必要が出てきます。楽天グループはこれまでも大規模な資金調達を行ってきましたが、この状況が続けば、財務体質への懸念がさらに強まる可能性があります。自己資本の減少と営業キャッシュ・フローの流出は、今後の楽天グループの資金繰りや財務戦略において、より一層の注視が必要となるでしょう。
楽天グループの今後の戦略と展望:苦境を乗り越える道筋
今回の決算発表は、楽天グループが直面する課題の大きさと同時に、それを乗り越えようとする強い意志と具体的な進捗を示すものでした。では、今後楽天グループはどのような戦略で、この苦境を乗り越え、成長軌道に乗ろうとしているのでしょうか。
売上二桁成長とNon-GAAP営業利益黒字化目標の実現性
楽天グループは、2025年12月期の連結業績予想において、株式市況の影響を大きく受ける証券サービスを除いた連結売上収益について、2024年12月期に比べ二桁成長を目指すとしています。そして、Non-GAAP営業利益についても、当期中の黒字化を目指す方針を明確に示しています。
これらの目標は、決して楽なものではありませんが、今回の決算で示されたインターネットサービスとフィンテックの堅調な成長、そして楽天モバイルのEBITDA黒字化という具体的な成果を見ると、その実現可能性は高まっていると言えるでしょう。特にモバイル事業が、これまでの「赤字の主因」から「収益改善の牽引役」へと転換しつつあることは、グループ全体の収益構造を大きく変えるポテンシャルを秘めています。
ただし、金融収益の不安定さや、予期せぬ非経常的費用が発生するリスクは常に存在します。これらのリスクをいかにマネージしつつ、本業での成長を確実に遂げていくかが、目標達成の鍵を握るでしょう。
エコシステム強化とAI活用への期待
楽天グループは今後も、楽天エコシステムを基盤とした新規顧客獲得、クロスユース促進に注力していく方針を示しています。楽天ポイントを核とした経済圏をさらに強固にし、ユーザーが楽天市場、楽天カード、楽天モバイル、楽天銀行といった複数のサービスを横断的に利用することで、顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高めていく戦略です。このエコシステムは楽天の最大の強みであり、今後もその強化が成長のエンジンとなるでしょう。
また、デジタル技術やAI活用によるサービス開発も重要な戦略として挙げられています。ビッグデータを活用したパーソナライズされたサービス提供、顧客サポートの効率化、そして新たなビジネスモデルの創出など、AIは楽天グループの多岐にわたる事業において、生産性向上と競争力強化の重要なツールとなります。特に、モバイル事業におけるネットワーク最適化や、フィンテック事業における不正検知など、広範な分野でのAIの活用が期待されます。
楽天モバイルについては、引き続きネットワーク品質の向上とユーザー獲得に注力していく方針です。プラチナバンドの獲得や、人口カバー率のさらなる向上、そして通信速度の安定化は、ユーザー満足度を高め、解約率の低下、ひいては新規契約数の増加に直結します。通信品質の改善は、モバイル事業の収益改善だけでなく、楽天エコシステム全体のユーザー体験向上にも繋がり、相乗効果を生み出すでしょう。
楽天グループは、短期的な損失拡大という「影」を抱えながらも、中長期的な視点では、各事業の成長とモバイル事業の改善という「光」を着実に強めようとしています。彼らがこの困難な局面を乗り越え、再び力強い成長軌道に乗ることができるのか、今後の動向から目が離せません。
まとめ:楽天グループ決算から見えてくる「攻め」と「守り」のバランス
今回の楽天グループ2025年12月期中間決算は、まさに「光と影」が同時に示された、非常に多面的な内容でした。
「光」の部分としては、まず連結売上収益が1兆1,590億円を超える二桁成長を達成し、グループ全体が規模を拡大していることが挙げられます。そして、IFRS営業損失が大幅に改善し、さらにNon-GAAPベースでは営業利益の黒字転換を果たしたことは、楽天グループが本業で着実に利益を稼ぎ出す体質への転換を進めている明確な証拠です。インターネットサービスとフィンテック事業の安定した成長、特にフィンテックの圧倒的な収益貢献は、グループの強固な基盤を支えています。そして何よりも、長年の課題であった楽天モバイルが単独でEBITDA黒字化を達成したことは、今後の収益改善に向けた大きな一歩であり、楽天グループ全体の財務健全化への期待を高める明るいニュースです。
しかし、「影」の部分も無視できません。最も大きな課題は、売上成長や営業改善の裏で、親会社の所有者に帰属する中間損失が1,244億円へと拡大した点です。その主要な要因は、Lyft関連のデリバティブ評価損に代表される金融収益の劇的な減少、そしてスポーツ事業の契約解約金やカード債権の追徴税額、証券事業の不正アクセス補償といった突発的な非経常的損失の多額計上でした。さらに、持分法投資損失や法人所得税費用の増加も、最終損失を押し上げる要因となりました。
財務面では、自己資本と親会社持分が減少し、連結自己資本比率が低下。さらに、営業活動によるキャッシュ・フローが資金流出に転じたことも、今後の資金繰りや財務体質に影響を及ぼす可能性があるため、継続的な注視が必要です。
楽天グループは、売上二桁成長やNon-GAAP営業利益の当期中黒字化という目標を掲げ、楽天エコシステムのさらなる強化、デジタル技術・AI活用によるサービス開発、そしてモバイルネットワーク品質の向上とユーザー獲得に引き続き注力していく方針です。
今回の決算は、楽天グループが成長への「攻め」の姿勢を維持しつつも、過去の負の遺産や突発的なリスクへの対応という「守り」の重要性も突きつけられた結果と言えるでしょう。楽天グループがこの光と影のバランスをいかに取り、持続的な成長を実現していくのか、今後もその経営戦略と事業進捗に注目していく必要があります。彼らの挑戦は、まさに今、正念場を迎えていると言っても過言ではありません。
免責事項:
本記事は、楽天グループ株式会社の2025年12月期中間決算発表の内容に基づき、公開情報のみから作成されたものです。掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。また、将来の業績や見通しに関する記述は、執筆時点での分析に基づいたものであり、その実現を保証するものではありません。市場環境の変化、経済状況、競争状況、あるいはその他の要因により、実際の業績が記述された内容と異なる可能性があります。投資判断はご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報の利用によって生じた、いかなる損害に対しても、筆者および運営者は一切の責任を負いません。最新かつ正確な情報については、必ず楽天グループ株式会社の公式発表をご確認ください。(参照元:楽天グループ株式会社 IR情報)