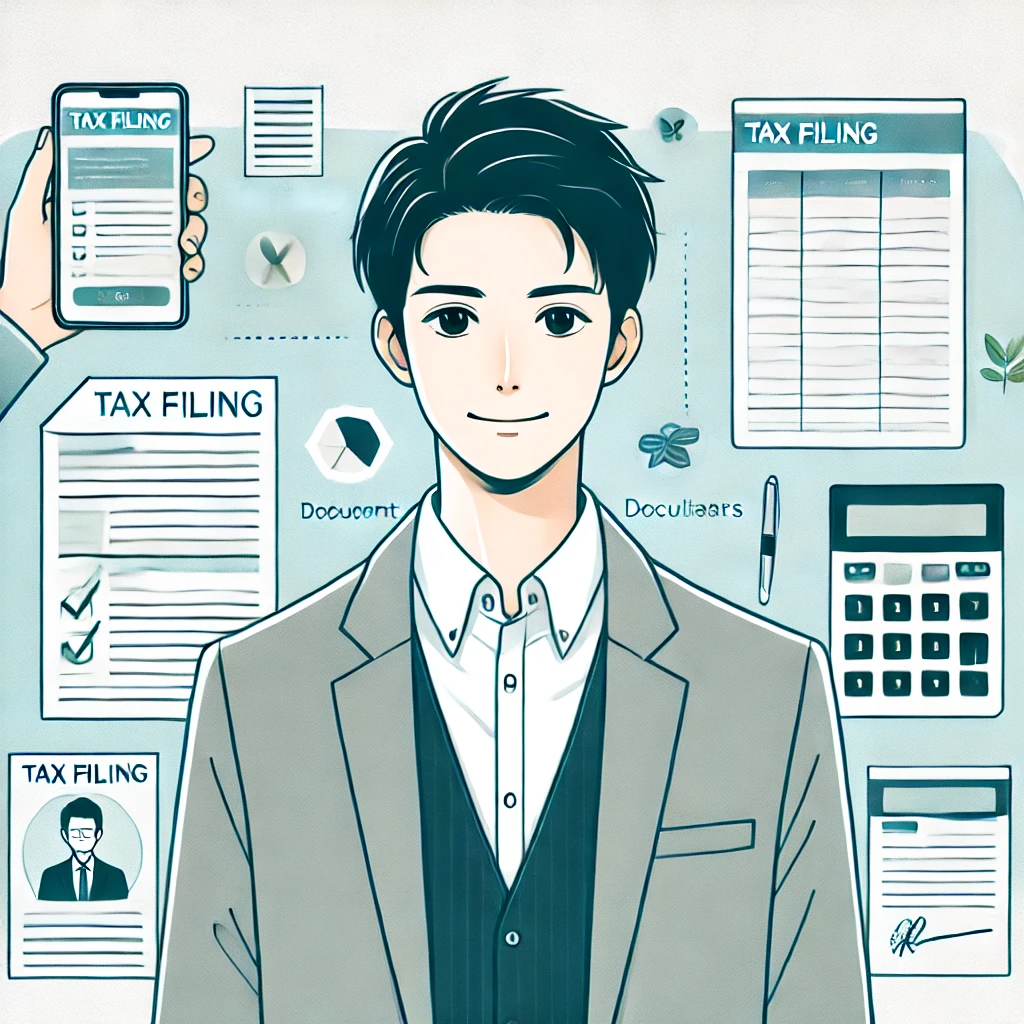
【簡単すぎる】
スマホで確定申告!
マイナンバーカードをかざすだけで完了!?
こんにちは、元・大手上場企業の財務経理部門を経て、今は「エンジョイ経理編集長」として情報発信を行っている筆者です。
2025年現在、国税庁が推し進める「スマホで確定申告」は、マイナンバーカードを使った電子申告(e-Tax)を活用することで、これまでよりも圧倒的に簡単に申告作業ができるようになりました。書面での提出や税務署への持参が不要となり、いつでもどこでも申告が可能です。
本記事では「スマホとマイナンバーカードを使った確定申告のすべて」を10,000字の長文で解説します。特に難しい専門用語の意味や、医療費控除などの複雑な入力の仕方、データ保存の重要性までカバーし、初めての方やこれまで紙で申告してきた方にも分かりやすいよう構成しました。ぜひ最後までご覧いただき、よりスムーズな確定申告手続きを実現してください。
目次
- スマホ確定申告が注目される理由
- スマホ申告に必要な準備物
- 知っておきたいキーワード一覧
- スマホを使った確定申告の全体的な流れ
- e-Taxサイトへのアクセス
- マイナンバーカード方式でのログイン
- 利用者情報の登録(初回利用時)
- 申告書作成コーナーでの入力
- 医療費控除など各種控除の入力
- 送信前の確認作業
- データ送信・結果確認
- 医療費控除の入力方法を詳しく解説
- ふるさと納税の入力時のポイント
- 年末調整を受けている方への注意点
- 提出後に必ず行いたい2つのこと
- よくある質問とつまづきポイント
- まとめ:スマホ申告で時間も手間も節約しよう
1. スマホ確定申告が注目される理由
1-1. 紙作成・税務署持参の手間がなくなる
これまでの確定申告といえば、紙の申告書に源泉徴収票や医療費の領収書などの情報をもとに自分で記入して、税務署に郵送または直接提出するのが主流でした。
しかし最近は、マイナンバーカードとスマホを使えば24時間いつでもどこでも電子申告できるようになり、郵送や税務署への持参といった手間が大幅にカットできます。
1-2. e-Taxなら還付が早い
さらに、電子申告なら「還付金の振込スピードが速い」という大きなメリットがあります。紙で申告すると、どうしても書類の処理に時間がかかりがちですが、e-Taxで送信すれば電子データで処理されるため、完了までの期間が短縮されるケースが多いのです。
1-3. データ連携で入力の手間を最小化
「医療費控除」や「ふるさと納税」など、控除入力のために必要なデータをマイナポータル経由で連携できれば、数字を手打ちする手間が減り、ミスも減らせます。
ただし、2025年現在ではまだ会社員向けの源泉徴収票データがすべて自動で連携できるわけではありません。医療費通知やふるさと納税の一部データなど、対応範囲はある程度限られるものの、一部のデータはすでにスムーズに連携可能です。
2. スマホ申告に必要な準備物
ここからは、実際に「スマホ申告」を行うにあたって何が必要かを整理していきます。
2-1. マイナンバーカード
スマホ確定申告を行うには、まずはマイナンバーカードが必要です。通知カードやマイナンバーの番号が書かれた紙ではログインできないので注意しましょう。
マイナンバーカードを取得していない方は、市区町村の窓口で申請し、受け取りを行いましょう。
2-2. マイナンバーカード対応スマートフォン
マイナンバーカードにはICチップが内蔵されており、スマホのNFC機能を用いて読み取りを行います。
2025年現在、ほとんどの最新スマホで対応していますが、機種によってはNFC機能非対応やOSバージョン制限があるので、事前にチェックしてください。
2-3. 各種パスワード
マイナンバーカードには複数のパスワードが設定されています。主に以下の2種類がe-Taxログイン時に必要となるケースが多いです。
- 4桁の数字パスワード(利用者証明用電子証明書用)
- 英数字6〜16文字のパスワード(署名用電子証明書用)
どちらも忘れると大変なので、事前に把握しておきましょう。もし分からない場合は、住民票のある自治体窓口で再設定が可能です。
2-4. 各種書類・データ
- 源泉徴収票(給与所得・公的年金など)
- 医療費通知、医療費控除の明細書(1年分の医療費を合計した通知など)
- ふるさと納税の寄付金受領証明書または連携データ
- 社会保険料・生命保険料控除証明書
- 住宅ローン残高証明書(住宅借入金等特別控除がある場合)
上記はあくまで代表的なもの。自分が申告する所得や控除内容によって、必要書類は異なります。
3. 知っておきたいキーワード一覧
確定申告は専門用語が多いため、ここでポイントとなる用語を押さえておきましょう。
3-1. e-Tax(イータックス)
国税電子申告・納税システムのこと。税務署に出向かずに申告や納税ができる国の公式サービスです。
3-2. 利用者識別番号
e-Taxを利用するにあたって登録が必要となる16桁の番号です。初めてe-Taxを使う人は、マイナンバーカードを用いて手続きすれば、その場で自動取得できます。
3-3. 確定申告書等作成コーナー
e-Taxの中にある、確定申告書や各種届出書などを作成する機能のこと。ブラウザ上で必要事項を入力すると、自動で計算・作成してくれます。
3-4. マイナポータル
政府が運営するオンラインサービスで、医療費通知やふるさと納税などのデータを連携したり、行政手続きをオンラインで行ったりできます。
ただし、一部のデータは未対応のものもあり、現時点ではすべてが完璧に連携できるわけではありません。
3-5. XMLデータ
医療費通知やふるさと納税などのデータがXML形式で提供される場合があります。これをe-Taxに読み込むことで、入力の手間を省くことが可能です。
3-6. 所得と控除
確定申告で最も大事な考え方は以下のとおりです。
(1)収入 − (2)経費 = (3)合計所得
(3)合計所得 − (4)各種控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 所得税
特に**(4)各種控除には、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)**、配偶者控除などが含まれ、それらを適切に入力しないと余分な税金を払ったり、還付を受けられない可能性があります。
4. スマホを使った確定申告の全体的な流れ
ここでは、スマホとマイナンバーカードを使った中間的なやり方(マイナポータル連携をフルには使わず、必要書類やXMLデータを読み込む方式)での電子申告フローを概説します。
4-1. e-Taxサイトへのアクセス
まずは、国税庁の「確定申告特集ページ」などからe-Taxの確定申告書作成コーナーにアクセスしましょう。
トップページにある「申告書を作成する」ボタンをタップして、申告を始めます。
4-2. マイナンバーカード方式でのログイン
ログイン方法を尋ねられたら、**「マイナンバーカード方式」**を選択します。
- 事前にマイナポータルアプリをインストールし、利用規約に同意しておく
- 画面の案内に従い、4桁のパスワードを入力
- スマホのNFC機能でマイナンバーカードを読み取り
うまく読み取れないときは、スマホをカードに密着させて少し待ち、動かさないようにするのがコツです。
4-3. 利用者情報の登録(初回利用時)
e-Taxを初めて利用する方は、マイナンバーカードの情報を読み取った後に「利用者情報登録」画面が表示されます。
ここで、住所や氏名、生年月日、連絡先などを入力し、16桁の利用者識別番号を取得します。パスワード(英数字6~16文字)設定も必要です。
ポイント:すでに利用者識別番号を持っている人は?
過去にPCなどからe-Taxで確定申告した経験がある人は、すでに利用者識別番号を持っています。その場合は、マイナンバーカード方式でログインした後、既存の利用者識別番号を入力すればOKです。
4-4. 申告書作成コーナーでの入力
ログインが完了すると、以下のステップで申告書を作成していきます。
- XMLデータの取り込み(任意)
- ふるさと納税など、XML形式のデータがあれば読み込む
- 対応していない場合はスキップ
- 収入の種類を選択
- 給与所得、公的年金、事業所得、雑所得(副業)など、該当する項目にチェックを入れる
- 収入金額などを入力
- 給与所得なら、源泉徴収票の支払金額や源泉徴収税額などを画面の指示に従って入力
- 事業所得(個人事業主)なら、経費や売上などを入力
- 控除の入力
- 寄付金控除(ふるさと納税)や生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、医療費控除など、該当する項目を選択し金額を入力
4-5. 医療費控除など各種控除の入力
控除項目ごとに画面があるので、それぞれ順番に入力していきます。医療費控除はマイナポータル連携や医療費通知のXML読み込みが可能な場合もあれば、手動入力や医療費通知の書面を見ながら合計額を入力する場合もあります。
4-6. 送信前の確認作業
入力が完了したら、計算結果と控除総額などを最終的にチェックし、申告書のプレビュー(PDF)を確認します。
PDFはスマホ上でもプレビューできますが、間違いがないかはしっかり見直しましょう。
4-7. データ送信・結果確認
問題なければ、送信ボタンをタップして電子申告を完了させます。送信結果が「正常に送信されました」となればOK。
電子申告後、数日〜数週間で税務署の審査が行われ、還付金がある人は銀行口座に振り込まれます。
5. 医療費控除の入力方法を詳しく解説
スマホでの確定申告においても、医療費控除は多くの方が該当する可能性がある重要な控除です。ここでは方法を詳細に見ていきます。
5-1. マイナポータル連携による自動入力(対応している場合)
- 健康保険組合や共済組合の医療費通知データがマイナポータルから取得可能であれば、それを読み込むことで全自動で医療費が入力される
- ただし、対応していない組合もあるため注意
5-2. XMLファイルをアップロード
- 健康保険組合などのサイトからXML形式でダウンロードできる場合は、e-Taxに読み込むことでまとめて入力が可能
- 補填金額(高額療養費・出産育児一時金など)がある場合は、マイナス分も忘れずに入力
5-3. 医療費通知を書面で受け取った場合
- 1年分の医療費が合計額で記載された通知を見ながら、金額を入力
- 通知にない期間や追加の領収書がある場合は、画面の指示に従って病院ごとに手入力する
5-4. 領収書のみの場合(1件ごと入力)
- 領収書ベースで医療費を計算する必要がある
- 病院や薬局の名前、支払った金額、日付などを1件ずつ入力
- 合計額が多い場合は手間がかかるので、エクセル等で集計しておき、「医療費集計フォーム」を使うと楽
6. ふるさと納税の入力時のポイント
ふるさと納税を行っている方は、寄付金控除として申告する必要があります。
ただし、ワンストップ特例制度を利用している場合でも、1年間に別の理由で確定申告をすると、ふるさと納税分も確定申告書に必ず記載しなくてはなりません。
- 寄附金受領証明書の内容を参考に、寄附金額を入力
- XMLデータを読み込める自治体であれば、e-Taxへのアップロードで自動入力可能
- 間違って控除を重複させたり、申告漏れがないよう注意
7. 年末調整を受けている方への注意点
会社員の多くは、年末調整で生命保険料控除や扶養控除、住宅ローン控除の一部を反映済みです。ただし、確定申告時に再度正確に入力しなければこれまで受けた控除や減税が取り消される可能性がある点に要注意です。
7-1. 年末調整はあくまで「仮の申告」
年末調整は、1月〜12月の給与所得にかかる源泉徴収税額の過不足を、おおむね正しくする仕組みです。しかし、本番の確定申告で再チェックされるため、確定申告書に正確に反映しないと控除が適用されないケースがあります。
7-2. 二重計算や未計算を防ぐ方法
- 源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料控除額」「生命保険料控除額」などの数字をそのまま入力
- 年末調整済みの控除項目も再度入力画面で確認
- ふるさと納税(ワンストップ特例含む)も、確定申告を行う場合は全額申告書に記載する
8. 提出後に必ず行いたい2つのこと
8-1. PDF保存・印刷
確定申告書の最終画面で表示できるPDFは、必ずダウンロードして保管しましょう。
- iPhone:共有ボタン→ファイルアプリやブックアプリへの保存
- Android:表示すると自動的に「ダウンロード」フォルダに保存
将来的に税務調査やローン審査などで、確定申告書控えの提示を求められる場合もあります。
8-2. e-Tax用データの保存
e-Taxの入力内容は、「.data」ファイルやXMLファイルとして保存できます。
- 翌年分の確定申告時に読み込むと手間が省ける
- 医療費控除や不動産所得など、申告内容が似ていれば、去年のデータを流用することで入力を短縮可能
9. よくある質問とつまづきポイント
ここでは、実際にスマホ申告で多くの人が疑問に思う点やトラブル事例をまとめました。
9-1. スマホのNFCが反応しない
- スマホケースを外す
- スマホをマイナンバーカードに裏面ぴったりと当てて少し待つ
- NFCの位置は機種ごとに微妙に異なるので、当たる位置を探る
9-2. パスワードを忘れた
- マイナンバーカードのパスワードは市区町村窓口で再設定が可能
- 4桁のパスワード、英数字6〜16文字パスワードの両方を正確に管理しましょう
9-3. 「利用者識別番号と暗証番号が違う」と表示された
- 過去にPCなどで利用した利用者識別番号の暗証番号と、マイナンバーカード方式のパスワードを混同している場合がある
- まずはマイナポータルアプリのパスワード(4桁)とe-Taxの暗証番号(英数字6~16文字)をそれぞれ整理しよう
9-4. ワンストップ特例は適用されないのか
- ワンストップ特例は「確定申告をしないこと」が前提
- 副収入や医療費控除など、何かしらの理由で確定申告をしたらふるさと納税分を申告書に記載する必要がある
9-5. 申告後に追加書類を出す必要はある?
- 住宅借入金等特別控除など、一部の控除は別途書面提出が必要なケースがある
- 該当者はe-Tax作成コーナーのガイドに従って、郵送する必要がある書類を確認
10. まとめ:スマホ申告で時間も手間も節約しよう
スマホとマイナンバーカードを使った確定申告は、国税庁が目指す「全国民スマホ申告化」の大きな柱となっており、今後ますます利便性が向上すると期待されています。
- マイナポータル連携で医療費やふるさと納税のデータを読み込めれば、入力ミスが減り、申告の手間も10〜15分ほどで完了
- 最初の設定(利用者識別番号の取得など)が済めば、翌年以降もデータの引き継ぎができ、申告作業がどんどん楽に
- 送信後はPDFと入力データのダウンロードを忘れずに、保管しておけば安心です
慣れないうちは専門用語の多さやスマホアプリの操作に戸惑うかもしれませんが、一度流れを把握すれば紙での手書き申告よりも格段に速く、正確に行えます。ぜひ本記事の内容を参考に、早めの準備でスムーズに確定申告を済ませてください。
重要ポイントのおさらい
- マイナンバーカード、NFC対応スマホ、パスワードの管理が必須
- e-Tax初回登録時はマイナンバーカードから利用者識別番号取得
- 医療費控除やふるさと納税のデータ連携を活用して入力を効率化
- 年末調整済みでも確定申告で抜け・重複がないか確認
- 送信後はPDFとe-Taxデータを保存
もし操作方法や制度について不明点があれば、国税庁ホームページや最寄りの税務署、そして各自治体が提供するマイナポータル関連のヘルプページをチェックするとより確実です。
以上、元・大手上場企業財務経理幹部である私、エンジョイ経理編集長が、2025年現在の最新情報をもとに「スマホで簡単!マイナンバーカード×e-Tax確定申告」のポイントを総合的に解説しました。これを機に、ぜひスマホ申告でラクして節税・還付を受け取ってください。
本記事がお役に立ちましたら、ブックマークやSNSでシェアしていただけると嬉しいです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。今後も皆さまの経理・税務のお悩みを解決すべく、有益な情報発信を続けて参ります。
(本記事は2025年2月時点の情報をもとに作成しております。制度や手続き内容は改正やシステム更新などにより変更される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。)スマホ一つで完結!マイナンバーカードとe-Taxを活用した最新「簡単確定申告」徹底ガイド


