はじめに
「4月~6月の残業代が増えすぎると、9月以降の社会保険料が高くなるかもしれない」という話を耳にしたことはありませんか? 多くの会社員にとって、4月〜6月は新年度が始まったばかりで、慣れない環境への対応や、決算期や繁忙期のあおりを受けて残業が増えやすいシーズンといえます。この時期に受け取る残業代は嬉しいものの、実は社会保険料のベースとなる標準報酬月額がこの3か月の平均給与を元に決まるため、結果的に手取り額が大幅に減ってしまう可能性があるのです。
そこで今回は、顧問の社会保険労務士(以下、「社労士」と略)に取材を行い、4〜6月の残業代増加が社会保険料にどのような影響を与えるのか、高くなりすぎる社会保険料を抑える方法はあるのか、その具体的なポイントを詳しく解説します。記事の最後には免責事項も記載しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
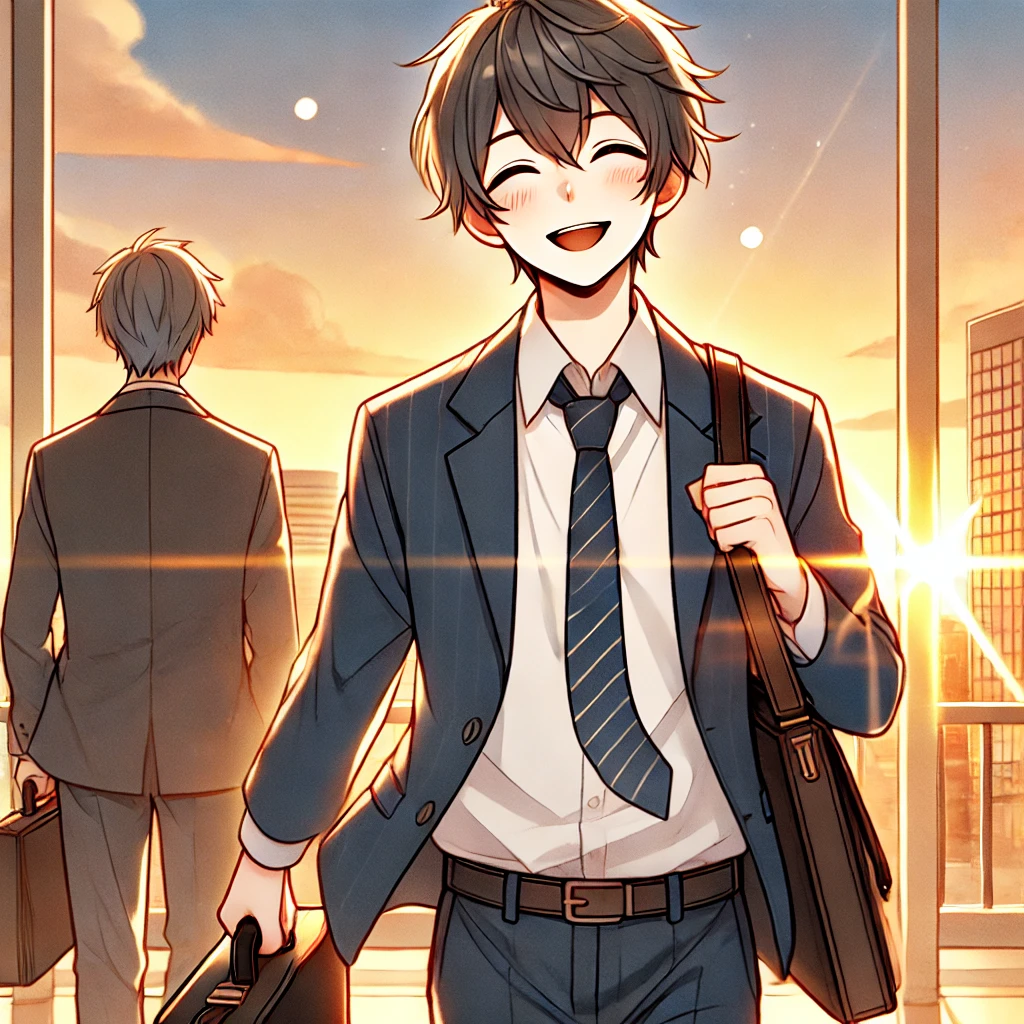
4月~6月は残業をするな
1. 4月~6月の残業代が社会保険料を引き上げる理由
新年度がスタートする4月は、企業によっては組織再編や人事異動が行われ、5月・6月はゴールデンウィークや決算作業、年度末決算からの引き継ぎなど、業種・職種によって繁忙期が重なりやすい時期です。その結果、どうしてもこの期間の残業時間が増加し、給与に上乗せされる残業代が大きくなるケースが少なくありません。
ここで問題になるのが、社会保険料は4月・5月・6月の3か月の給与平均をもとに算定されるという点です。実は、この3か月分を平均した「標準報酬月額」をもとに、毎年9月から翌年8月までの社会保険料(健康保険・厚生年金)の額が確定します。そのため、たとえ一時的に給与が高くなっただけでも、1年間にわたって高い保険料を支払い続けることになりかねないのです。
- ポイント
- 4月〜6月は新年度の繁忙期になりがち
- 残業代が増えると給与が上がり、標準報酬月額も上がる
- 9月以降の社会保険料が思わぬ高額になるリスク
4月〜6月だけ仕事が忙しく、その後は落ち着くというタイプの企業や部署に所属している方は、注意が必要です。
2. 社会保険料が上がると何が問題?
「保険料が上がるのは仕方ない」と思う方もいるかもしれませんが、社会保険料が上がることによって生じるデメリットは思いのほか大きいものです。
2-1. 手取り給与の減少
社会保険料は、給料明細における「控除欄」に記載される項目の1つ。標準報酬月額が上がると、それに保険料率を掛け合わせた金額が天引きされる仕組みになっています。つまり、標準報酬月額が1等級でも上がれば、月々の保険料負担が確実に増え、手取り額が減ることになるのです。
2-2. 会社の負担増
会社員の社会保険料は、会社と本人が折半する形で支払われています。つまり、標準報酬月額が上がれば、会社にとっても負担が増えるということ。企業にとって人件費が増大するため、コスト意識が高い企業ほどこの問題を重視しています。
2-3. 年金受給時のメリットは?
厚生年金保険料が上がると、将来的には年金額が増える傾向にあります。しかし、4~6月のみ給与が高くてその分だけ保険料を多く払うのが本当に得かどうかは慎重に判断する必要があります。短期的に残業代を稼いだ分の天引きが、後々の年金にしっかり反映されるかどうかは個人の働き方や将来の年金制度にも左右されるため、一概に「多く払っておけばお得」とは言い切れません。
3. 標準報酬月額と定時決定の仕組みを徹底解説
では、社会保険料を算出するための基礎データとなる「標準報酬月額」はどのように決まるのでしょうか。ポイントを整理してみましょう。
3-1. 標準報酬月額とは
標準報酬月額は、毎月の給与(基本給 + 各種手当 + 残業代 + 通勤手当 など)を一定の幅で区分したものです。たとえば「月収が21万円以上23万円未満の場合は○等級」というように、等級で区切られています。
3-2. 定時決定とは
毎年9月には「定時決定」と呼ばれる手続きで、4月・5月・6月の給与を合計し、3で割って平均した金額をもとに新しい標準報酬月額が決定されます。そのため、この3か月の給与が高いと、結果として9月以降の社会保険料が上昇してしまうわけです。
定時決定の流れ
- 4月・5月・6月に実際に支給された賃金を合計
- その合計を3で割って平均額を出す
- 平均額を標準報酬月額表に当てはめて等級を決定
- 健康保険・厚生年金の保険料額が9月分(10月支給給与)から変更
3-3. 随時改定との違い
社会保険料の算定には「随時改定」という仕組みも存在します。昇給や降給などで給与が大きく変わるケースでは、4~6月以外のタイミングでも標準報酬月額が変更されることがあります。ただし、定時決定とは別の要件が定められており、一般的な繁忙期の残業増では必ずしも随時改定が適用されるわけではありません。
4. 【顧問社労士に聞いてみた!】年間平均算定が使えるケース
ここからは、実際に顧問の社会保険労務士に聞いた内容を交えながら、4月~6月だけ給与(残業代)が高くなるケースで使える特例について解説します。
4-1. 年間平均算定とは
本来、定時決定は4~6月の給与平均を用いますが、業務の性質上、この期間だけ極端に給与が高くなる場合は「年間平均の給与をもとに標準報酬月額を決定する」特例が認められる場合があります。
顧問社労士によると、以下のような条件で認められる可能性があるとのことです。
- 業務の性質上、特定の時期にだけ残業代や手当が大きく増える
- 4~6月と他の期間の給与格差が著しく大きい
- 会社が申請し、年金事務所や健康保険組合が認めた場合
例えば、3月決算の企業で4月〜6月にかけて決算作業が集中し、残業代が著しく増える経理担当者や、税理士事務所に勤務していて「確定申告の時期(2〜3月)から年度末処理」が続く方などが該当しやすいようです。
4-2. 等級差が2等級以上のときが目安
年間平均算定を適用するには、4~6月における給与を元にした標準報酬月額と、1年間トータルで見た平均給与から算出した標準報酬月額に2等級以上の開きがあるなどの基準を満たす必要があります。
顧問社労士曰く「具体的な金額ベースで見ると、月にして3〜4万円以上の差が継続的に生じていれば可能性がある」とのこと。ただし、最終的には年金事務所や健康保険組合が認めるかどうかが鍵になるため、会社を通じて申請が必須となります。
4-3. 会社への申請が必要
年間平均算定の特例は、社員個人が直接申請するのではなく、事業主(会社)が申請する手続きです。そのため、まずは総務・人事担当者や上司に「4~6月だけ給与が極端に高くなるので、年間平均算定ができないか」と相談する必要があります。
顧問社労士によると、会社としても社会保険料の事業主負担が軽減できるメリットがあるので、「制度自体を知らなかった」ケースであっても、情報を提示すれば前向きに検討される可能性が高いそうです。
5. 4~6月の残業を抑える?それとも年間平均算定?4つの対策
顧問社労士からは、4~6月の繁忙期における社会保険料対策として以下の4つの方法が挙げられました。それぞれのメリット・デメリットを把握し、自分の働き方や会社の状況に合わせて検討してみましょう。
5-1. 会社へ「年間平均算定」の相談をする
まず最優先で考えたいのが、前章で紹介した年間平均算定の適用です。
- メリット: 残業代をあまり気にせず、繁忙期にしっかり稼いだ分の給与を受け取れる。会社負担も下がるため理解が得やすい。
- デメリット: 必ず認められるわけではなく、要件を満たすかどうかのチェックが必要。会社の協力が不可欠。
5-2. 繁忙期をずらす・業務分担を見直す
業務の段取りを組み替え、4〜6月に集中している仕事を他の時期に分散できないか検討する方法です。
- メリット: そもそも4〜6月だけ極端に残業が増える状況を緩和できれば、自然と標準報酬月額も安定しやすい。
- デメリット: 業種や取引先の都合で、簡単に繁忙期をずらせない場合が多い。社内調整が大変。
5-3. 短期的な有給休暇取得で給与額をコントロール
どうしても4〜6月に残業が増えるが、個人的に休暇を取りやすいなら、一時的に有給休暇を活用して給与額を調整する方法も考えられます。
- メリット: 自分の裁量で休暇を取得できれば、残業代の急激な増加を抑えられる可能性がある。
- デメリット: 給与が下がるため、せっかくの残業代を減らすことになる。本末転倒という見方もある。
5-4. サービス残業は絶対にNG
顧問社労士からも強く注意を受けたのが、サービス残業で調整するのは絶対に避けるべきという点です。
- サービス残業をしてはいけない理由
- 労働基準法に違反する恐れがある
- 将来の年金額算定にも影響し、損する可能性が高い
- 自己犠牲が長期的には体や心に悪影響を与える
どうしても残業を抑えたい場合でも、正当な残業代を受け取れない働き方は決して推奨されません。会社としても法的リスクが伴うため、根本的な業務改善や人員配置の見直しを行うことが望ましいでしょう。
6. よくあるQ&A
ここでは、4~6月の残業と社会保険料に関して顧問社労士に聞いたよくある疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 4~6月の残業を無理に抑えるべきですか?
A. 無理やり残業を抑える必要はありません。むしろ、年間平均算定の活用を検討したほうが合理的です。業務の都合で必要な残業なら、しっかり残業代を受け取るのが本来の姿。サービス残業は絶対に避け、まずは会社に年間平均算定の可能性を相談してみましょう。
Q2. 年間平均算定を使うにはどうすればいい?
A. 会社を通じて、年金事務所や健康保険組合に申請します。社員個人での申請はできません。顧問社労士によると、「4~6月だけ極端に給与が高くなる理由」を明確に示し、他の月との収入格差を証明できる資料(給与明細や勤務表など)を提出することで認められやすいそうです。
Q3. 年金額は本当に増えますか?
A. 厚生年金保険料が上がれば、将来受け取る年金(2階部分)が増える計算にはなります。しかし、4~6月の給与だけを理由に大幅な等級アップがあった場合、長期的に見たときに支払う保険料ほど年金受給額が増えるかは個人の状況や受給期間によります。特に退職時期や年金制度の改正などの要因もあるため、顧問社労士やファイナンシャルプランナーに相談して判断するとよいでしょう。
Q4. 会社が制度を知らない場合は?
A. 決して珍しいことではありません。社会保険や年金制度は改正や細かい規定が多く、実務レベルでも担当者が詳しくないことは往々にしてあります。顧問社労士がいれば直接聞いてみるのが最善ですが、いない場合は日本年金機構や健康保険組合の公式サイトを参考にして情報を伝えましょう。会社としても、保険料の事業主負担が下がるメリットがあるため、制度を知れば前向きに対応してくれるケースがほとんどです。
7. まとめ
- 4月~6月の3か月間に残業が集中すると、9月以降の社会保険料が高くなる原因に。
- 社会保険料が高くなると、手取り給与の減少・会社の人件費負担増・将来の年金受給との兼ね合いなど、さまざまな問題が発生。
- 標準報酬月額は原則として4〜6月の給与平均をもとに決定される(定時決定)。
- 業務の性質上、4〜6月だけ極端に給与が高くなる場合は、年間平均算定による特例が認められる可能性がある。
- 顧問社労士いわく、「月収ベースで3〜4万円以上の差が開く場合は要検討」。まずは会社に相談を。
- サービス残業で調整するのはNG。違法行為になる上、将来的な年金算定にも悪影響。
4月〜6月という、企業にとって忙しくなりがちなシーズンに働く人は多いもの。残業代をしっかり稼ぎたい気持ちは当然ですが、一方で「長期間にわたって高い社会保険料を払うことになるリスク」があるのも事実です。そこで年間平均算定という仕組みを積極的に活用し、無駄に高い保険料を支払わずに済むようにしましょう。
さらに、会社にとっても社会保険料は大きなコスト。顧問社労士がいる会社であれば、担当者や社労士に一度確認してみる価値があります。もしも制度を知らなかったり、要件に該当するか分からない場合でも、相談すれば具体的な対応策を示してもらえるでしょう。自分の給与明細を定期的に確認し、「なぜこんなに社会保険料が高いんだろう?」と思ったら、まずは社内の総務・人事や社労士に声をかけてみてください。
8. 【免責事項】
- 本記事は、執筆時点での一般的な情報をもとに作成しています。社会保険・年金関連の法令や運用方法は改正される可能性がありますので、最新情報は日本年金機構や健康保険組合の公式サイト等で必ずご確認ください。
- 記事内でご紹介した「年間平均算定」の適用は、一定の要件を満たす場合のみ認められます。最終的な判断は会社や年金事務所・健康保険組合に委ねられます。
- 各個人の働き方や給与体系、会社の規定によって最適な対応は異なります。具体的な対応策を決定する際は、顧問社労士や専門家にご相談ください。
- 本記事の内容を参考にしたことによって生じた損失・損害について、当方は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
4〜6月の残業代が思わぬ形で社会保険料を押し上げ、手取りが減ってしまう事態は決して珍しくありません。だからこそ、顧問社労士の知見や専門家の力をうまく活用し、正しい知識のもとで対処することが重要です。ぜひこの機会に、会社の担当者とも連携して社会保険料の負担を適正化しましょう。


