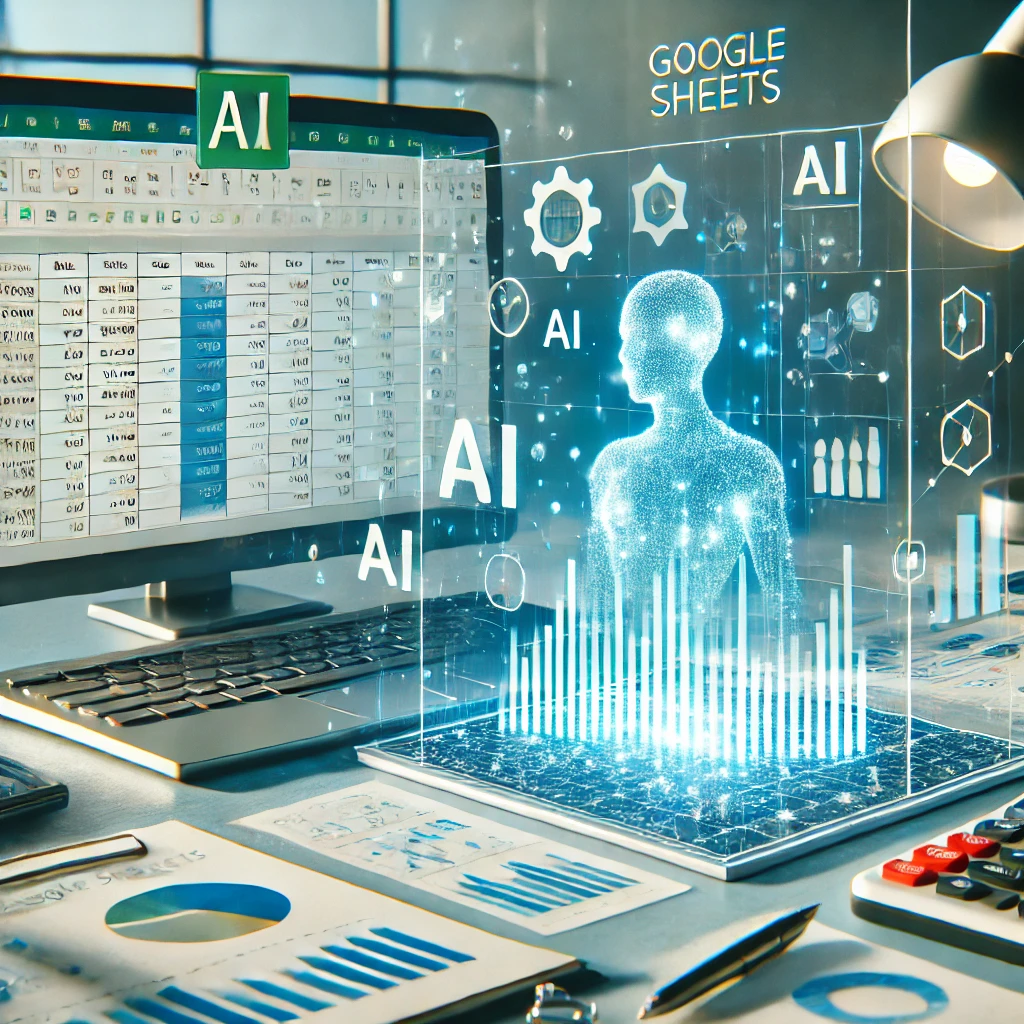
【大企業経理】
2025年は「経理スクリプト量産」で勝敗が決まる!
はじめに
皆さん、はじめまして。「エンジョイ経理」編集長です。私は以前、IT大手上場企業で財務経理の幹部を務めた経験があり、財務戦略や経営管理の最前線で数多くのプロジェクトに携わってまいりました。その中で強く感じたのは、「変化を恐れず、積極的にテクノロジーを活用できる企業や個人こそが、未来のビジネスをリードする」ということです。
昨今、多くの企業で経理担当者の退職が相次いでいると耳にします。理由として、手作業の煩雑さや残業の多さ、覚える業務の幅広さなどが挙げられますが、これらは日本企業の宿痾(しゅくあ)ともいえる構造的な問題でもあります。2023年、2024年、そして2025年と、AI技術が飛躍的に進化していく中で、経理現場でのソフトウェア活用や生成AIとの連携がいよいよ本格化し、企業間競争を大きく左右しはじめています。
この記事では、私がこれまでIT企業で財務経理の幹部として体験してきた視点を踏まえ、**2025年の経理業務の勝者となるために必要な「ソフトウェア×生成AI活用術」**を、約9000字というボリュームで解説していきたいと思います。経理や財務の仕事に携わる皆さま、あるいはこれから経理のキャリアを考えている方々が、「このままではマズい」「でも、どうやって改革すればいいのか分からない」と悩まれているなら、ぜひ最後までお付き合いください。
以下のいずれかの方法でブックマークに追加できます:
iPhoneの場合:
- 画面下の「共有」ボタン(□と↑のマーク)をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 右上の「追加」をタップ
Androidの場合:
- ブラウザのメニュー(⋮)をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 「追加」をタップして完了
第1章:経理担当者が退職する5つの理由とその背景
まずは経理担当者が退職を決意する主な理由を整理し、それが企業全体にどのような影響を及ぼすのかを考えてみましょう。企業規模を問わず、以下のような要因が特に多く聞かれます。
- 手作業の多さ
経理業務といえば「数字を扱う」イメージがありますが、現実には紙の請求書の処理やエクセルへの手入力など、細かな手作業が大量に発生します。これが日常的な負荷となり、生産性を低下させてしまうのです。 - 残業の慢性化
月末月初の締め処理や、決算時期の繁忙期における残業は避けられない面もあります。しかし、日常業務の属人的な作業に時間がかかりすぎることで、慢性的に残業せざるを得ない状況に陥るケースが少なくありません。 - 覚える業務が多岐にわたる
経理と一口にいっても、「売掛金管理」「買掛金管理」「経費精算」「月次・四半期・年次決算」「税務対応」「資金繰り」「原価計算」など、分野が非常に広いです。その上、会計システムやエクセル、各種クラウドツールの使い方まで覚える必要があり、学習コストが非常に高いのです。 - スキルアップのビジョンが見えにくい
ルーチン作業や単調な入力業務に追われていると、キャリアパスの展望が持ちにくくなります。経理業務は企業運営に不可欠な役割を果たすにもかかわらず、本人から見ると「将来、どのようにスキルを伸ばしていけるのか」が見えづらく、モチベーションが低下してしまいます。 - テクノロジー導入への抵抗感と格差
経理部門にICTやDXを導入する動きが加速している一方で、「使いこなせない」「自分の仕事が奪われる」といった不安や抵抗感を持つ人も少なからずいます。特に新しい技術やソフトウェアを積極的に使うことで、短時間で効率よく業務をこなす人と、従来の方法に固執して残業が増える人との格差が広がりがちです。
企業に及ぼす影響:経理から始まる事業停滞
経理担当者の退職が増加すると、まず真っ先に影響を受けるのは「資金繰り」の安定性や「キャッシュフロー」の管理体制です。会計や税務などは一朝一夕では身につかないノウハウが求められ、すぐに代わりを見つけるのは難しいのが現状です。
経理業務に混乱が生じれば、業務が滞り、売上や利益の計算にも影響し、経営判断や予算管理、ひいては事業そのものの成長を阻害する恐れがあります。
第2章:2025年に訪れる経理業務の大変革
ここからは、2025年に向けて急速に広がる経理業務の大変革について詳しく見ていきましょう。
既に一部の先進企業では、ソフトウェア×生成AIを活用した自動化や、担当者自身がスクリプトを組んで業務効率を高める動きが始まっています。こうした取り組みは、今後ますます重要性を増し、勝ち組企業とそうでない企業の差を決定的に広げると考えられます。
テクノロジーが変える経理の未来
- ソフトウェアによる自動化
請求書処理や経費精算など、書類のデータ入力やチェックは特に負荷が大きい業務です。これをソフトウェアによるOCR(Optical Character Recognition)やRPA(Robotic Process Automation)で自動化する企業が増えています。
RPAは一度設定すれば、決まったフローに従って膨大な手続きや入力を自動で行ってくれるため、残業が大幅に減り、正確性も向上します。 - 生成AIの台頭
ChatGPTをはじめとする生成AIは、自然言語処理の高い精度とスクリプト作成のアシスト機能を組み合わせることで、経理業務の標準化や高度化を加速させます。たとえば、会計システムに蓄積されたデータから自動で傾向分析レポートを生成する、複雑な集計式を自動で提案・作成する、会計基準や税務ルールに関する質問に応答するなど、人的なリソースを削減しながらもクオリティを維持できます。 - 担当者自身がスクリプトプログラミングを活用
2025年以降の経理現場では、従来の「プログラミングはIT部署の仕事」という認識は大きく変化するでしょう。Pythonなどのプログラミング言語を使って簡単な自動処理やデータ集計のコードを書いたり、RPAツールでシナリオ(スクリプト)を組んだりするスキルが必須になってきます。
さらに、生成AIの能力を活用すれば、担当者自身が「こんな処理をしたい」と文章で指示するだけで、半自動的にスクリプトを生成できるようになります。こうした新しい働き方が、今まさに広がっています。
第3章:ソフトウェア×生成AIを活用するメリット
ここからは、ソフトウェアと生成AIを活用する具体的なメリットについて掘り下げてみましょう。
- 業務効率の劇的向上
RPAやAIを導入することで、従来は1人あたり月に数十時間かかっていた処理を数分や数十分に圧縮することが可能になります。請求書処理、経費精算、仕訳自動化、レポート作成など、あらゆる業務領域で大幅な効率化が期待できます。 - 正確性の向上とヒューマンエラーの削減
大量の数字や手続きを扱う経理業務では、人的ミスを完全にゼロにすることは困難でした。しかし、テクノロジーによる自動化や入力支援機能を活用すれば、人的ミスを最小化できます。特に決算期などの忙しい時期にこそ自動化が威力を発揮し、チェック作業を効率化できます。 - 担当者のモチベーション向上
単調な入力作業や書類整理に追われていた担当者が、より専門性の高い分析や戦略的な仕事にシフトできるようになります。
たとえば、経営戦略のサポートや経理データを使った予実管理、KPI分析などの業務に時間を割けるようになることで、キャリアアップのビジョンが見えやすくなり、モチベーションが上がるのです。 - コスト削減と生産性向上
単純作業の自動化により、残業代や外注費用を削減できます。また、ヒューマンエラーによる修正コストの削減や、スピードアップによるプロセス全体の効率化が図れるため、企業全体の生産性を大きく向上させる効果があります。 - 経理データを活用した経営戦略の高度化
経理部門が生み出すデータは、企業の経営意思決定にとって重要な材料です。ソフトウェア×生成AIの導入によってデータ収集や集計が迅速かつ正確に行われれば、財務分析や事業計画、投資判断などに必要なデータがリアルタイムで得られ、企業の競争力が飛躍的に高まります。
第4章:自社でスクリプトプログラミングを大量に作る体制づくり
ここでは、スクリプトプログラミングを活用した経理業務自動化体制の整備について、もう少し具体的に解説します。
1. RPAツールやPythonの基本的な学習
まずは、担当者がRPA(UiPathやAutomation Anywhereなど)やPython(pandas、openpyxlなどのライブラリを活用)を使って、基礎的な自動処理を組めるようになるところから始めます。オンライン学習やセミナーに参加することで、基本的なスクリプトの書き方や処理手順は短期間で習得可能です。
2. 生成AIを補助ツールとして活用
最近の生成AIは、人間が書いた自然言語から自動的にコードを生成したり、既存のコードを最適化したりしてくれます。たとえば以下のような活用が考えられます。
- エクセルのマクロやVBAの自動生成
どうしてもエクセルを使わないといけない業務については、生成AIに「こういう処理をマクロで書いてほしい」と指示して作らせることができます。 - Pythonスクリプトの補完
集計やデータ変換などでPythonを使いたい場合、生成AIに処理の概要を日本語で書けば、コードの下書きを作ってくれます。それを担当者が確認・修正するだけで、ある程度まとまったスクリプトが完成します。 - RPAシナリオの自動提案
RPAツールで何をどう自動化すべきか迷ったとき、業務フローをAIに相談するだけで、最適なシナリオを自動生成してくれる可能性があります。
3. スクリプト管理とバージョン管理の整備
一度作ったスクリプトは、後々改変やバージョンアップが必要になるため、コードの管理が重要です。GitHubなどのバージョン管理ツールを導入し、担当者全員が同じ環境でスクリプトを保管・共有する仕組みを構築しましょう。
これにより、誰がいつどのような修正を加えたのかが一目でわかり、トラブルシューティングも容易になります。
4. セキュリティとリスクマネジメント
スクリプトによる自動化は便利ですが、誤ったコードや不正アクセスによるリスクも考慮しなければなりません。特に経理データは企業の機密情報が多いため、セキュリティ体制を整備し、テスト環境で動作を検証してから本番環境に導入するプロセスを徹底する必要があります。
第5章:経理担当者が能動的に動く組織文化
スクリプトプログラミングを活用するには、単にツールを導入するだけでなく、「経理担当者が能動的に学び、改善を試みる」組織文化が不可欠です。
1. ラーニングカルチャーの醸成
企業が積極的に学習の機会を提供し、失敗を許容する風土を作ることが重要です。たとえば、週に1度1時間程度の勉強会を開いたり、オンライン学習サービスの受講費用を支援したりすることで、担当者のスキルアップを促進できます。
2. 適切な評価制度
新しいスクリプトを開発して業務を改善した担当者を評価し、昇給や賞与に反映するなど、「挑戦する人が報われる」仕組みを作りましょう。経理や管理部門は往々にして成果が見えにくいとされますが、可視化された効率化成果を評価することで、組織全体のモチベーションを高められます。
3. 異部門とのコラボレーション
経理部門だけでなく、情報システム部門や経営企画部門と連携しながらプロジェクトを進めることで、より大きな改革効果が期待できます。部署の垣根を越えたチーム編成やワークショップを定期的に行い、情報共有とノウハウの蓄積を図りましょう。
第6章:私がIT大手上場企業で体験した事例
ここでは、私が実際にIT大手上場企業で財務経理の幹部を務めていた際に経験したプロジェクト事例を一部ご紹介します。
事例1:OCR×RPAによる請求書処理の自動化
- 背景: 月に数千枚もの請求書を人力で処理しており、確認作業やデータ入力に1人あたり月20時間以上を費やしていた。
- 導入内容: OCRツールで請求書のデータを読み取り、RPAが会計システムに自動入力するフローを構築。
- 効果: 1人あたりの月当たり作業時間が5時間以下に削減。残業削減と入力ミスの大幅減少を実現。担当者はデータチェックや分析などの付加価値業務に移行。
事例2:Pythonによる決算資料作成の効率化
- 背景: 部署ごとにエクセルで管理している売上データや経費データを、決算前に集約・加工していたが、マクロの不備や担当者による手入力が課題。
- 導入内容: Pythonとpandasライブラリを使い、各部署のエクセルデータを自動的に読み取り、決算資料のベースとなる統合テーブルを一括で作成するスクリプトを開発。
- 効果: 従来は数日かかっていた集計作業が数時間で完了。エクセルファイルを更新するだけでスクリプトが最新データを自動取り込み。決算作業全体がスピードアップ。
事例3:生成AIを活用した経理Q&Aチャットボット
- 背景: 社内で経理や経費精算のルールに関する質問が頻繁に寄せられ、担当者が対応に追われていた。
- 導入内容: 社内規程や過去のFAQを学習させた生成AIベースのチャットボットを導入。社員はチャットボットに自然言語で質問するだけで、ガイドラインや手続き方法を即座に確認可能。
- 効果: 担当者の問い合わせ対応時間を大幅に削減。チャットボットの回答内容は適宜人間がチェックし、ルール改定時にもアップデートを継続実施。
第7章:2025年に向けたアクションプラン
経理担当者の退職が相次ぎ、人的リソース不足に陥る企業は、今すぐ以下のアクションプランに取り組むべきだと考えます。
- 現状分析とKPI設定
- 手作業に費やしている時間や残業時間、ヒューマンエラーの発生率など、定量的なデータを可視化しましょう。
- これらを基に、「半年後に手作業を30%削減」「1年後にRPA導入で残業を50%減」などのKPIを設定し、組織全体で共有します。
- ソフトウェアとAIツールの導入検討
- OCR、RPA、クラウド会計ソフト、BIツール、生成AIなど、自社の状況に合ったソリューションを選定します。
- 可能であれば、複数のベンダーを比較検討し、試験導入(PoC: Proof of Concept)を行うことで失敗リスクを低減します。
- ITリテラシー向上のための教育プログラム整備
- 経理担当者が自らスクリプトプログラミングを扱えるようになるには、段階的な研修プログラムが必要です。
- 外部講師やオンライン教材の活用、社内の有志による勉強会など、多角的なアプローチが効果的です。
- 小さな成功事例の積み重ね
- 初めから大規模な自動化プロジェクトを立ち上げるのではなく、まずは請求書処理などの一部の業務から取り組み、成功事例を作ることを推奨します。
- 成功したノウハウを横展開し、段階的に自動化範囲を拡大していくことがスムーズな変革につながります。
- トップマネジメントのコミットメント
- 経理業務の改革は、現場レベルの努力だけでは難しい場合があります。
- 役員や部長クラスが経理の重要性を再認識し、必要な投資や人材育成に対して積極的なコミットを行うことが、変革成功の鍵となります。
第8章:AI時代における経理担当者のキャリアパス
ここまでご紹介した通り、今後はソフトウェアやAIを積極的に活用し、**「経理のプロフェッショナル」かつ「テクノロジーに強い人材」**として成長できるかどうかが、キャリアの大きな分岐点となるでしょう。では、具体的にどのようなキャリアパスが開けてくるのか、いくつか例を挙げてみます。
- 経理×DX推進リーダー
経理部門で培った会計知識と、RPA・生成AIなどの技術知識を兼ね備えたリーダーは、企業のDX推進において非常に貴重な存在になります。経理だけでなく、人事や総務、営業など他部門へのDX展開をリードし、経営に近いポジションで活躍できる可能性が高まります。 - 経営企画や財務部門へのステップアップ
経理データや業務の自動化に精通していれば、より戦略的な財務分析や経営企画業務にも対応しやすくなります。将来的にはCFO(最高財務責任者)やCIO(最高情報責任者)などのポジションを目指すことも夢ではありません。 - コンサルタントやフリーランスとしての独立
経理の業務フロー構築やシステム導入のノウハウを身につけることで、外部企業の顧問やコンサルタントとして独立する道も開けます。特に中小企業では、経理とITの両方に強い人材はまだまだ少ないため、高い需要が見込まれます。 - 海外進出や多国籍企業への転職
海外でも経理や財務は企業運営の重要ファクターです。グローバル基準の会計知識(IFRSなど)とテクノロジーを組み合わせることで、多国籍企業や海外スタートアップへの転職を果たすことも十分可能です。
第9章:まとめ―2025年の勝者となるために
この記事では、経理担当者の退職が相次ぐ背景から、2025年に訪れる経理業務の大変革に至るまでを、私自身のIT大手上場企業での財務経理経験を交えつつ、約9000字のボリュームで解説しました。改めてポイントを整理しましょう。
- 退職者続出の原因
手作業の煩雑さ、残業の慢性化、覚えることの多さ、テクノロジーへの抵抗感など、構造的な課題が山積しています。 - 2025年に広がる大変革
ソフトウェアと生成AIの導入、担当者自身によるスクリプトプログラミングの大量作成が進むことで、生産性と正確性が劇的に向上し、経理の価値が再定義されます。 - ソフトウェア×生成AI活用のメリット
業務効率向上、ヒューマンエラー削減、モチベーション向上、経営戦略の高度化など、多岐にわたるメリットがあります。 - 自社でスクリプトを大量に作る体制づくり
RPAやPythonなどの基礎学習、生成AIの活用、スクリプト管理とセキュリティの整備など、段階的なアプローチが必要です。 - 経理担当者が能動的に動く組織文化
ラーニングカルチャーの醸成、適切な評価制度、異部門とのコラボレーションが、経理改革を成功に導きます。 - 実際の事例
OCR×RPAによる請求書処理の自動化、Pythonによる決算資料作成の効率化、生成AIを活用した経理Q&Aチャットボットなど、多くの企業ですでに成果が出ています。 - アクションプランとキャリアパス
現状分析とKPI設定から始め、ソフトウェアやAIの導入、教育プログラムの整備、小さな成功事例の積み重ね、そしてトップマネジメントのコミットメントが重要です。経理担当者にとっては、DX推進リーダーや財務・経営企画、コンサルタント、海外転職など多様なキャリアパスが広がります。
最後に
経理の仕事は、企業経営にとって欠かせない重要な役割を担っています。そして2025年以降の世界では、経理の位置づけが「単なるバックオフィス業務」から「データドリブンな経営を支える中心的存在」へと変わるでしょう。それは必ずしも悲観的な話ではなく、むしろ新たなチャンスに溢れています。
「退職者が相次いでいる」「このままでは経理業務が回らない」といった問題に直面している企業こそ、ソフトウェアと生成AIの導入、そして担当者自身によるスクリプトプログラミングの大規模展開に挑戦してみてください。そうした取り組みを早期に行う企業こそが、2025年の“勝者”となるはずです。
未来はいつだって、変革への勇気と行動力を持った人や企業が勝ち取ります。この記事が、そんな一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。
免責事項
- 本記事は、私個人の経験や知見に基づく情報提供を目的としたものであり、特定の投資・経営判断を推奨するものではありません。
- 本記事に記載されている技術やツールの導入効果は、企業の状況や人材スキル、システム構成など、様々な要因によって左右されます。必ずしも同様の成果を保証するものではありません。
- 本記事の内容は、執筆時点での情報をもとにしており、将来的に技術や法令が変更される可能性があります。最新の情報を適宜確認のうえ、導入や実行を検討してください。
- 本記事で紹介した事例や数値は、一部プライバシー保護のために抽象化・変更している場合があります。個別具体的な検討を行う際は、専門家や該当企業にお問い合わせください。


