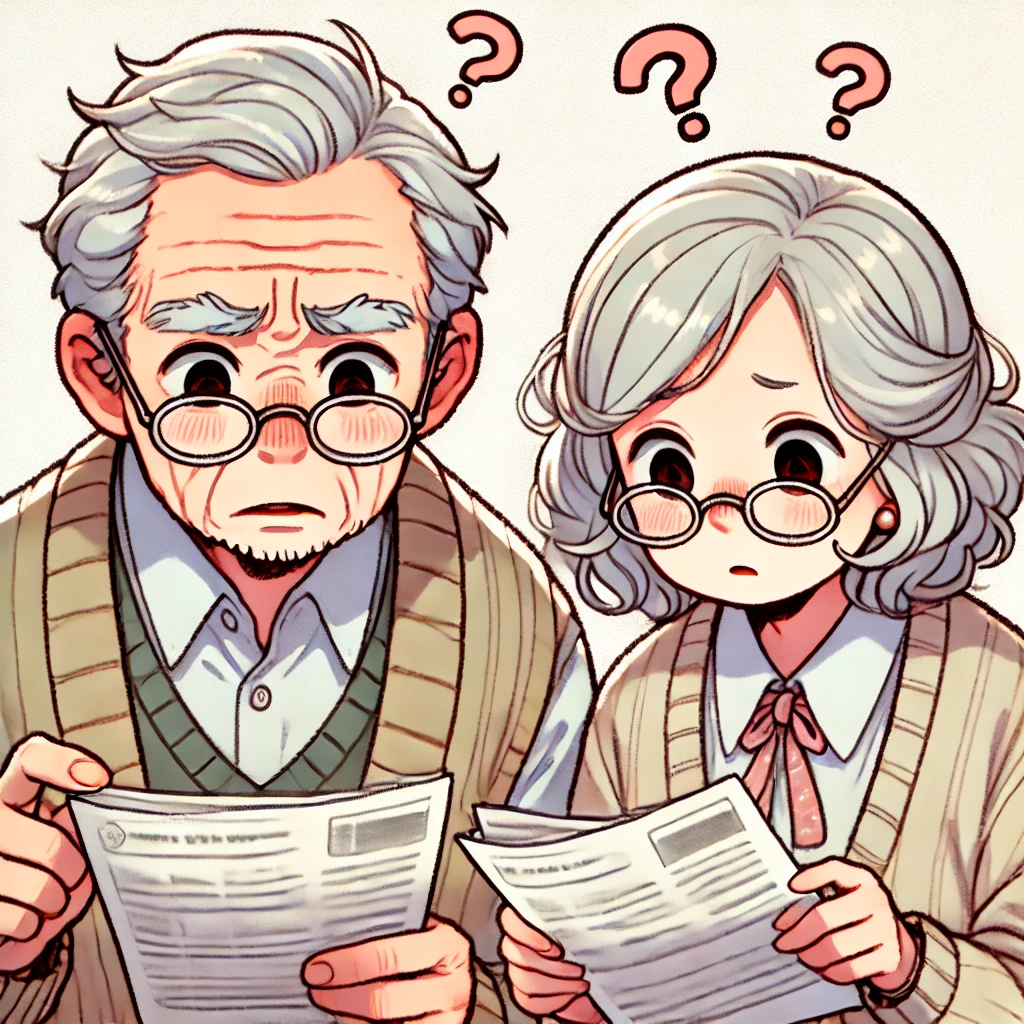
公的年金等の源泉徴収票のポイント
はじめに
皆さん、こんにちは。エンジョイ経理編集長です。私はかつて、IT大手上場企業の財務経理部門で長年幹部職を務め、多角的な視点から会社のお金の流れを管理してきました。現在は「エンジョイ経理」として、経理・財務知識から家計管理のポイントまで、幅広いトピックを発信しています。
最近、私の両親から「年金と一緒に届いた源泉徴収票を見ても、定額減税だとか不足給付だとか、何がなんだかよくわからない」という相談を受けました。調べてみると、確かに令和6年(2024年)から始まる定額減税制度、さらには不足給付(調整給付金)の仕組みなど、年金生活者にとって初めて聞くような言葉が多く、戸惑う方が多い印象です。
そこで私自身が、日頃お世話になっている顧問税理士と顧問社会保険労務士の先生方に詳しく話を聞き、両親にもわかりやすいよう噛み砕いて整理しました。本記事では、「公的年金等の源泉徴収票」にまつわるチェックポイントや、「定額減税」「不足給付金(調整給付金)」などの基礎知識を、できるだけ平易な表現でまとめていきます。
老後資金の柱となる年金は、人生100年時代と言われる現在において非常に重要です。少しでも損をしないため、あるいは正しい手続きで控除を受けるために知っておくべき情報を一通り解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
以下のいずれかの方法でブックマークに追加できます:
iPhoneの場合:
- 画面下の「共有」ボタン(□と↑のマーク)をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 右上の「追加」をタップ
Androidの場合:
- ブラウザのメニュー(⋮)をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 「追加」をタップして完了
1. 公的年金等の源泉徴収票とは
1-1. なぜ届くのか?
公的年金を受給している方(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)には、毎年1月頃に「公的年金等の源泉徴収票」が届きます。これは、支給された年金額や、源泉徴収された所得税・復興特別所得税の金額などを記載した重要書類です。
給与所得者に発行される源泉徴収票と同じく、年金も所得の一種であるため、課税対象となる人には所得税が源泉徴収される仕組みになっています。源泉徴収票をよく確認しないと、控除されるべき金額が反映されていなかったり、定額減税などの恩恵を正しく受けられていなかったりする可能性があるため、しっかりチェックすることが大切です。
1-2. いつ届くのか?
令和7年(2025年)1月で言えば、日本年金機構からは1月上旬から中旬にかけて発送される見込みです。数日~1週間ほどで手元に届くのが一般的ですが、年末年始で配達が遅れる場合などもあります。待っていても届かない場合は、年金事務所へ問い合わせてみましょう。
1-3. どのような情報が載っているか?
源泉徴収票には、主に以下の項目が掲載されます。
- 支払金額:令和6年中(具体的には2月~12月支給分など)に支払われた年金の合計額
- 源泉徴収税額:実際に引かれた所得税と復興特別所得税の合計額
- 社会保険料額:介護保険や健康保険、年金保険料などの合計額
- 適用された所得控除や、その対象となる扶養親族や障害者、寡婦(家婦)などの種別
源泉徴収票が届いたら、まずは記載されている金額に間違いがないかを確認すると同時に、「扶養や障害者控除、寡婦控除などが正しく反映されているか」をしっかりチェックしましょう。
2. 課税・非課税の違い:老齢年金・障害年金・遺族年金
公的年金を受給しているといっても、実際にはさまざまな種類があります。大きく分けると、以下のように区分されるのが一般的です。
- 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)
老後の収入をサポートする年金。原則として課税対象となり、源泉徴収票が発行されます。 - 障害年金
一定の障害状態に該当し、労働や日常生活に制限がある方向けに支給される年金。これは非課税扱いとなるため、源泉徴収票は届きません。 - 遺族年金
生計を維持していた方が亡くなったときに、遺族が受け取る年金。こちらも非課税です。源泉徴収票は届きません。
高齢者であっても、障害年金を受け取っている場合は非課税である点がポイントです。また、老齢年金と障害年金などを併給しているケースもあるので、自分がどの年金を受け取っているかをしっかり把握しておきましょう。
3. 源泉徴収票の主要チェックポイント
本章では、源泉徴収票を受け取ったら特に注意して見ておきたい項目と、その理由を解説します。
3-1. 支払金額
令和6年2月から12月など、その年に実際支給された年金の合計額が記載されています。ここにはまだ所得税や社会保険料は控除されていない“支給総額”が載っているので、「手取りの年金額」とは異なります。過去の源泉徴収票と比べて大きな差がある場合、「年金額が変わったのか」「控除申告が反映されていないのか」を見極める必要があります。
3-2. 源泉徴収税額
実際に納めた所得税・復興特別所得税の合計額をチェックしましょう。例年よりも増えていれば、扶養控除や配偶者控除、障害者控除などを申告し忘れた可能性があります。逆に、例年より少なくなっている場合は、令和6年(2024年)度から始まる定額減税が影響しているのかもしれません。
3-3. 適用された所得控除の有無
源泉徴収票には「本人」の欄に、障害者・寡婦(家婦)・ひとり親などの控除対象が記載される場合があります。市区町村などの証明が必要な控除(障害者控除など)は、要介護認定でも対象になるケースがあります。
- 障害者手帳を持っていないからダメだ、と諦めない
- 要介護度が高ければ自治体の認定証明により控除対象となる可能性がある
また、寡婦(家婦)控除やひとり親控除などは、夫と死別、あるいは離婚している女性が受けられる制度です。収入要件等が細かく設けられているため、自分の状況に該当しないかを確認しましょう。
3-4. 扶養親族等申告書の提出状況
年金受給者には、毎年9月頃に「扶養親族等申告書」が送付されます。これを提出しておかないと、配偶者控除や扶養控除などが受けられず、多めに源泉徴収されることになります。
過去と比べて源泉徴収税額が増えているのに、年金額自体がほぼ変わらないなら、この申告書を出し忘れた可能性が高いです。もし出し忘れたことに気づいたら、後からでも確定申告や市区町村への申告で税金の還付が受けられることがありますので、諦めずに手続きを進めましょう。
4. 定額減税の基本ルール
令和6年(2024年)度から導入される「定額減税」は、合計所得が1,805万円以下の方を対象に、所得税で最大3万円、住民税で最大1万円、合わせて4万円分の減税が受けられる制度です。
4-1. 減税の内訳
- 所得税:最大3万円
- 住民税:最大1万円
- 合計で最大4万円
さらに、扶養親族や配偶者などがいる場合は加算されるケースがあるため、家族構成によって減税額が変わる仕組みになっています。
4-2. 年金受給者への適用方法
年金から源泉徴収される所得税に対して、定額減税分を差し引いて納める仕組みです。引ききれない分は「不足給付(調整給付金)」として、後から振り込まれることがあります。これが「不足給付」という言葉の由来であり、後述する調整給付金の仕組みと合わせて理解しておく必要があります。
5. 不足給付(調整給付金)の仕組み
定額減税により年金から差し引くことができる所得税分が3万円(扶養親族がいれば加算あり)なのに対し、そもそも源泉徴収される所得税額が少ない場合、定額減税を「引ききれない」状態が発生します。
5-1. 調整給付金とは?
引ききれなかった減税分を別途補填する制度が「調整給付金」です。年金から控除されなかった所得税相当を受け取れるため、結果的に定額減税の恩恵を漏れなく享受できる仕組みになっています。
ただし、調整給付金は1回で完結するわけではなく、概算と本決算の2段階で支給されることに注意しましょう。
5-2. 2段階の給付
- 当初給付(第1次調整給付)
前年(令和5年=2023年)の所得実績などを基に、令和6年(2024年)夏以降、「これくらいは差し引き切れないだろう」と推計した金額を先行して支給する。 - 不足給付(第2次調整給付)
令和6年度分の所得税・住民税が最終確定する令和7年(2025年)以降、実際の課税状況と照らし合わせて、不足分があれば追加給付される。
5-3. 多めに受け取った場合の扱い
推計が過大で、実際よりも多く調整給付金が支給された場合でも、現在は返還を求めない方針とされています。これは自治体の事務負担を軽減する目的があるようです。もし気になる場合は、市区町村や国税当局に確認してみましょう。
6. 家族が見落としがちな控除項目と注意点
源泉徴収票を見ても、自分が本来受けられる控除が反映されていないことに気づいていない方が多いです。ここでは、特に見落としがちな控除項目をまとめます。
6-1. 障害者控除
障害者手帳を持っていない=障害者控除は受けられないと思い込んでいませんか? 実は、要介護認定を受けている場合でも市区町村が認定証明を発行すれば、障害者控除に該当することがあります。
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 同居特別障害者控除:75万円
これらの控除額が総所得から差し引かれることで、所得税や住民税が大きく軽減される可能性があります。場合によっては住民税非課税世帯となり、介護保険料や施設利用料も下がるケースがあるため、非常に重要です。
6-2. 寡婦(家婦)控除・ひとり親控除
夫と死別、あるいは離婚した女性など、一定条件を満たす場合に適用されます。
- 寡婦(家婦)控除:所得税27万円・住民税26万円など
- ひとり親控除:扶養親族がいる、年収要件を満たすなど細かな基準あり
特に、死別後に再婚していなければ、扶養家族がいなくても適用される場合があり、年金生活者にも関わってくる控除です。利用できるかどうかをしっかりチェックしておくと、将来的な介護保険料負担などが大きく変わってきます。
6-3. 配偶者控除・扶養控除
年金生活者でも配偶者や家族がいる場合、配偶者控除や扶養控除が適用されるケースがあります。扶養親族等申告書を提出し忘れると、これらの控除が適用されず、結果的に所得税・住民税を多めに払うことになるので注意しましょう。
7. 実際にあった相談事例
ここでは私の両親や、読者の方から寄せられた相談をもとに、顧問税理士や顧問社会保険労務士がどのようにアドバイスしてくれたかを簡単に紹介します。
7-1. 「源泉徴収額が増えていて年金手取りが減った」
原因
- 扶養親族等申告書を提出し忘れ、配偶者控除などが外れていた。
- その結果、所得税の源泉徴収額が増え、年金の手取りが減った。
アドバイス
- 申告書を再提出したうえで、もし過去分の申告漏れがあるなら確定申告で還付を受けるように手続きを行う。
7-2. 「要介護度3の母は障害者控除を受けられないと思い込んでいた」
原因
- 障害者手帳がないとダメだと思い、申告していなかった。
アドバイス
- 市区町村で「障害者控除対象者認定証明書」の交付を受けることで、障害者控除を適用可能。過去5年分の所得税還付請求(還付申告)も検討できる。
7-3. 「調整給付金が思ったより少ない?」
原因
- 定額減税の推計で算定された当初給付(第1次)が少なめだった。
- 実際の最終税額が確定した後、第2次の不足給付が行われる予定。
アドバイス
- 自治体から追加給付の連絡が来るのを待つ。必要書類を求められたら速やかに提出する。多く支給された人も返還不要の方針なので、落ち着いて対応する。
8. 扶養親族等申告書の重要性と提出漏れ対策
8-1. 毎年必ず送られる書類
公的年金受給者には毎年9月頃、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(扶養親族等申告書)」が送られます。扶養家族の状況や配偶者有無、障害者控除の対象者などを記入し、返送しないと源泉徴収税額に反映されません。
8-2. 出し忘れるとどうなる?
- 所得控除(配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除など)が受けられず、結果的に源泉徴収される税金が増える。
- 手取り年金が大幅に減り、生活設計に影響を及ぼす可能性もある。
もし出し忘れに気づいたら、翌年分の申告書を提出するだけでなく、確定申告や市区町村での修正申告をすることで過去分の還付が受けられるケースがあります。顧問税理士や最寄りの税務署に相談してみましょう。
9. 定額減税不足給付に関する自治体の対応と手続き
定額減税で「引ききれなかった分」が不足給付(調整給付金)の対象です。これは所得税だけでなく、住民税の納付状況にも関係してきます。
9-1. いつ支給される?
令和6年(2024年)度の所得税と住民税が最終的に確定するのは令和7年(2025年)に入ってからです。その後、順次各市区町村が不足分を計算し、支給手続きを進めることになります。支給時期は自治体によって差がありますが、早くても2025年春以降になる見込みです。
9-2. 手続きの流れ
- 自治体が対象者の所得データ(公的年金等の支払報告書、確定申告情報など)を収集
- 不足給付に該当する場合、自治体から個別に通知が来る、または直接口座振込される
- 多く給付されていても返還は求められないのが現行の方針
通知が届いたら、求められた書類を提出し、支給を受ける形です。もし該当しそうなのに連絡がない場合は、市区町村の税務担当窓口へ問い合わせましょう。
10. まとめとよくある質問(FAQ)
10-1. まとめ
- 公的年金の源泉徴収票は、年金と税金の重要情報が詰まった書類。
- 障害年金・遺族年金は非課税のため、源泉徴収票自体が届かない。
- 定額減税の適用で源泉徴収税額が変わる場合がある。
- 減税しきれなかった分は「不足給付(調整給付金)」として後日支給されることも。
- 扶養親族等申告書を提出し忘れると、控除を受けられず源泉徴収税額が増えがち。
- 障害者控除や寡婦(家婦)控除、ひとり親控除などは要件を満たしていれば大きな減税効果がある。
10-2. よくある質問
Q1: なぜ源泉徴収票に住民税が載っていないの?
A1: 源泉徴収票は所得税と復興特別所得税に関する記載が中心です。住民税は給与や年金から特別徴収されるケースもありますが、源泉徴収票には記載されないのが一般的です。
Q2: 不足給付を受け取りたいけど、自分から申請が必要?
A2: 基本的には自治体が所得データを把握しているため、該当者には通知が届きます。ただし、自治体によって手続きが異なる場合があるので、心配な方はお問い合わせください。
Q3: 過去に受けられるはずだった障害者控除を申告し忘れた。今からでも間に合う?
A3: 過去5年以内なら「還付申告」によって遡って控除を受け、所得税の還付を受けることができます。顧問税理士や税務署に相談してみてください。
11. 免責事項
本記事は、筆者(エンジョイ経理編集長・元IT大手上場企業財務経理幹部)が顧問税理士・顧問社会保険労務士や公的情報をもとに作成したものであり、法的アドバイスや税務上の正式な見解を保証するものではありません。記載内容は執筆時点での一般的な情報を元にしていますが、法改正や個別事例によって解釈が変わる可能性があります。実際の手続きや詳細なご相談は、税理士や社会保険労務士、弁護士などの専門家にお問い合わせください。記事の内容を利用することで生じたトラブルや損害について、筆者および関係者は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。


